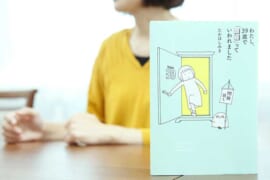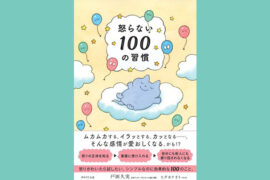賃貸住宅の退去時の原状回復費用に関するトラブル、敷金が返還されない、入居前の解約、トラブル相談窓口などについて、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、借主の立場からの解決法について連載で聞いています。(これまでの回は文末のリンク先参照)
今回(第8回)は、入居中に修理が必要になった場合、借主か貸主(家主)のどちらがどうするか、またその費用はどちらが負担するのかについて尋ねます。
給水栓、電球など小規模修繕は特約を確認する
——借主の立場から、入居中の修理に関する困ったことには、どういう事例がありますか。
穂積さん:賃貸契約期間中に、部屋の不具合に関する借主と家主のトラブルでは、次のような事例が多くみられます。
(1)キッチンや洗面所の水道栓から水が漏れている。家主に伝えたがいっこうに修理されない。
(2)トイレの電球がつかなくなった。
(3)入居時から備え付けてあった「設備」のエアコンが壊れた。
(4)入居時に張り替えてあったクロスが、継ぎ目からはがれてきた。
(5)玄関の鍵が回らなくなった。
(6)ベランダの物干し台がガタガタと揺れる。
——本連載でたびたび紹介している「民法の改正」では、これら入居中の修繕に関する内容が記されているそうですね。
穂積さん:そうです。まず、現行の民法には次のように明記されています。「賃貸人」とは家主、「賃借人」とは借主のことです。
(賃貸人による修繕等)
第606条
1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
これを受けて、東京都発行の『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版』(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf?2022=)には次のように記されています。
・貸主(家主)の修繕義務
貸主は、借主がその住宅を使用し、生活をしていく上で、必要な修繕を行う義務を負うことになっています。ただし、家賃が著しく低額であるにもかかわらず、修繕に多額の費用がかかる場合など、例外的に、貸主の修繕義務が免除されることもあります。
・借主の費用負担
借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じたキズや建具の不具合などは、借主が費用を負担して修繕を行うことになります。
・小規模な修繕の特約とは
貸主と借主との間の合意により、小規模な修繕を借主の負担とする特約を定めることができます。
電球や蛍光灯、給水栓(パッキン)、排水栓(パッキン)の取替えなどの小修繕は費用も少なく、建物に傷をつけるわけでもないので、その都度、貸主の承諾を得なくても修繕できるようにした方が、借主にとっても都合がよいと考えられます。そのため、判例においては、小規模な修繕を借主の負担とする特約は「有効」とされています。
この東京都発行のガイドラインは通称『東京ルール』と呼ばれ、全国の都道府県の自治体がこれを例に、同様のドラブル予防を呼び掛けています。つまり、このルールが適正とされて、全国で運営基準となっているわけです。
実際に訴訟になった場合は、民法や東京ルール、またこれまでくり返し紹介してきた国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html)に準じた判例となります。
——では、「小規模な修繕の特約」は、入居時に家主と交わした「賃貸借契約書」に記されているのですか。
穂積さん:賃貸借契約書の「特約」の記述を確認してください。具体的に次のように記されている場合が多いでしょう。
乙(賃借人)は、下記のような小規模(軽微)な修繕について、甲(賃貸人)の承諾を得ることなく、乙(賃借人)の負担において行なうことができ、甲(賃貸人)は修繕義務等を負いません。
障子紙・襖紙・網戸の貼り替え、コンロの点火用電池・電球・蛍光灯の取り替え、ヒューズ・給水栓・排水栓の取り替え
主に、消耗品の交換です。しかし、修理箇所の状態がどうなのか、この書面だけでは把握できず、どうすればいいかがわからない場合も多くあります。そこで必ず、家主か管理会社に、修理が必要な状況と困っていること、希望を伝えましょう。
「必要費」は家主の負担
——それぞれのケースについて、どう対処すればいいでしょうか。
穂積さん:まずするべきことは、「家主にすぐに伝えること」です。その際に、「どこが・どのように・いつから不具合なのか。緊急性はどうか」についてメモをして、写真を撮っておきましょう。
次に、それぞれの事例について考えます。
(1)キッチン、洗面所、バスルームなどの水道栓の根元や部品の継ぎ目からちょろちょろと水がしみ出てくるケースでは、内部の給水栓(パッキン)の劣化が原因と考えられます。(2)の電球の件とともに「小規模(軽微)な修繕」のケースになり、自分で取り換えられる場合は費用を自分で持ち、取り換えるとよいでしょう。
ただし、給水栓や排水栓、電球とも消耗品で、借主にすれば家主側がいつ取り変えたのかはわかりません。入居しておよそ1年以内に不具合が出た、故障した場合は、小規模なケースといえども、家主に修繕義務があります。
また、(1)の例で、水道栓によっては自分での取り換えが難しいケースもあります。その場合は業者に依頼しての交換になり、給水栓代だけではなく、業者による出張費や修理費といった費用も加算されるので、家主や管理会社に修繕を依頼しましょう。
しかしながらお悩みの例のように、家主側がすぐに修理をしてくれない場合、または水漏れでは緊急を要する場合もあるでしょう。そのようなときは民法の607条の2項(下記)によって「自分で修繕や業者を手配すること」と、608条の1(下記)によって「修繕費用を家主側にただちに請求すること」が認められています。
これを「必要費償還請求権」といい、家主側はその費用を支払わなければなりません(償還)。そのため、修繕にかかった領収書を必ず受け取り、速やかに家主側に請求しましょう。
「必要費」とは、借主が建物を目的に従った使用に適する状態のために必要な費用のことです。(1)はもちろん、(2)~(6)のケースの修繕費もすべてこれにあたります。ただし先述の通り、借主による過失や故意による故障の場合は借主による費用負担になります。
(賃借人による修繕)
第607条2 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
(賃借人による費用の償還請求)
第608条
1 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

※イメージです。
通常使用の範囲の場合は家主に修繕義務がある
——(3)~(6)のケースは小規模ではなく、大規模な修繕になりますか。
穂積さん:専門業者による補修や修繕が必要となるため、小規模な修繕とはいえません。これらのクロス、鍵、物干し台の修理のほか、部屋の扉がガタガタする、雨漏りがする、窓ガラスにひびが入った、トイレの水が流れない、窓枠(サッシ)や窓からすきま風が入ってくる、畳やフローリングなど床がきしむ音がしたり一部が浮いていたり沈んでいる、換気扇から異音がするなど、借主による破損ではなく通常使用でこうしたことが生じている場合は、家主側に修繕義務があります。すぐに連絡して修繕してもらいましょう。
万が一、賃貸借契約書の「特約」に、これらも借主が修繕を負担するという記述があっても、有効ではなく、家主側の負担となります。家主側が修繕に応じない場合は、第6回で紹介したトラブル相談窓口へ早めに相談してください。
ただし、(3)のエアコンは注意が必要です。エアコン、照明器具、温水洗浄便座、カーテンなどが入居前から付帯されている場合、それが家主側の所有物であれば「付帯設備」となるので修繕は家主側の負担となります。しかしながら、「前の住人が置いていった『残置物』」である場合は借主の負担となる場合があります。
賃貸借契約書の特約に、それらが「付帯設備」なのか「残置物」なのかが明記されているので確認してください。この件は、契約前の「重要事項説明」の際に、仲介の不動産会社の宅地建物取引士から必ず借主に説明されますが、「聞き流していた」「意味を理解していなかった」などで入居後にトラブルになるケースが多発しています。
聞き手によるまとめ
賃貸住宅の入居中に、給水栓や電球などの消耗品の損傷から雨漏りなど大規模な修繕まで、借主が壊した場合以外は家主に修繕の義務があること、ただし、主に消耗品に関する小規模な修繕の場合は、賃貸借契約書の特約に記載があれば借主が行うということです。
(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)