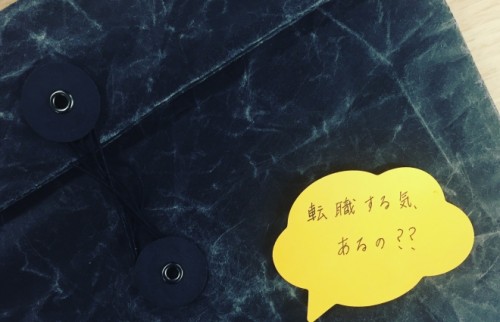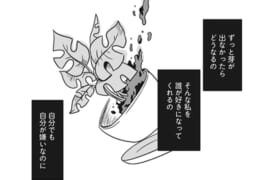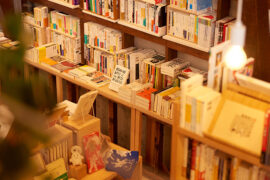「賃貸住宅から借主が退去するとき、どこまで入居時の状態に戻す必要があるのか、例えば貸主(以下、家主)に、クロスについた小さな傷やしみの弁償代を請求されたが支払わなくてはいけないのか、といった『原状回復』に関する相談は後を絶ちません」。そう話すのは、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さん。
「国民生活センター」は2023年2月1日付けで、「住み始める時から、『いつか出ていく時』に備えておこう! ―賃貸住宅の『原状回復』トラブルにご注意」といった報道資料を発表し、公式サイト内でも注意を喚起しています。
同センターによると、「賃貸住宅に関する消費生活相談は毎年3万件以上、そのうち、原状回復に関する相談件数は毎年1万 3,000~4,000 件程度。賃貸住宅に関する相談のうち約4割を占める」「相談数は月別で2~4月に増える」「当事者の年代別では、30歳代が最も多く、20歳代と40歳代を合わせると全体の7割を超える」ということです。
そこで穂積さんに、具体的なトラブルのケースと解決案や法律ではどうなっているのかについて尋ねました。
「原状回復」とは住居を元に戻すことではない
——借主が引っ越しをするとき、部屋を元の状態(原状)に戻して返す義務があることを「原状回復の義務」といい、「重要事項説明」や「賃貸借契約書」に明記されています。ただし、借主と家主の間で、どちらがどう費用を負担するのかというトラブルが多いのですね。
穂積さん:原状回復とは、借主が入居時の状態に戻す費用を負担することだと解釈されていることが多いのですが、実はそうではありません。国土交通省(以下、国交省)が策定した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、「原状回復は、賃借人(借主)が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確にしています。
家賃を支払って数年間ほど生活するわけですから、入居時の状態に回復させるということではなく、「借主の故意、過失による建物や設備の汚損、破壊、もしくは無断で間取りを変えたなどの原状を変更したときに負う責任」となります。
自然な劣化を「経年変化」、借主の通常の使用によって生ずる損傷や劣化を「通常損耗(そんもう)」と呼び、その範囲は賃料に含まれていると考えられ、家主が費用を負担することになります。
これは2020年4月に施行の民法の改正でも明確化されました。それまでは、同ガイドラインによる指針であったことが、現在は法制化されているのです。
原状回復についてトラブルになるのは主に、「『クロスの日照による色の変化』や『浴室の扉ががたがたしてきた』などの経年変化、『壁に絵をかけるためのネジ穴』や『普通の生活で付いたフローリングの傷』などの通常使用による損耗であるにも関わらず、家主が退去時に修理代として返却するべき敷金から差し引いた場合」や、「『ガス給湯器が故障ぎみ』『鍵の取り換え』など設備に関する費用を請求された」、「掃除をして退去したが、業者によるハウスクリーニング代を請求された」といったケースです。
原則として2020年4月以降に締結された賃貸借契約では、これらのことは家主側の暴利行為(民法で「相手の困窮や、知識不足・経験不足などにつけ込んで、不当に過大な利益を得ること。」であり、公序良俗違反となる)になります。
国土交通省が策定した「原状回復ガイドライン」がある
——それらの例は賃貸住宅でなくても、暮らしていると自然に発生することですね。
穂積さん:まず知っておいてほしいのは、こうした借主と貸主のトラブルには、解決のために、先ほど話した国交省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』があること、また各都道府県の自治体でも、これをもとにガイドラインを設けている場合が多いことです。
どれもウエブ上で公開され、誰もが無料で閲覧できるようになっています。例えば東京都なら『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』)、大阪府は『賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために 大阪府版ガイドライン』、福岡県は『賃貸住宅 住まいの手引き』などです。特に東京都では、2004年に通称「東京ルール」と呼ばれる「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」を制定していることもあり、ガイドラインの内容がわかりやすく、他府県の人でも判断基準の参考になります。
それらのガイドラインには、多くのトラブル事例と、借主と貸主のどちらが費用を持つべきかが明記されています。日照による自然な損耗、経年や通常の使用による汚損(おそん)や破損については、家主側が費用を持ちます。借主が弁償する必要はありません。
一方、借主による不注意、故意、過失などは、民法では「善管注意義務」(善良な管理者の注意義務)の違反といって、借主が費用を負担します。手順は、費用の明細を提示され、退去時に返還される敷金から差し引かれるか、請求書によって請求されるかのいずれかになります。先述の事例も含めて紹介しましょう。
ケース1 床・壁・天井など
家主が費用負担する例:自然損耗、経年変化したクロス、畳、フローリング、ふすまなどの張り替え、フローリングのワックスがけ、エアコンやテレビの設置時にあいた壁のビス穴や跡、壁に張った絵やポスターなどの跡、画びょうやピンなどによる穴、家具の設置によるカーペットのへこみ、設置跡、冷蔵庫やテレビなど家電の後部壁の黒ずみなど。

借主が費用負担する例:借主の手入れや管理が悪く、通常の使用や経年の変化ではなく発生したもので、カーペットに飲み物をこぼしたり、結露を放置したために拡大したシミ・カビ、冷蔵庫下のサビ跡、引っ越し作業で生じた引っかき傷、雨の吹き込みなどによる畳やフローリングの色落ち、故意の落書きなどの汚損や破損、台所の油汚れ、結露による拡大したカビ、タバコ等による畳の焼きこげ、下地ボードの張り替えが必要な重量物をかけるためにあけた壁などのクギ穴・ネジ穴など。
ただし、フローリングやクロスなど修復の単位や経過年数は別の指針があり、故意や過失で著しい故障や汚れを発生させるなどでない限り、部位や設備の経過年数が長いほど借主の負担の割合は小さくなります。具体的には次のようになります。
・畳は1枚単位で算出するが、畳表は消耗品と考えて経過年数は考慮しない(つまり借主の負担なし)。
・襖紙・障子紙は消耗品につき経過年数は考慮しない。
・畳床・カーペット・クッションフロアの耐用年数は6年(6年以上経過した住宅は借主の負担なし。それまでは6年で残存価値1円となる負担割合を算出)。
・フローリングは原則として経過年数は考慮しない、原則1平米単位での算出。
・クロスは6年。それまでの損傷などは1平米単位での算出が望ましいが、状況によって一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない。など
——これまで、筆者も複数の賃貸マンションを引っ越ししてきましたが、クロスやフローリングの通常の使用による傷でも、修繕費用を請求されたことがあります。しかもその費用の明細は不明でした。とても勉強になる情報です。次回の「ケース2 網戸・ガラス・鍵・ハウスクリーニングなど建具や設備」の原状回復について続きます。
■参考サイト
東京都『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm)
大阪府『賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために 大阪府版ガイドライン』(https://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/genzyo/index.html)
福岡県は『賃貸住宅 住まいの手引き』(https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/10949/1/chintai_tebiki_2022_page.pdf?20220707142952)
(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)