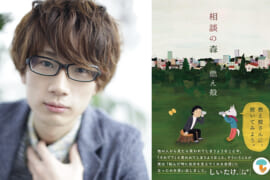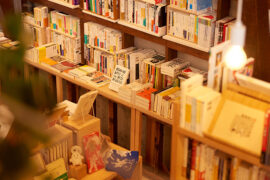2011年3月に始まり、いまだ収束しないシリア内戦。今年8月には戦闘が激化するアレッポで、ほこりと血にまみれた少年が救急車に乗せられ、静かに前を見つめる映像が世界に衝撃を与えました。
シリアから逃れた人たちの多くは、イラクやヨルダンなどの難民キャンプに身を寄せています。混迷が深まる祖国に戻ることもできず、定住することも叶わない――そんな難民キャンプで暮らす人々の姿を追うフォトジャーナリストの安田菜津紀(やすだ・なつき)さん(29)に、過酷な状況下に置かれている人たちを撮り続ける理由、そして写真を通して伝えたいことを聞きました。
父と兄を亡くして「家族」について考えた
――最初に、安田さんがフォトジャーナリストを志すことになったきっかけについて教えてください。
安田菜津紀さん(以下、安田):高校2年生の時に、NGO団体「国境なき子どもたち」のプログラムに参加し、カンボジアに取材に行きました。その時に、同世代の子どもが人身売買の被害にあっていることを知り、衝撃を受けました。
実は、私も中学2年生で父を亡くし、その後3年生の時に兄も亡くしているんです。そんな背景もあって、「家族って何だろう」とずっと考えていました。一方、世界に目を向けると、家族と暮らしたいのに暮らせず、虐げられている子どもがいる……なぜこんな不条理なことが起きるんだろうと疑問が芽生えました。そして、彼らと出会うことで「家族って何だろう」という問いに答えをくれるんじゃないか、とも思ったんです。最初のきっかけは自分本位なものでした。
――ご自身の家族とカンボジアで目にした現実が重なったことが、今の活動の原点になったのですね。
安田:そうですね。でも当時はまだ高校生だったので、何もできませんでした。ただ、多くの人に自分が見聞きしたことを伝えたいと思い、帰国してからカンボジアの児童人身売買について記事に書いて雑誌に投稿したこともありました。とはいえ、そこまで興味を抱いていない同世代の子たちに対して、いかに伝えるかを考えたとき、文章よりも写真の方が、間口の広い伝え方ではないかと思いました。「あれ?これなんだろう?」と興味を抱く最初の扉を築くのが写真の役割だと思い、フォトジャーナリストを志すようになりました。
シリアは「勢いのある優しさ」を持った国
――シリア難民のキャンプを撮影されるようになったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
安田:学生時代に、来日していたイラク人の友だちができたのですが、当時シリアは政情が安定していて、むしろ難民を他国から受け入れていたんです。その友だちが難民としてシリアに行くと聞いたので会うことになりました。その時はまだ世界中から旅行者が集まってきていたし、街も本当に美しくてシリアという国の魅力に惹かれていきましたね。
――その頃、シリアはどんな国だったのでしょうか?
安田:「人が“勢いのある優しさ”を持っている国」でした。初めてシリアにお邪魔した時に ガイドブック片手にバス停を探していたら、頼んでいないのに勝手にいっぱい人が集まってきたんです。何か騙そうとしているのかなと思って身構えていたんですけど、皆でバス停に連れて行ってくれて、バス代も誰かが勝手に払ってくれたんです。あと、風邪を引いて鼻をすすりながら歩いていたら、すれ違いざまに見知らぬ人がティッシュを渡してくれたこともありました。「人に対するおもてなしを大切にする」「困っている人を見かけたら積極的に親切にする」ことに対して、決して手を抜かない人たちなんだなと思いました。
――そんな人たちが内戦で祖国に戻れないのは何ともやるせないですね。
安田:彼らにとって優先順位の一番は家族そして人間関係、その礎の上に仕事や、その他のあらゆる営みが成り立っています。それを考えるといかに彼らが今、苦しんでいるかがわかります。ある人はシリアに残り、ある人はシリアを出てヨーロッパか隣国に逃げる。バラバラの状態になってしまったことで、大事にしていた人間関係、彼らの“すべて”だったものを壊されたわけですから。
難民キャンプで差し出されたコーヒーと毛布
――難民キャンプではどのような様子なのでしょうか?
安田:やはり皆さん本当に親切ですね。過酷な状況にもかかわらず、私が訪れると少ない食糧の中からコーヒーやお菓子でもてなそうとしてくれるんです。テント生活なのに「寒いから毛布を持っていけ」って言うんです。そんな優しさはどこからくるのかなって思います。皆で協力し合って暮らす姿が印象的です。
――現地の方とのコミュニケーションはどのようにとられているのでしょうか?
安田:私はアラビア語が話せないので、英語ができる難民の女の子が通訳として協力してくれています。実は、彼女自身も過酷な経験をしていて、お兄さんがフランスに逃れたのですがフランスは難民に対して厳しく、生活をしているうちにうつ状態になってしまい、イギリスへの密航を試みたところ船が転覆してしまったそうです。ご遺体はオランダに流れ着き、現地の警察が(遺体の)身元を探してくれたため、亡くなったことがわかったと言っていました。お兄さんは今も墓石もないところにたった一人で眠っているようです。そういう苦しみを抱えながらも協力してくれるのは、シリアの人たちに「人に対して全力で向き合う」という気持ちがあるからだと思っています。
――そうした過酷な経験をされてきた方々にレンズを向けるにあたって、心がけていることはありますか?
安田:確かに深く傷つく経験をたくさんしてきた人たちですが、悲しいだけの瞬間ばかりではありません。テントの中にいれていただくと意外な一面をかい間見ることもあります。たとえば、部屋では派手な格好をしていたり、旦那さんとキスしている写メを撮ったりと、外では決して見られない瞬間があります。そういう何気ない日常の姿も一緒に伝えたいなと思っています。
そのため、日ごろから、生活に入り込んで時間をかけてゆっくり向き合って取材をさせていただきたいと思っています。滞在する時には前回撮った写真を持って行くと喜んでいただけます。家を焼け出されいる人がほとんどなので、思い出の写真が何もないんです。そうした事情もあって、私の写真を見て、「自分たちに残った最初の思い出だ」と言ってくださることがうれしいですね。
「ただ悲惨なだけじゃない」それを伝えたい
――それは、ニュースではあまり報じられない、生活の一面ですね。
安田:私は「真実は多面性を持っている」と考えています。たとえば、日本に入ってくるニュースは精査されているので、空爆で何人死亡したとか、テロで殺されたかというような情報がほとんどですが、それを聞くと単純に私たちは恐怖を感じてしまいます。怖いという感情は人の心を遠ざけるエネルギーが強い。だから一つひとつのエピソードを伝える上でも、「最初から難民だった人はいない」ということを意識しながら、様々な背景の人たち、いろいろな思想の人たちがいる“多面性”を伝えるのが大事だと考えています。
ちなみに、熊本地震が起きた時、誰よりも早くお見舞いのメールをくれたのはシリアにいる友人だったんです。自分たちが身近な人たちの死を経験しているだけに、私たちのために祈ってくれる。シリアはそんな人たちがいる国です。
――今後の活動について教えてください。
安田:常態化した難民の現状は、ニュースになりにくいんです。でも、私は彼らに光が当てられるようにしたい。「中東」と一口にいってもすべてが戦闘地帯や危険地帯ではなく、日常が穏やかに営まれている場所もあります。黒もあれば白もある、いろんな濃さのグレーがある、それを伝えていきたいと思っています。
(末吉陽子)