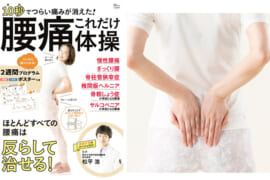特別、田舎暮らしへの憧れがあったわけではない私だが、東京に住みながらもずっと「心の原風景」みたいなのはあった。そして、その原風景とともに思い出すのが、ばあちゃんの呪文と生き様だ。
私の場合、「母の呪文」ほど「ばあちゃんの呪文」はあまり効果がなかったようだけれど……。
ばあちゃんの田舎にあった、自分だけの基地
東京で生まれ育った自分の中に、子どもの頃からあった「原風景」。
それは、ばあちゃんの家の茅葺き(かやぶき)屋根の家だ。
子どもの頃、毎年夏休みになると、母方の田舎である宮城の山奥に帰省した。
そこは、私がいま住んでいる立山町・千垣以上に本当に何もない「田舎」で、集落自体もこじんまりとした村だった。
大きな茅葺き屋根の家に、中に入ると夏でもひんやりと冷たい土間。
囲炉裏(いろり)。
たっぷりと水が張られた水甕(みずがめ)。家の裏庭にひっそりとあった小さな池と井戸。
夏はたらいに冷たい井戸水を入れてスイカを冷やした。
トイレはもちろん水洗ではなく、「厠(かわや)」という言葉が似合いそうな、家の前を流れる小さな用水路の上に建てられた「離れ」だった。
その「厠」の中には、鈍い灯かりを発する豆電球に、天井からハエ獲りの粘着テープが下がっていて、髪の毛がくっつかないよう気をつけた。
昼間でさえ「厠」に行くのは怖かった。
冠婚葬祭を家で取りしきった名残りで、家にはお布団が何組もあり、法事などで親族が一堂に集まると、ふすまをはずして、大きなお堂のようにだだっ広いスペースにお布団を敷いて、みんなで雑魚寝になった。
夏は部屋の四隅に蚊帳(かや)を張って、その中で眠った。
まるで、自分だけの基地が出来たような気分だった。
「結婚相手なんて、目と鼻と口があれば誰でもいい」
時代の流れとともに、屋根を葺き替え(ふきかえ)できる職人さんも減り、家は取り壊され、どこを切っても同じ顔が出てくる「金太郎飴」みたいな、味気もへったくれもない家に変わってしまった。
だけど、大人になってからも、ずっとこの「原風景」は胸の中に残っていて、何かの折につけてひょっこり顔を出した。
便利でも快適でもない家だったはずなのに、どこか心地よくて懐かしい記憶。
そして、この原風景とともに思い出すのがばあちゃんの言葉だ。
子ども心にばあちゃんは大変、頭がキレる人で、厳しい人だった。
じいちゃんが亡くなってから20年以上、晩年も子どもたちを頼ることなく、施設に入ることもなく、終の棲家(ついのすみか)でたった一人、暮らした祖母。
年頃になっても、ちっともおめでたいニュースのない私に、ばあちゃんは呪文のようにこう言った。「結婚相手なんて、目と鼻と口があれば誰でもいい。アフリカの人だってかまわねぇんだから」。
目と鼻と口……。
かつ、アフリカの人でもOKとは。
我がばあちゃんながら、この突き抜けた考えに爆笑してしまった。
昔の人間にしては、ずいぶんハイカラな人だったのだ。
「生き様」を見せてくれた祖母
そんなばあちゃんは、92歳の時、亡くなった。
お盆を前にした夏の暑い日、大好きな畑の上で。誰にも看取られることなく。
ばあちゃんは、おそらく前の日の夕方、畑に出かけ、そこで倒れて息を引き取ったらしい。そして、一晩、土の上で眠った。翌朝、近所の長四郎さんが、畑の上で倒れているばあちゃんを発見した。
ばあちゃんの訃報を聞いたとき、正直、ショックというよりも「あぁ、ばあちゃんは最後まで、自分らしい生き様を見せてくれたのだな」と感じた。
そう「死に様は、生き様」だ。
どのように死にたいか、から逆算して考えれば、じゃあ日々、どんな生き方をすればいいのか見えてくる。
この一瞬だって、「死に向かって生きている」ということに気づけば、誰にだって優しくなれる。
「公務員になれ」という母の呪文ほどは効果がなかった、「結婚相手なんて、目と鼻と口があれば誰でもいい」というばあちゃんの呪文。
だけど、こんな風に私の胸に響く生き様を見せてくれた祖母なのだ。
写真:松田秀明