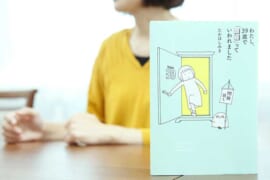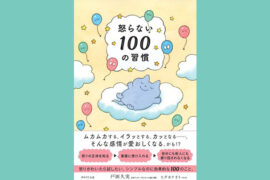いまや、スマートフォン(以下、スマホ)の操作は生活習慣のひとつとなり、起きてから寝る直前まで手放せないという人も少なくないのでは?
眼科専門医でみさき眼科クリニック(東京都渋谷区)の石岡みさき院長は、「同じ姿勢でモニターを凝視する時間が長く続くと、『スマホ老眼』の症状が現れる可能性が高まります。頻繁に使用する人は注意が必要です」と指摘をします。
そこで、「スマホ老眼」の症状が起こるしくみ、そして予防とケアの方法を詳しく聞きました。
ピントを調節する筋肉が凝って、機能が低下する
はじめに、「スマホ老眼」とはどのような状態なのかについて、石岡医師はこう説明をします。
「医学的には『調節緊張』と言います。スマホの長時間の使用が原因で老眼のような症状が現れることから、『スマホ老眼』と呼んでいます。
具体的な症状は、『目がかすむ』、『目がしょぼしょぼする』、『手元の文字がぼやける』、『夕方になると画面が見えづらくなる』、『目が疲れて頭痛がする』、『肩や首のこりを感じる』などです。目を酷使したために、ピントを調節する機能が一時的に衰えた状態です」
次に、「スマホ老眼」が起こるしくみについて、石岡医師は次のように続けます。
「私たちの目には、ものを見るときに、そのものとの距離によって自動的にピントを合わせる機能が備わっています。このピントの調節にかかわっているのが、カメラのレンズのような働きをする『水晶体』と、そのまわりにある『毛様体筋(もうようたいきん)』という筋肉です。
近くを見るときには、毛様体筋を緊張させて水晶体の厚みを増やし、遠くを見る際には毛様体筋を緩めて厚みを薄くして、ピントを合わせています。
近くにピントを合わせるためには筋肉を緊張させる必要がありますが、遠くの場合は緩めるだけなので、人間の目は本来、遠くのほうを見やすくできていると言えます。近くを見続けることは、それだけ目に負担がかかって疲れやすくなるわけです」
そうすると、スマホの画面という「近く」をじっと見続けることが目の不調を生むということでしょうか。
「そうです。一定の近くの距離にあるものを長い時間じっと見ていると、毛様体の筋肉がこり、水晶体の厚みをスムーズに調節できなくなります。これが、諸症状が現れる原因です。
また、スマホやタブレット、パソコンなどの作業中は、近くの画面に集中するためにまばたきの回数が減っています。すると目の潤いが低下するため、目の疲労度合いがいっそうと高まります」と石岡医師。
「スマホ老眼」は老眼に似た症状ということですが、老眼そのものとは違うのでしょうか。
「違います。若い人がスマホを見続けたからといって老眼になるわけではありません。老眼のような症状が現れる状態を言います。
若い人の場合は中高年に比べてピントを合わせる機能が高く、『調節緊張』に支障が出ることは少ないのですが、スマホを長時間使用すると、日常的に目に重い負担を強いていることになります。疲労や不快感が一時的なもので、休息や睡眠で回復している間はよいのですが、使用状況によっては症状が慢性化することがあります」
「スマホ老眼」の症状を自分でチェック
ここで石岡医師に、スマホ老眼が気になる場合のセルフチェックのポイントを挙げてもらいました。
(1)スマホの操作後に遠くを見るとぼやける
(2)遠くは見えるのに、近くの文字がぼやける
(3)今まではまぶしいと感じなかった光がまぶしく感じる
(4)夕方になると、スマホの画面の文字や細部が見づらくなる
(5)目の焦点が合いづらいときがある
(6)目が充血することがある
(7)目がかすむことがある
(8)目の奥が痛むことがある
(9)目が乾くことがある
(10)頭痛、頭重感がある
(11)肩のこり、首のこりがある
「これらのうち、ひとつでもあてはまれば注意が必要ですが、3つ以上の症状があれば、『スマホ老眼』の可能性が考えられます。予防やケア法を実践しましょう」(石岡医師)
30分以上続けない、40センチ以上離す、照度を抑える
では、スマホ老眼を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。石岡医師に「自分でケアする方法と予防」を伝授してもらいましょう。
「使用の継続時間、画面との距離、画面の照度、まばたきの回数がポイントです。次の7つの方法を実践してみてください」
(1)スマホを長時間、連続で操作せず、30分続けたら5~10分の休憩をとる。
(2)スマホを目から40センチ以上離す。
(3)時々、画面から目を離して遠くを見る。緊張が続く毛様体筋を緩めることになる。
(4)画面の照度を抑える。
(5)意識的にまばたきをして、涙で潤いを与える。
(6)ホットアイマスクやホットタオルで目を温める。目の周囲の血流がアップして毛様体筋のこりがほぐれる。
(7)「ピント調節機能を改善する」、また、「涙を補う」種類の目薬を活用する。
最後に石岡医師は、「休憩中に、首を回す、肩を上下するなどのストレッチも有用です。これらを1週間~10日ほど実践してもスマホ老眼の症状が改善しない、悪化する場合は、早めに眼科を受診しましょう」とアドバイスをします。
スマホに向かっていると、思いがけず時間が経っている……ということがしばしばあり、これらの症状にはいくつも思いあたります。スマホを便利に使い続けるためにも、スマホ老眼から目の健康を守るケアを毎日実践しておきたいものです。
(取材・文 ふくいみちこ、岩田なつき/ユンブル)