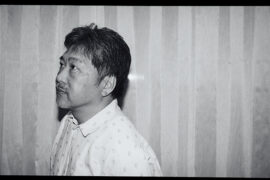元フジテレビのアナウンサーで現在は経済ジャーナリストとして活躍中の小出・フィッシャー・美奈さん(58)。
米国の投資運用会社で働いていた経験をもとに、投資業界で働く人々の実像に迫った『マネーの代理人たち〜ウォール街から見た日本株〜』(ディスカヴァー携書)を上梓しました。
小出さんは新卒でフジテレビに入社。ニュース番組のキャスターを務めたのちに記者職に転向し、外信デスクを経て37歳のときにフジテレビを退社。MBA留学後、投資業界に転職して米国でアナリストやファンドマネジャーとして活躍し、現在は経済ジャーナリストという“異色の”経歴の持ち主です。
第2回はフジテレビでのアナウンサー時代のお話を聞きます。
アナウンサーにはなったけど…
——1982年にフジテレビ入社ということは男女雇用機会均等法*が施行される以前ということですよね。当時はどんな感じだったのでしょうか?
*1985年成立、翌86年施行。採用や昇進、職種の変更などで企業が男女で異なる取り扱いすることを禁じている。
小出・フィッシャー・美奈さん(以下、小出):まだ「女子アナ」ブームも起こってなかったころだったんですが、均等法の導入前夜というか、少しずつ働く女性にとってのオポチュニティが拡大しつつあった時代なんです。
ちょうどそのころに、アメリカの三大ネットワークの男性キャスターと女性キャスターが対等にニュースを読むというスタイルが日本のテレビ局でも導入され始めたころで……。
フジテレビでは田丸美寿々さんという大先輩が日本の女性キャスターの草分けとしてニュース番組に新しいスタイルを確立して、旋風を巻き起こしていらっしゃいました。田丸さんら先輩たちが女性キャスターや女性ニュースレポーターの素地を作ってくださっていた、非常にラッキーなタイミングで入ったと思います。
——そうだったのですね。
小出:一方で、そのころのフジテレビは視聴率低迷から這い上がりつつある時期で、社内の気風も「もう何をやってもいいじゃないか」「ちょっと冒険しようじゃないか」と活性化し始めたころだったんです。会社のトップも代替わりをして、すごく冒険心に満ちていたときだったんですね。失敗してもいいから、新しいことをやろう、って。
入社した4月の改編で番組が大きく入れ替わって、できたばかりの早朝ニュース番組に新人アナウンサーの、私と、私の同期の女性の2人がつくことになりました。私の同期はベテラン男性と組んでのスタジオ担当キャスターで、私は入社式の朝からいきなり生中継の現場レポートを任されることになったんです。
——えー、入社式の朝ですか?
小出:はい。新人研修も終わっていないド素人ですよね。その頃のフジテレビにはずいぶん冒険心がありました。今でも覚えていますけれど、上野駅前の派出所に家出少年少女の問題についてインタビューをするっていう……。
——最初から重いですね。
小出:むちゃくちゃ緊張しました。こうして「面白そうだから」などと言って「ちょっと苦手な」分野に飛び込んでしまった人間の苦闘がその日から始まったわけです……。自分がいかにできないかって思い知らされる日々の始まりでしたね。
——すごい倍率の入社試験を勝ち抜いてアナウンサーになったわけですよね。それでもそう思うんですね。
小出:それこそ、まわりのアナウンサーにはサラブレッドのような人がたくさんいるんですよ。「おじはNHKでスポーツ中継をやっていました」みたいな。彼らとは入ったときから発声からして違うんです。
しかも私は関西出身だったので、「無声化」って言うんですけれど、「国鉄(こくてつ)」とか「美しい(うつくしい)」と発音したときに標準語では「く」や「つ」の母音を発音しませんが、私はしょっちゅうそれを忘れてしまう。番組が終わるたびに先輩から「また無声化ができなかったね、小出くん」と言われる日々でした。
——そんな苦労があったんですね。
小出:原稿読むのはまだいいんですけれど、実力不足を思い知らされたのは大きな発生もののニュースの対応ですね。ニュースキャスターの力量が一番問われるのは、生で何かが飛び込んできたときの対応力だと思います。入社3年目に、露木(茂)さんという大ベテランのアナウンサーと昼のニュースをやっていたときに日航ジャンボ機墜落事故*が発生し、本番5分前に御巣鷹山の生存者発見のスクープ映像が飛びこんできたんです。
*1985年8月12日に発生したジャンボ機墜落事故。羽田発大阪行き日本航空123便が群馬県・御巣鷹の尾根に墜落し、乗客・乗員計520人が死亡し、4人が重傷を負った。
「予定の原稿は全て忘れてくれ。今日はこの映像一本で行くっ!!」と編集長が大声で叫んで、予定原稿は全てボツ。ほんとに手元に何もないんですよ。まだ新人に毛が生えた状態だったので、「何をしよう」「何を喋ろう」とうろたえるしかない。そこを、長年のキャリアがある露木さんが、モニターに映る現場からの映像だけを見て一人でその修羅場をアドリブで乗り切ったんです。「使えないアナ」の私を横にして。
それを見たときに、ニュース・キャスターはこれができなきゃいけないんだとつくづく思いました。
——生の対応力ということですね。
小出:はい。それはやっぱり、天賦の才を持った上で、さらにその上で何十年と鍛えられた方ができる世界なんだと思ったわけです。アナウンサーで生対応が上手い方っていうのは、おそらく考える前に言葉が出ている、反射神経なんです。
でも、私は喋りながら自分の言っていることは本当だろうか、などと反芻(はんすう)してしまうタイプなので、どうも瞬発力にかけてしまうんです。
そんな私だったんですが、本当に恐れ多いことに、2年目からいわゆるキャスターを任されて。それから6年間ずっとニュース帯番組*を担当させていただきました。一方で、当時はアナウンサーとは言え、大きな取材現場にもかなり出してもらいました。
*「FNNモーニングワイド ニュース&スポーツ」「FNNニュースレポート6:30」「FNNスピーク」「FNN DATE LINE」を担当。
まだ二十歳そこそこの小娘だったのに、ダライ・ラマにインタビューをしたり、フィリピンのマルコス大統領追放劇のときは何回も現地に取材に行き、その時のレポートについては当時他局で仕事をされていた安藤優子さんとご一緒に、栄えある放送批評懇談会の「ギャラクシー奨励賞」までいただいてしまいました。他にもメキシコ大地震や米軍のパナマ侵攻など多くの“カオス”の海外取材現場を歩く機会に恵まれました。
——すごい……。歴史の教科書ですね。
小出:本当にある意味、戦慄を覚えるような貴重な体験をさせていただいて。自分としてはすごく恵まれているなと思う一方で、すごく葛藤があったんです。
「私はここにいてよいのだろうか」という葛藤
——葛藤ですか?
小出:私はここにいてよいのだろうか? 私はこれをやる資格があるんだろうか? という葛藤です。原稿を読んでいても中途半端にしか理解していないときもあるんです。特に昼のニュースは、世の中で動いている時間帯に記者もニュースを取材しているので、飛び込み原稿ばっかりなんですね。
記者クラブにいたりすると、10時とか10時半くらいから記者会見が始まって、それを記者が取材して、書いたものを11時くらいに本社にあげてきて、それを担当デスクや編集長がチェックして直して、ということをやっているので、アナウンサーに原稿が届くのが本番ギリギリなんですよ。
ひどい場合は、原稿が本番開始までに届かなくて下読みも出来ないままスタジオに入ることになる。しかも、当時はワープロさえ使っていない時代で手書きの原稿だったんです。
——怖いですね。
小出:記者も時間に追われて必死になって書いているから、ミミズがはったようなすごい字で書かれた原稿がくるんです。それでもどうにかこうにか読んでいると、矢印が書いてあって「前に戻る」みたいな(笑)。そういう原稿を初見で生放送で読まなくてはならないんです。
内心では冷汗タラー……なんですけれど、何事もないかのように、また自分はそのニュースを熟知しているかのように冷静沈着を装って落ち着いた声で読むわけです……。というようなことをやっているうちに、「私はこの原稿を何とか読めているけれど、きちんと内容を理解しないまま視聴者に伝えていていいのだろうか?」という思いがふつふつと湧いてきたんです。
20代前半のうちはそれでもいいですけれど、20代後半になってくると「このままこのキャリアを積んでいっていいのか?」「生半可な理解で原稿を読み、取材現場の場数も踏んでいない。それなのにニュースキャスターなどと名乗っている自分は偽物ではないのか。このままでいいんだろうか?」という自責の念がどんどん大きくなってきちゃったんです。
もっと自分で取材をしたい。それで、7年間レポーターやキャスターを務めた29歳のときに上司に「報道に行かせてください」とお願いしたんです。
※次回は5月23日(水)公開です。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)