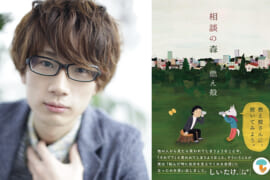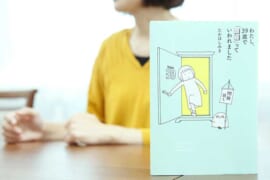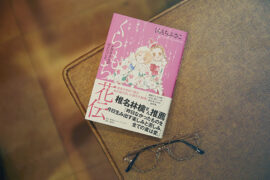「同時通訳者」と言うとどんな仕事を思い浮かべるでしょうか? 真っ先に海外ニュースの通訳や、取材やインタビューでの通訳が頭に浮かびますが、そのほかにも国際会議の同時通訳や企業の株主総会、記者会見、翻訳や執筆など「通訳」が発生するありとあらゆる場所に仕事が発生するそう。
そのため、仕事が入るたびに現場に応じた専門的な知識や用語をインプットする必要があり、「毎日が受験勉強」と言われています。
たくさんの情報をインプットして、本番には頭をフル回転させて同時通訳をする……毎日が「本番」でありとあらゆる現場をこなす同時通訳者の仕事にはきっと私たちの仕事にも役立つヒントもあるにちがいない……というわけで、同時通訳者にインプット術やタスクの整理方法、時間の使い方などの仕事術を聞きます。
お話を聞くのは、通訳・翻訳サービスを提供する「テンナイン・コミュニケーション」所属の通訳者で、ロンドンの「BBCワールド」勤務を経て現在は「CNNj」「CBSイブニングニュース」などで放送通訳者として活躍中の柴原早苗(しばはら・さなえ)さん。第1回目のテーマは「インプット術」です。
「毎日が受験勉強」ってどういうこと?
——同時通訳の仕事は「毎日が受験勉強」とお聞きしました。
柴原早苗(以下、柴原):たくさん資料を読んだりとか、本当にやることはエンドレスにあるんですけれども、今まで自分が知らなかったことを知るチャンスは貴重ですし、勉強は楽しいですよ。
——楽しみながらやってらっしゃるんですね。でも、これだけ場数を踏んできた柴原さんでも知らないことってあるんですか?
柴原:もちろんです(笑)。本当にいっぱいあって、今日もさっきCNNの同時通訳の仕事をやってきたのですが、分からない単語を本番中に書いて調べて、「家でもうすこし調べなければ!」と思いました。新しい単語に出会うと「今日も新しい単語に知り合えた!」と新しい人に知り合うような感じでうれしくなりますね。
——外国の方とのインタビューの仕事もあるんですね。事前準備がすべてとお聞きしたんですが、具体的にどんな準備をするんですか?
柴原:まずは、インタビュー対象者がどこのどなたでどういうバックグラウンドを持っているのか、本を出していれば本を取り寄せます。原書を読むのは大変なので翻訳本があればそこから拾い読みして、雑誌記事やインタビュー記事など、ありとあらゆる書籍や記事に目を通して、動画もあれば動画も見ます。そして自分で単語リストを作ったりします。
——通訳はインタビュアーの質問を置き換えるだけではないんですね。
柴原:同時通訳の場合、じっくりと意味を考えてから訳すというわけにはいきません。聞いた内容を瞬時に目的言語に訳出し、しかも聞き手であるお客様が一番理解しやすいようにする必要があります。また、TPOを踏まえて声のトーンへの意識も求められますし、日本語であれば同音異義語をわかりやすい「やまと言葉」に置き換える必要もあるでしょう。文化的に理解しづらい場合は通訳者が補足することもありますね。
——それにしても本当に受験勉強みたいですね。準備期間はどのくらいなんでしょうか?
柴原:仕事を割り当てられてから当日までが準備期間になるんですが、来週とか3日後とかケースバイケースですね。
例えば数年前に、ホロコーストの強制収容所を生き延びたという80歳くらいの学者さんにインタビューする通訳をお願いされたんですが、その方が書いた本を取り寄せ、日本語版もあったのでそれも読み、記事も読み、ホロコーストについての勉強をして、ナチスの勉強をしました。そして、インタビュー前日の夜に都内で講演会をやると聞きつけたので聴きに行きました。その方の英語に慣れようと思ったのです。
準備も勉強もすべて通訳料に入っているんですが、勉強しない人も同じお給料、勉強して自腹を切っても同じ金額です。でも、自分に投資をすることによって同時通訳の業務に良い形で反映されればと思っていますので、今の自分でできる限りの準備はします。
——ほかの仕事にも通じるかもしれないですね。“本番”のために今自分ができる限りの最大限のことをするというのは。
柴原:「人事を尽くして天命を待つ」ではないですが、自分で一通り準備したならば、当日に「不安だ、不安だ」と言っても仕方がないので、「そこまで自分はやった。以上!あとはベストを尽くすのみ」という感じで会場に行きます。
資料を読むポイントは「じっくり読まない」
——私の仕事もそうですし、企業で働いている方もプレゼンや何かの仕事をする前に資料を読みこまないといけない機会があると思うんですけれど、インプットの際のポイントはありますか?
柴原:ポイントは、やっぱり一字一句じっくり読まないことですね。本当に拾い読みでいいです。
——えっ、そうなんですか?
柴原:どこに自分が求めている情報があるかというのを探知する。探知犬のように嗅ぎつけるというか、勘を働かせて読むというようなことをしていますね。洋書では、後ろにインデックス(索引)が付いてるので、最初からは読まずに索引から調べてどんどん読み進めます。斜め読みですね。
——資料はじっくり読まなければいけないと思っていました。でも、確かにそうかも……。
柴原:岩波新書とか講談社現代新書とか、新書も読むのですが、まえがき、あとがき、目次を読んで、面白そうなところから読んで、一通り読んだらあとはダーッと空気を入れておしまいという感じです。1週間も2週間もかけません。
——そっかー、それでいいんだ。
柴原:はい。じっくり読んでいくといくら時間があっても足りないですよね。いい意味で乱暴な読み方を自分に許してあげるとすごく気が楽になります。なので、完璧を目指さないということですね。
——ざっとでもいいから全部に目を通したほうがいいですか?
柴原:少なくとも、その方のお書きになった本は読むようにしていますね。複数の本を書いていらっしゃる方でしたら、まず新しいものから読む。やはり学説やいろいろな理論は新しいものに新しい情報があると思います。
——なるほど。
専門性が高い分野は子ども新聞を読む
柴原:あと、地球環境問題やオゾン層など専門性が高い分野の通訳をする時は、まずは朝日小学生新聞や児童向け百科事典の「ポプラディア」などを見ます。
——小学生新聞!
柴原:内容を理解できているかの基準は「小学校1年生に教えられるか」なのです。ですので、大学の通訳の授業でも、例えば「北朝鮮の核開発について5歳の子供でも分かるような日本語で1分間スピーチを用意してください」という課題を出します。
いきなり「金正恩氏」や「核開発」「遠心分離機」など核関連の言葉が出てきてもわかりません。「北朝鮮という国が日本のお隣にあってね」というようにやさしく言わせます。
やはり自分が詳しく知っていることはやさしい言葉で言える。やさしい言葉で言えるということは自分の中で全部吸収できているということですね。
——なるほど。難しいことを言うと「わかってる気」になっちゃうけれど、実はわかっていなかったってこと、ありますもんね。
ネットでの情報収集は時間を決めて
——ネットでの情報を収集することもあると思うのですが……。
柴原:その場合も時間を決めてタイマーで計測しながらやっています。眠くなって寝る時も、タイマーで5分かけて突っ伏して寝ます(笑)。
やはり時間というのは、あっという間に経ってしまいます。メリハリをつけて集中したほうが断然効率がいいと思います。要は短い時間で集中してできる限りの情報収集をする、ということですね。
——次回はタスク管理術について聞きます。
(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)