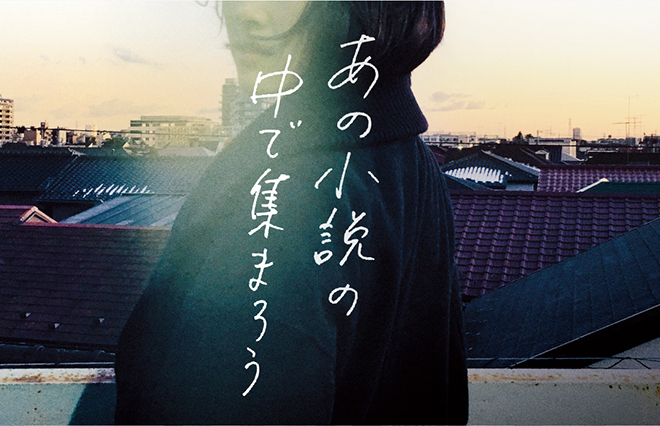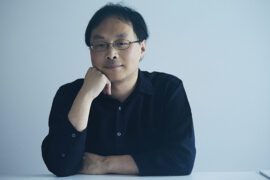ツイッターで約9万人のフォロワーがいる燃え殻さんによる初の小説『ボクたちはみんな大人になれなかった』(新潮社)が6月30日に発売されました。
燃え殻さんは、テレビの美術制作という“一般人”ながら、「日報代わりに始めた」ツイッターで多くの人の心をつかみじわじわと人気に。昨年、ウェブサイト『cakes』で連載された小説が話題を呼び、書籍化が決定。糸井重里さんら著名人からも支持を受けています。
今回、初の小説発売を記念して、ベストセラー『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)の著者・古賀史健さんと燃え殻さんが対談を行いました。
ウートピ読者から見ればおそらく“お兄さん”的な存在のお二人。3回にわたり、小説の舞台になった90年代のこと、背伸びしていた青春時代のこと、東京で働くということ、「大人」になることについて語っていただきました。
「誰かが見てくれてた」に救われた瞬間
古賀:燃え殻さんの小説は女性のセリフが印象的ですよね。「キミは大丈夫だよ、面白いもん」とか「きっと男の子が全員、男になれるわけじゃないんだよ」とか。実際に女の子から言われて記憶に残ってる言葉ってありますか?
燃え殻:「ほぼ日」のイベントの時にも話したと思うんですけど、学級新聞のエピソードかな。荒廃した高校に通っていたんですが……。
古賀:ああ、『北斗の拳』みたいな学校でしたっけ?
燃え殻:そう(笑)。不良が一番偉くて、一番怖い不良が一番可愛い子と付き合っているみたいな。そんな環境にあっても、どこか自己主張したくて、毎日学級新聞を書いていたんですよ。そして壁に貼ると、不良がちぎるんです。「うぜえよ、誰の許可取ってるんだよ」って言われて。「確かに許可は取ってないな」みたいな(笑)。
古賀:うん、それは不良も正しい(笑)
燃え殻:「すみません」って言いながらも毎日貼っていたんだけど、ある時心が折れてやめたんです。やめたら、不良と付き合ってた女の子から「あんたさ、アレやらないの?」って言われて。
古賀:ああー。
燃え殻:「読者がいた!」って。あの言葉に僕は救われたんですよね。誰かが見ててくれたっていうだけでいけるんだって。「じゃあやる」って再開して。まあまた不良がベリッて破るんだけれど……。古賀さんはいかがですか?
古賀:僕、肘のあたりにアザがあるんですが、すごく嫌で気にしていたんです。特に思春期は。サポーターしたり、腕を隠すクセがあったりするくらい。大学生の時に、ある女の子が肘のアザを見て「わ、カッコイイ!」って言ったんです。「そういうふうに見えるんだ」って救われましたね。
小説を書いたことで「針が回り始めた」
古賀:今回、一冊の小説を書き終えていまの心境はどうなんですか?
燃え殻:前に「cakes」での連載が終わった時、担当の編集者さんから「成仏しましたか?」って聞かれたんですよ。正直、あのときは全然成仏していなくて。むしろかさぶたから血が出ちゃった、みたいな。全然スッキリしなかった。でも、今回小説を書いてみて、心から満足したんです。
古賀:わかります。あれだけ書き上げれば、なにも後悔ないだろうなーって。
たぶん僕たち、心のどこかに「90年代で止まっている時計」が掛かってるんですよ。アナログの、壁掛け時計が。これ、デジタルの時計だったら電池が切れて、液晶そのものが消えちゃうんだけれど、アナログだから、ずっと「止まったまま」なんです。3時15分なら3時15分を指したまま、針が止まっている。
終わってない感とか、やり残した感が、嫌でも目に入っちゃうんですよ、それは。でも、燃え殻さんの場合、今回これだけの小説を書き上げたことで、止まっていた針が回り始めたんじゃないかな。
燃え殻:そうなのかなあ。
古賀:僕も『嫌われる勇気』を書いた時、それに近い思いがあったんです。20代でアドラー心理学の本を読んで、それまでいろいろ悩んできたことが「アドラー的に見たらこういうことなのかな」と整理ができた。
でも、整理するだけじゃダメで、言葉としてアウトプットしないと「成仏」できない。苦しかったけど、あの本を書きあげた時に、誰がどう評価するかわからないにしても、自分の中ではこれ以上のものは書けないだろうな、という満足感があったんです。
燃え殻:「成仏」したんですね。
古賀:そう。これって技術の話じゃないですよね。20、30代と、僕で言うとセンター街の思い出とか、もっとみじめな思い出とか、恥ずかしいことや辛いことがたくさん積み重なってようやく、仕事上での達成につながる。そういう、恥ずかしい人生を、ちゃんと恥ずかしく生きずに、ショートカットで効率的に技術だけを覚えたとしても、「成仏」には至らなかったんじゃないかなあ。
「生きててよかった」って思えるとき
燃え殻:なるほど。それに近いところで言うと、今回僕が小説を書けたのは「僕がこれから書こうとしているのは普遍的なことなんじゃないか」っていう気持ちがあったからなんです。「これはアートだ! 誰もわからなくても俺はやるんだ!」という思いではなくて、きっとわかってくれるんじゃないか、みたいな。
僕が出会ってきた人たちって、絶対に『anan』のグラビアは飾らない人たちなんだけれど、僕は彼ら彼女らの人生が尊くて大好きで仕方がないんです。みんなも、本当はそうなんじゃないかな。「私にとってのこの人は、“キムタク”より大切だ」って。そんなの当たり前じゃないですか。
たとえば(小説に登場する)関口や「彼女」は、社会で特別にピックアップされることはないかもしれないけれど、そういう人間に人生を教えてもらったり、そういう人間に会えたから僕の人生よかったって思えたりするもんじゃないかな。
みんなにそれぞれの関口とか「彼女」みたいな人がいて、誰に言っても自慢にならないけれど、そいつに会えたから、今自分がここにいるなって思えるのって普遍的なことだと思うんです。そういうことのほうが僕は「生きてる」「生きててよかった」って思うんですよね。それが小説を書いていいたかったことです。言い訳に近いけど。
古賀:うん。さっきの学級新聞で言ってた「見ててくれる人がいた」じゃないけど、燃え殻さんも僕も、基本的に自分の実力、腕一本でのし上がったとかじゃないんですよね。ただ「誰かに見つけてもらった」なんですよ。
少なくとも仕事であなたがちゃんとやっていれば、誰かがあなたのことを見つけてくれる。あなたのがんばりを見ている人はいるし、いつか、誰かがスポットライトを当ててくれる。そう信じてないとやってられないってのもあるけれど、やっぱり信じていいんじゃないかなって思うんですよね。
※対談3回目は7月2日公開です。
(構成:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)