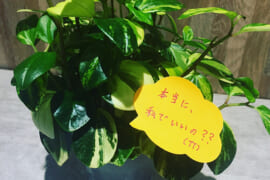ツイッターで約9万人のフォロワーがいる燃え殻さんによる初の小説『ボクたちはみんな大人になれなかった』(新潮社)が6月30日に発売されました。
燃え殻さんは、テレビの美術制作という“一般人”ながら、「日報代わりに始めた」ツイッターで多くの人の心をつかみじわじわと人気に。昨年、ウェブサイト『cakes』で連載された小説が話題を呼び、書籍化が決定。糸井重里さんら著名人からも支持を受けています。
今回、初の小説発売を記念して、ベストセラー『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)の著者・古賀史健さんと燃え殻さんが対談を行いました。
ウートピ読者から見ればおそらく“お兄さん”的な存在のお二人。3回にわたり、小説の舞台になった90年代のこと、背伸びしていた青春時代のこと、東京(都会)で働くということ、「大人」になることについて語っていただきました。
古賀「ようやくクラスメイトに会えた気持ちでした」
古賀:燃え殻さんと初めてお会いしたのは去年の春。ツイッター上で知り合ったのをきっかけに、糸井重里さんを囲んでお食事会をすることになって。ものすごく不思議な縁なんです。
燃え殻:失礼がないように早めに行かなきゃと思って行ったら、すでに古賀さんが立って待っていて。お店の人だと思って「すみません、ここで大丈夫ですか?」って聞いたら「間違いございません」って言うから「あ、お店の人だ」と思って。
古賀:そうそう(笑)
燃え殻:僕たち同じ歳なんですよね。
古賀:最初は、同じ歳だってことも知らなかったし、燃え殻さんの本名さえ知らない。正直言うと、「cakes」の連載も知らなくて、うちの奥さんが「これ、すごいいいから読んだほうがいいよ」って勧めてくれたんです。彼女も僕らと同級生なんで、同じ時代を生きた人間として感じるところが多かったんだと思う。
いざ連載を読み進めると、僕と親和性が高いんだけど、この人は一歩間違えたら危ないやつかもしれないって思っていて(笑)。ほら、作品はすごくいいんだけど、現実生活は破綻している作家さんっているじゃないですか。いや、いるんですよ。それで、この燃え殻さんって人はどっちなのかなあ……って少し不安でした。
でも、お会いしてみたらちゃんとしてるし、逆に僕よりしっかりしているくらいで。僕はずっとフリーランスでライターをやってきて、燃え殻さんみたいにひとつの会社に勤め上げる経験はなかったので。
燃え殻:僕の古賀さんのイメージは、今までしっかり計画性を持っていろいろなことをやってらっしゃってきて、『嫌われる勇気』で地位を確立した方なんだろうなと。なので、最初はメガネ店の店員をやられてたと聞いてびっくりしました。
古賀:大学卒業後、地元の福岡でメガネ店の店員をやっていたんですが、1年くらいで辞めちゃいました。そのあとは無職期間がしばらく続いて、地元の編プロに入って、ようやく上京したんです。
燃え殻:僕はずっと同じ場所にいるんです。同じ場所って言っても、いつ沈むかわからない船に乗っているような感じで。だから、古賀さんと話していて、ある種の近しいものを感じたんです。年齢だけじゃなくて、「安定した時期が少なかった」という部分に。
古賀:そう、ひと言で言うと、僕たち“出自”が悪いんですよね(笑)。
燃え殻:そうそう。古賀さんと初めて会った集まりの時も、シェフの方が(調理法で)「こういうのもできるよ」とか「ああいうのもできるよ」とか言われて、みんな料理の名前をよく知っているんですよ。僕は「あ、それ丸焼きでいいです」って言いたくてしょうがなかった。「うん、それでそのアワビはどういう目にあうんだ?」みたいな。
古賀:僕も、いまは仕事でエリート編集者さんばかりに囲まれてありがたいし嬉しいんだけど、やっぱり「育ちが違うなあ」と痛感させられる機会は多くって……。だから燃え殻さんに会った時はようやくクラスメイトに会えた感じでした。年齢もそうだけど、いろんな意味で「同じクラス」にいた感じがすごかった。
燃え殻:うん、まったく同じ気持ちでした。
燃え殻「『小説って何?』って聞いて回ったんです」
燃え殻:古賀さんが上京したのは社会人になってからだったんですね。
古賀:そうですね。福岡の編プロ兼出版社に就職して、東京に子会社があったので転勤願いを出して1997年に東京に来ました。23か24くらいだったかな。
燃え殻:僕の小説の舞台と同じ頃ですね。
古賀:そう。あの『ボクたちはみんな大人になれなかった』って小説は、これまでになかったタイプのフォークロア小説だと思います。たとえば1960年代を振り返った小説は、村上春樹さんとか村上龍さんとかいろいろな方々が書いていますよね。
ところが90年代は、映像や音楽の分野ではしっかりその時代を表現しているものがあるんだけど、小説ではあまり記憶がないなって。あの当時の、どうしようもないくらいダメだった僕たちのことを、こんなにリアルな郷愁として見せてくれる小説は読んだことなかったです。
あと、これは絶対言いたいんですが、「cakes」での連載当時と、今回出版される小説はまったく違う作品。文学的に磨き抜かれたものになっているので、ぜひ本を手にとってほしいですね。
燃え殻:あ、ありがとうございます。
今回、新潮社から小説として出すと決まった時に、新しいことをしないといけないなって思いました。あのウェブ連載のまま出すわけにはいかないと。ただ、そこから悩みまくって、もう「そもそも小説って何なんだろう?」ってレベルの疑問にまで降りていったんですよ。実際、いろんな人に「小説って何?」って聞いて回ったくらいで。
古賀:なにか答えは見つかりました?
燃え殻:うーん。二村ヒトシさんに聞いた時は「一般的な事言っていい? 小説ってのはね、最初と最後で主人公が変わっていること。よくても悪くても」って答えで。
また、ある人は「一冊を通して『生きる』とは? ってことに答えていること。間違っててもいいけれど、作者が『生きるって、こうなんじゃないか』って答えていること」って言っていました。
「cakes」の連載の時は、糸井さんに「これは、叫びだね」って言われたんです。「それはそれでいいよ」って言ってくれたんですが、今回は違うものにしたかった。
古賀「恥ずかしいことをいろいろ思い出しました」
古賀:糸井さんがおっしゃった、「叫び」の部分もしっかり残っていて、そのバランスがすごくいいなあと思いました。人間の記憶って、断片的なものじゃないですか。数秒単位の映像だけ憶えていたり、何かの曲が流れてきた時に「ああ、めちゃくちゃ寒い日に、あの校舎の前で、あの子と一緒に聴いたなあ」って思い出したり。
この小説には、そういうたくさんの写真みたいな断片的映像が散りばめられていて、そこに言葉を紡いでいく中で映画のフィルムになっていくような……。
燃え殻さんの本を読んでいるというよりも、自分の過去を見ているような、自分の記憶を掘り返している気持ちになりました。恥ずかしいこと、いろいろ思い出しました。
燃え殻:古賀さんの恥ずかしい思い出って?
古賀:僕も地方から出てきて、当時はまだまだ渋谷系のイメージが強かったから、出てきた最初の日曜日にとりあえず渋谷に行ったんです。まずはセンター街に行って、「おお、お前がセンター街か」って。そして「俺は絶対に道を譲らないぞ」って決めて、センター街のど真ん中をスタスタ歩いたんですよ。
燃え殻:ええー!
古賀:しかも、道を譲らなかった誰かと肩がぶつかったら、ぶん殴ってやろうと決めてたんです。みんなが俺に道を譲るか、ぶつかってケンカするか(笑)。
燃え殻:完全にヤバイ人じゃないですか(笑)。
古賀:そうそう。結局、最後まで歩ききったんですよ。誰ともぶつからず、ケンカにもならずに。みんなちゃんと道を譲ってくれたんです。その時に……
燃え殻:東京が認めてくれた!
古賀:そう、「東京に勝ったぞ!」って!本当にバカすぎるエピソードなんだけど、そういう恥ずかしい話を思い出しました。もう90年代とか関係ないんですが(笑)。でも、あのころ田舎者にとっては、センター街が何かの象徴だったんですよね。
燃え殻「つま先ギリギリで渋谷を歩いていた」
燃え殻:裏原宿も含めて、あの頃の東京のハリボテ感、でも全員でそのウソを成り立たせるために一生懸命頑張るっていう。「Tシャツ1枚で2万円なんてクソ高いけど、これにはワケがあるにちがいない」みたいな。
古賀:そうそう。渋谷でもどこでも、みんな田舎者の集まりなんですよ。みんな、東京の人にバレないようにって背伸びし合って、お互いに東京人を演じている。俺は東京の人間だぞ、田舎者じゃないぞって。バレていないだろうかってドキドキしながら……。
燃え殻:それ、わかるなあ。本とか映画とか音楽も全部そうですよ。彼女から「寺山修二の詩集読んだほうがいいよ」って言われて、読んでよくわからないんだけれど、いつかわかる日が来るんじゃないか、とか。こういうことをしていると、いつか東京の感性に近づくんじゃないかって。
古賀:カルチャーを教えてくれる子、かっこいいんだよね。
燃え殻:観もしない単館映画のポスターをトイレに貼ってみたり、ヴァネッサ・パラディのCDを聴く前に友達に「いいよ」って貸したりとか。そういう、いつか自分の感性が追いつくはずだ、いつかオシャレになるはずだって感じで、つま先ギリギリで背伸びしながら渋谷を歩いてましたね。ほとんどつりそうになりながら(笑)。
だから、あの頃聴いていたよくわからないノイズ系のCDとかを聞くと、当時の自分を思い出すんですよ。まだ終わっていない青春感というか痛さというか。消化されていないから、引き戻されちゃう。CMで使われていたようなキャッチーな曲だったら懐メロになるんだけど、ノイズは今聴いてもちゃんと痛い。懐メロになってくれない。
燃え殻さんの小説は「なにも終わらなかった」の喪失感
古賀:燃え殻さんの小説は「今度、CD持って行くね」って言って、それっきりになっちゃった彼女との物語だもんね。
燃え殻:「俺たちもう終わったね、楽しかったね、これからは友達でいようね、なんでも相談してよ」っていう別れ方だったら、ちゃんと終わるんですよ。CDの彼女の場合は「パート2に続く」ってなったまま、いつまでたっても作られない映画みたいな。
他人(ひと)に聞いても「そんな映画あった?」って返ってくるような、僕だけが待ちわびている「パート2」。そういうのってみんなあるんじゃないかな。
古賀:あの頃って、95年に地下鉄サリン事件があって、阪神淡路大震災もあって、99年にはノストラダムスの大予言が待っていて、2000年問題とかも騒がれて、なんとなく「世界が終わる」という雰囲気に満ちてたと思う。
僕が小学生の頃なんて、みんな「99年、自分は何歳になるんだろう」って換算してたもん。「26歳か。だったら結婚してるのかな、なんの仕事してるのかな」とか。でも、なんにも終わらなかった。
「終わるぞ、終わるぞ、今度は終わるぞ」って脅され続けたけれど、ひとつも終わらなかった。終わってくれなかった。その、微妙な肩透かし感がありましたね。燃え殻さんの小説に感じるのは、まさに「なにも終わらなかった」の喪失感なんですよ。みんながどこにも行けなかった感、というか。
※対談2回目は7月1日公開です。
(構成:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)