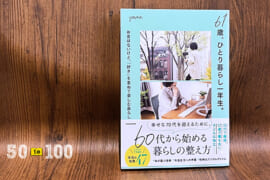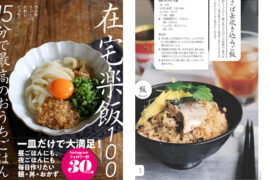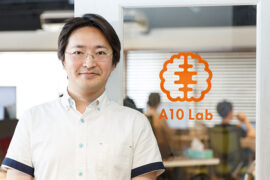「でもブスだよね?」——仕事で評価されても地位を得ても、私たち女性はその一言で突き落とされてきました。それほど強く根付いた“ブス”という価値観が、近年のCMや企業動画の炎上を経て、少しずつ変わり始めているようです。それでも、いまだ“美人“であることを求められる現代社会。私たちはどうサバイブしていくべきなのでしょうか?
著書『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)などで女性を論じてきた稲田豊史さんと、数回にわたり紐解いていく連載です。
「ブス」の基準は男が勝手に決めている
なぜこの世界で、女の“ブス”はこれほどまでに苦しむのか。それは、男が男の感覚で作った美醜の評価軸上に、有無を言わさず勝手にマッピングされてしまうからではないだろうか。
本連載の第1回に照らして言うなら、男でいうところの、年収の多寡だけで人間的価値の大半を測られるのと、同じだ。
もちろん、美醜の評価軸は同性である女性もよく設定するし、年収の多寡で人間的価値が測られるのは男だけに限らない。とはいえ現実問題として、ある女性が“ブス”かどうかの世間的な共通認識は、男の投票によって大半が決まってしまう。「1票の重み」が男女で圧倒的に異なるからだ。
要は、男が男に都合よくしつらえた土俵上で、女同士がマワシ一本で戦わされているというわけだ。見世物としての取り組みにヤンヤヤンヤと歓声を上げるのが男なら、番付を決めるのも男。
当の女力士はそこに介入できず、日々柱に突進して、相撲で勝つために特化した筋肉を鍛え上げることしかできない。相撲というスポーツが、特に好きではなくても。
上がるべきではない土俵に上がると、ろくなことにならない。柔道家がグローブを付けてボクシングのリングに上がってはいけないし、水泳選手が野球場のマウンドに立つのも得策ではない。いずれも惨敗必至だ。
また、同じ種目でも、20代の頃には勝てていた土俵で、30代になると歯が立たないことも多い(これを「タラレバ現象」という)。20代には20代の土俵が、30代には30代の土俵があるのだ。スポーツには「階級別」という言葉もある。
男子禁制 女性だけの「聖域」で生きる道
閑話休題。であれば女性が男性の設定する勝手な評価軸から逃れるには、男性が入ってこられない、関与できない土俵を見つけて、そこに上がればいい。世の中には、顔面の造作と体型の縦横比だけでは決まらない番付も、栄誉も、人生の意義もある。
たとえば、趣味空間としての「フラワーアレンジメント」や「ネイルアート」、「ホットヨガ」や「焼き菓子づくり」などは、女性に支持されている人気の土俵と言えるだろう。
そんななか、男子禁制の土俵としてひとつのジャンルを確立している立役者のひとりに、服部みれい氏がいる。
ご存知のかたには釈迦に説法だが、彼女は岐阜県美濃市に編集部を構える雑誌「マーマーマガジン」を主催する編集者にして文筆家。同誌上ほか多数の著作で、女性の心と体を「楽」にするさまざまな食やライフスタイルを提案し、多くのフォロワーを擁している。
●服部みれい氏のサイト
彼女が提案する「土俵」のキーワードは、「エシカル」「ホリスティック」「インナービューティー」「スピリチュアル」「オーガニック」「代替医療」等々。それは、多くの俗物男にとってはあまり馴染みのない、女子の、女子による、女子のための「聖域中の聖域」だ。
エシカル(ethical)とは直訳すれば「倫理」。日用品や食事などについて、コストや機能性や栄養面だけでなく、倫理的に正しい方法で存在しているかを問題にする態度のことだ。自分に優しいかどうかだけではなく、他の国の人や地球全体にとって優しいどうか。類義語は「サステイナブル」「フェアトレード」など。
ホリスティック(holistic)は「全体的、包括的」といった意味合いの健康観のこと。体に何か不具合があった場合、特定の臓器や部位だけに疾患の原因を求めるのではなく、体全体や心、生活環境も含めたつながり全体を見渡す考え方だ。自分と世界とのつながりを常に意識する生活態度や思想、という解釈も可能である。
界隈に通じたかたからの「ニュアンスが違う」といったご指摘はご容赦いただくとして、拙筆による説明ではよくわからないという場合は、「スピリチュアル」「オーガニック」というワードと並べていることから、アウトラインをご想像いただければと思う。つまり、そちら方面の世界観だ。
「キラキラ」「ゆるふわ」に乗らない選択肢
服部みれい氏界隈の世界観は、男が決めた評価軸とは一切クロスしない。
なぜなら、多くの男はこの手の世界観に通じていないだけでなく、字面だけで苦手意識を持つからだ。よしんば一部の奇特な男が興味を持ったとしても、実際に足を踏み入れることは難しい。
当たり前だ。「シルクの靴下4枚履き・冷えとり健康法」とか「白湯(さゆ)を水筒に入れて持ち歩く」程度ならまだしも、「布ナプキンの使用感」とか「月経血コントロールのコツ」みたいな議論に、生物学的にいうところの男は参加することができない。興味本位でちょっとでも触れれば大怪我必至。見た目が鮮やかだからといって溶岩に素手で触れれば、一瞬で指が消えるのと同じ。
「キラキラ」や「モテ」や「ゆるふわ」などからは程遠い地味な服をまとい、ほとんど化粧をしないこの界隈の女性たちは、男の決めた“美人”や“かわいい”の評価軸とは異なる評価軸で生きている。そのため、男からだけでなく、同性である女性――男が決めた評価軸に乗り、男の決めた“美人”を目指す人たち――からも、「不可解な存在」として見られることが少なくない。
しかし彼女たちは、気にしない。男の決めた番付には乗らない。不本意な土俵に上がることなく、結果的にとても賢い方法で「勝負」を避けている。彼女たちが住む世界には、男に投票権を与えない法体系が確立している。そこに肉体的な健康の獲得以上のものを求めて女性が集うのも、当然だ。
不本意な土俵に上がらされ続けて疲弊した者が、オルタナティブな外部規範に頼ろうとするのは自然だ。ここでいう「外部」とは、自分の頭で考えついたソリューションではない、という意味。成長の鈍化した企業が、社内だけで解決するのが難しいと判断し、外部のコンサル会社にソリューションを頼るのと同じ。
「エシカルでホリスティック」な世界観が、悩める女力士たちの駆け込み寺として機能しているのは、明白である。
いやいや、エシカルとかホリスティックなんて回りくどいことを言わなくても、要は「権威あるオルタナティブな外部規範」の究極って「宗教」でしょ? という聡明な読者の声が聞こえてくる。然り、ご明察。
次回後編では、弱った心を安定させる最強の安定ツール「宗教」に言及したい。