人生100年時代と言われる現代ですが、長生きをしても「健康」でなければ自分の満足のいく人生を送れないかもしれません。健康を維持しながら長生きができれば、より自分らしい人生プランを考えることができるのではないでしょうか。
健康に生きるためにいま注目されていることのひとつが「睡眠」です。睡眠時間の長さだけではなく、「睡眠の質」について気にしている人も増えています。スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスで睡眠の状態をチェックしたり、運動やストレッチ、サプリメントや飲料などで睡眠の質を向上させたりしている人もいます。
「健康長寿」を目指し、最先端の研究を学ぶYoutube番組「生命科学アカデミー」では、今回、ゲストに筑波大学の柳沢正史先生をお迎えしました。同プログラムのHIROCO学長が聞き手となり、「睡眠」の奥深さについて迫ります。
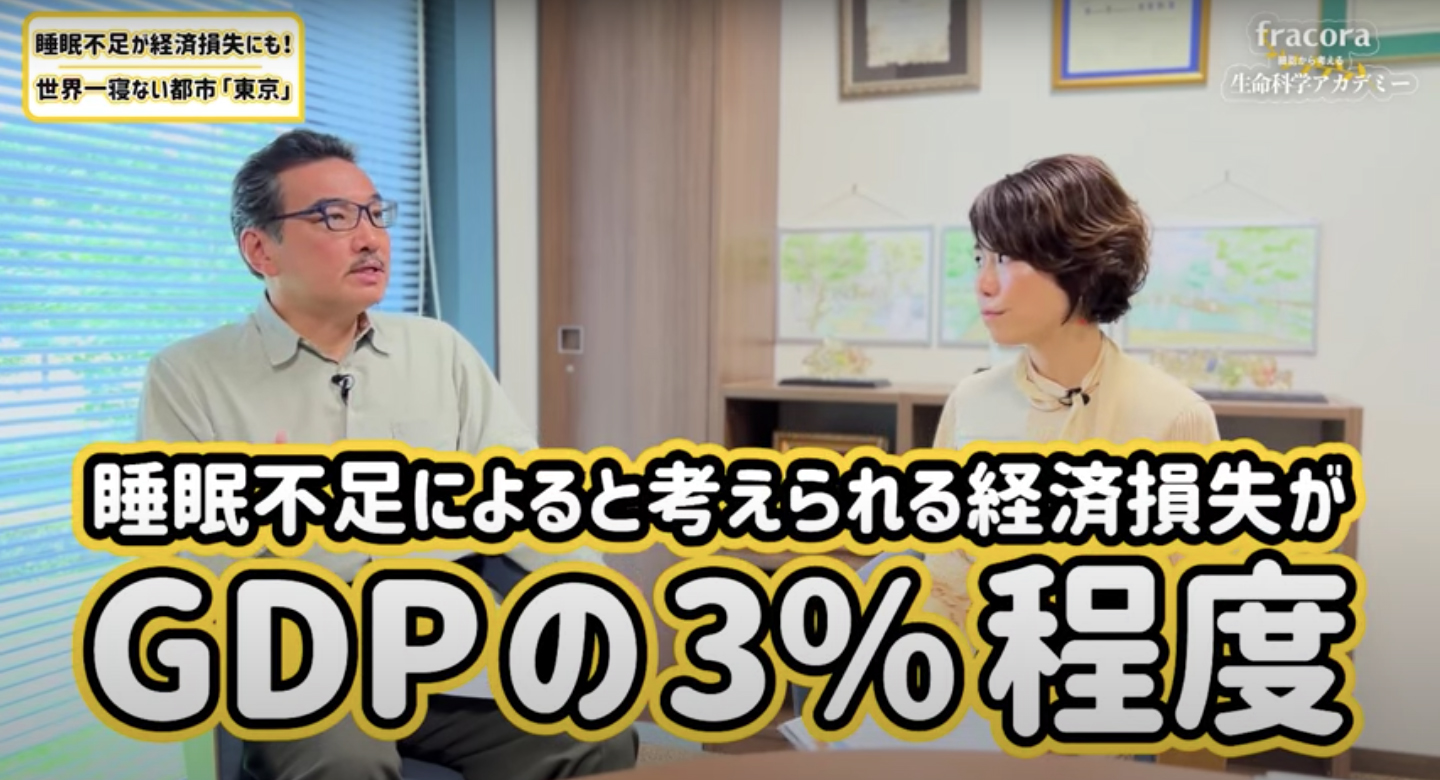
柳沢先生(左)とHIROCO学長(右)
まずは量の確保から! 睡眠の質を上げる秘策
──今回は、「睡眠の質」を上げる秘策にはどんなものがあるのか、柳沢先生にうかがっていきたいと思います。先生、早速ですがその秘策を教えてください。
柳沢正史先生(以下、柳沢):睡眠の質を上げるために一番大事なのは、「睡眠の量」です。睡眠時間を確保せずして、睡眠時間を論じても意味がない。まずは、睡眠時間を確保することが第一歩です。それを十分に確保したうえで、より良い睡眠をとるにはどうしたらいいか考えることができる。「短い睡眠で、なんとか質を上げてしのぎたいんですけど、どうしたらいいですか」と多くの方によく聞かれますが、それはもう問うことが間違っています。まずは、睡眠時間を確保してください。
──みなさん、睡眠時間を確保しましょう。
柳沢:睡眠時間は、アンタッチャブルなコアタイムとして確保してください。
──わかりました。
柳沢:そこで、睡眠の質を上げる方法なのですが、ちょっと悲しい話になります。実は、睡眠の質って減点法なんですよ。
──減点法というと?
柳沢:つまり、その人の「ベースの睡眠の質」があり、それよりもさらに良くしていきましょうというのはなかなか難しいです。万人に通用する、加点できるような方法は非常に少ないです。「寝る前にあったかいお風呂に入る」とか、それぐらいしかなくて、本当に少ないです。
減点法とはどういうことかというと、「これをすると、睡眠の質は確実に悪くなります」っていうことはたくさんあるんです。万人に共通して言えることは、その睡眠の質が悪くなる要因を一個一個潰していくことですね。
具体的にいうと、まず「寝室の環境」です。これがすごく大事で、私がいつも言うのは3つです。暗くて、静かで、適温。
──暗くて、静かで、適温。
柳沢:これ、当たり前だと思うじゃないですか。でも、この3つが守れていない人が結構多い。
たとえば、電気をつけっぱなしで寝ちゃったり、朝のものすごく早い時間から日の光がバーッと入ってくるところで、カーテンを閉めないで寝てしまったり。日本の夏は、明るくなる時間が早すぎるので、早朝覚醒になってしまいます。電気をつけっぱなしにするのも最悪です。
それから、テレビやラジオをつけっぱなしで寝るのも良くない。人間はコミュニケーションする動物なので、人の声に敏感にできているんですよ。人の声には覚醒作用があるといえます。だから、たとえ自覚的には起きていなくても、人の声が聞こえるところでは、睡眠時間は確実に浅くなります。これは良くないですね。
それから「適温」。寝室の温度は、その人にとって眠るのに心地良い温度があるじゃないですか。それを自分で決めて、その温度を朝まで保つ。それが大事です。これが、守れていない人が多いです。
日本では、なぜか「エアコンをつけっぱなしで寝ていると体に悪い」っていう、まったく何の根拠もない都市伝説がありますよね。だって、欧米の住宅って24時間空調が当たり前です。もちろん、ビュウビュウとエアコンの風が直接体に当たるのは、皮膚の温度が下がるので良くないです。ちゃんと、風を当てないようにして、自分が快適な温度を朝までちゃんと保つ。冬と夏ではもちろん掛けている寝具も違うし、自分でそこは決めてくださいということですね。
私の場合はすごく幅が狭くて、冬でも20度から21度くらいと、冬の寝室としてはかなりあったかいです。夏でも、25度だともう僕は暑苦しいので、23~4度までです。それ以上になるともうダメ。それくらい冬と夏であまり違わないようにしています。
──それはもう、自分で決めていいということですね。
柳沢:同じ寝室にいるベッドパートナーの方との折衝とかいろいろ難しい問題はありますが、そこは寝具とかで調整して、部屋の温度を朝まで保つ。「電気代がもったいない」とか「エコじゃない」という人もいますが、僕に言わせると、それで睡眠の質が悪くなるほうがよっぽどもったいないです。
──そうなんですね。
ディナータイム以降のカフェインは避ける
柳沢:減点法の話に戻すと、これもよく言われることですが、ディナータイム以降のカフェインを避けてください。
──それは、コーヒーとか……?
柳沢:緑茶やコーヒーなどのカフェイン飲料ですね。だいたいカフェインは、飲むと4~5時間くらいは効くと言われています。夜の12時に寝る人だったら、まあ夜7時以降はやめたほうがいい。だから、ディナーのあとのカフェインは、カプチーノとかも飲まないほうがいいです。
──レストランでは、ディナーの最後に「コーヒーにしますか」と聞かれますが、そこはハーブティーとかのほうがいい。
柳沢:そうですね。紅茶はあまりカフェインが入ってないので。コーヒーならば、デカフェ。でも、デカフェを飲むくらいだったら、飲まないほうがいいと僕は思います。
それから、アルコールも睡眠の質を下げます。ディナータイムの晩酌をやめてくださいとは言えないですけれども、寝る直前のアルコールは本当によくないです。
日本人は、世界のなかでも「寝酒(ナイトキャップ)」を飲む人が極端に多いんです。寝酒というのは、眠るためにちょっと一杯あおってから寝るというものです。アルコールそのものには催眠作用があるので、お酒を飲めばちょっとは眠くなります。だけどその後、エタノール・アルコールは必ずアセトアルデヒドというものに代謝されます。アセトアルデヒド自体は覚醒作用のほうが強いので、交感神経を刺激します。
だから、深酒をしてガーッと眠ると、2~3時間して起きてしまうじゃないですか。今度は眠れなくなるんですよ。私も深酒しちゃうことがあるのでよく体験しますが(笑)。とにかく、睡眠の質を下げたくないのであれば、アルコールはディナータイム以降はやめてください。
──はい、わかりました。
柳沢:そういう減点法によって、睡眠の質は下がります。逆に、睡眠の質を上げる方法というと、万人に共通する方法はなくて、その人に合ったやり方を見つけるしかありません。寝具も、自分が快適な寝具であれば何でもいいんです。何でもいいって言い方は良くないですね。「快適な寝具を追求すればいい」ということです。
──自分が心地良い寝具とか枕とかですよね。
柳沢:枕は、その人の首の骨格の形によって最適な形状が変わってくるので、その辺りに気をつけて選ぶ。掛け布団も、重いのが好きな人も、軽いのが好きな人もいます。マットレスも、あれは「寝姿勢」と言われる体圧分布に関わってきます。柔らか過ぎると寝姿勢が悪くなってしまいますが、そのあたりも自分の好みで。
──なるほど、好みに合わせていいんですね。
柳沢:それから、いわゆる寝るための「ルーティン」です。これをやれば自分は良く眠れるっていう、おまじないのシークエンスを発見するといいですね。
──ちなみに、先生はどんなルーティンがあるんですか。
柳沢:こんなことを言うと怒られるのですが、私のルーティンは「読みたくない、つまらない論文を読むこと」です。それをベッドの中でやっていると、あっという間に眠くなる。なので、これはもう僕には最適なんです(笑)。
人によってはアロマとか、ちょっとしたハーブティーかなにかを1杯飲むとか、それぞれ違った方法があると思います。自分にとっていい、こうやると心が落ち着く、リラックスできるみたいなやり方を発見するといいですね。ただ、残念ながら科学的な意味で万人に「これをやればあなたはよく眠れます」と言える方法はありません。申し訳ないけど。
◆まとめ
・睡眠においては、まず、質よりも量!
・睡眠の質は減点法
睡眠の質を悪くする要因を除いてゆくしかない
・寝室の環境が重要!「暗くて静かで適温」をキープ
・ディナータイム以降のカフェインとアルコールは避ける
(第9回へ続く)
■動画で見る方はこちら


































