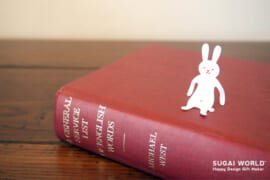「絶縁」をテーマに、アジアの気鋭の作家9名が短編を書き下ろしたアンソロジー『絶縁』(小学館)。日本から参加した村田沙耶香(むらた・さやか)さんが寄せた作品は、若者世代に「無」が流行し始め、世界各地に「無街」が作られるという物語だ。世界的ベストセラー『コンビニ人間』をはじめ、多くの人が何となく常識だと信じている価値観を鮮やかに覆す作品を発表し続ける村田さんにお話を聞いた。全3回。

村田沙耶香さん
「母性」という言葉の怖さ
——『絶縁』で書かれた「無」の中で印象的だったのが、感情は東京タワーから発信され、自分に流れ込んでくるものだと信じている美代が、自分の娘を「生きた家電」だと思っているというフレーズ。世間では「女性には母性が備わっている」「子供を産めば自然と母性が湧いてくる」と思われているフシがありますが、「母性」に対して疑問を持っていらっしゃるのかと想像しました。
村田沙耶香さん(以下、村田):子供の頃は、なぜ母と父が自分にご飯をくれるのか、本当にわからなかったんです。6つ年上の兄は普通におねだりしたりしていたのですが、「うちは貧乏なんだから」と母に怒られていたので、私は「うちはものすごい貧乏だから、お菓子のおねだりとかしちゃいけない」と思っていました。家もぼろぼろだったし、生活も質素だったので……。なぜ、この“両親”という人たちは、自分の子供だというだけで、貧乏なのに毎日ご飯を与えてくれて、寝る場所を与えてくれるのだろう?と、すごく不安だったんです。 誕生日におもちゃをもらうと、良心の呵責(かしゃく)を感じるというか、本当に胸が痛かった。でも、お人形やぬいぐるみをかわいがったり、小さい動物や赤ちゃんを見て「かわいいね」と喜んだほうが、「やっぱり女の子ね」と大人が喜ぶということも、一方で知っていました。
——とても冷静に大人や周りを見ていたんですね。
村田:すごく周りの顔色をうかがっている子供だったので、大人のそういう態度に過剰に敏感だったんだと思います。「大人が喜んでくれるように振る舞わないと、捨てられたらご飯が食べられなくなって死ぬのだろうな」とも思っていました。大人になって、心理学の本を読んで、「見捨てられ不安」という概念を知ってだいぶ楽になりました。そういう気持ちは大学生になってもすごくありました。
「母性」というのは、すごく恐ろしい言葉のような気がします。「母性があるから」という理由で、子産みをさせ、家事をさせ、病人や老人をケアする役割を回し、その言葉を使って徹底的に人間を使えてしまう怖さがあります。
——どこか“本能”と思わされているというか、だからこそあらがえない怖さのようなものは感じます。
村田:「母性があるでしょ?」と言われると、美しい物語を課せられて、現実的にはしんどいことをいろいろ背負わされるような気がして、怖い言葉だと思います。自分自身もその言葉を使って誰かを美化し、コントロールしている瞬間があったかもしれません。でも、自分には母性があると感じていて、それを誇りに思っている方も大勢いらっしゃるのかなと思います。ただ、自分の周りには「母性」ではなく「愛情」という言葉を選択する人が多いです。
“特権”の中にいる自分に気づいたときに感じたこと
——「無」には「優位な立ち位置にいる自分への罪悪感としんどさ」を感じている小学生の女の子が登場します。実体験をもとにしたエピソードなのでしょうか?
村田:なにか失敗をしても、「女の子でまだ小さいから沙耶香はいいよ」と許されたりしていて、自分が幼くて、女の子だということで本来受けるべき罰を回避しているのではないか、といつも懺悔(ざんげ)していました。実際には、逆に課せられているものもあったのだと思いますが、それを自覚する知識はありませんでした。
ある時、ラジオで「特権」という言葉に関する話を聞いて、自分も「女性」だということ以外はマジョリティの側に属していて、そのことで多くの特権を有しているということに気づきました。これに気づくことは、すごく難しいと感じました。
コンビニでアルバイトをしているとき、突然年配の男性のお客さんに「お前は外国人だろう。俺は顔を見ればわかる」と、ここでは言えないほどの差別的な罵倒をしたあと、「村田」という名札を見たとたん「日本人なんだね。頑張ってね」と態度を変えたことがあって、すごく自分を恥じたんです。気づかなかっただけで自分は特権の中にいて、同じように働いている留学生の子たちが嫌な目にあったりしてるんだろうなと、20代も過ぎてから気づいた。でも具体的に自分に何かできるわけでもない。そのことが、ますます恥ずかしかった。そんな感覚を今もずっと抱いているので、「無」でも特権の中にいる子を書きたかったんだと思います。
(聞き手:新田理恵、写真:藤岡雅樹)