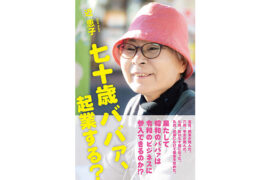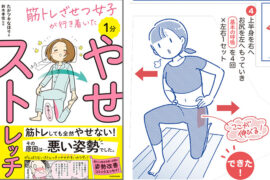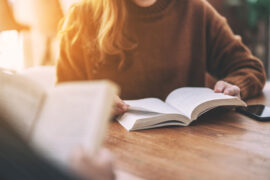子どもをもつ/もたないは個人の選択に過ぎない。そう理解していても、やっぱり子どもを産まないことに「なんとなく」抵抗があるのはなぜ? 産まないと一人前じゃないという意識はどこからくるの?
前回に引き続き、『わたしが子どもをもたない理由』(かんき出版)の著者で、作家の下重暁子(しもじゅう・あきこ)さんに話を聞きました。
第2回のテーマは「子どもがいないと」という枕詞についてです。
【第1回】81歳の今だから語れること「子どものいない人生に一度も後悔はありません」
子どもがいなくて淋しいは余計なお世話
——自分で決めることが大事だと前回教えていただきましたが、産むって自分の選択でもあるけど、パートナーの希望もあるし、親に孫の顔を見せてあげたいという思いもあって、自分だけの選択ではないような気がして。なんとなくプレッシャーに感じてしまいます。
下重暁子さん(以下、下重):パートナーと話し合うことはもちろん大事ですよ。親に孫の顔を見せたいという自分の思いがあるのなら、産めばいいじゃない。私は、母に孫の顔を見せてあげたいと思ったことは一度もなかったし、私のつれあいは私以上に子どもがいる家庭を望んでいませんでした。「彼は子どもを望んでいるんじゃない?」と心配してくれた人もいるけど、余計なお世話ですよね(笑)。
——淋しいと感じることはありませんでしたか?
下重:それもよく聞かれるけど、自分や世間のものさしで私を推し量るからよね。子どもがいなくて淋しいかどうかなんて、最初からいないんだもの、わかるはずないじゃないですか。猫を飼っていたので、愛情を注いでいた対象がいなくなってしまう喪失感なら私も知っていますよ。でも、最初から産まないという選択をしているんですから、淋しさなんてありません。
他人の人生を生きるなんてまっぴら
——パートナーとして産まないということを尊重し合える関係って素敵ですね。
下重:そういう相手を選びましたからね。一緒に暮らす人を、他人に選んでもらうなんてつまらないことだと思わない?
——私はなかなか男性を見る目がないので、「この人が最高のパートナーです!」って誰かが言ってくれたらいいなぁって思うことがあります(小さな声で)。
下重:人に決めてほしいというのは、自分の人生に責任を持ちたくないのよね。人に合わせる生き方をしていると、何か都合の悪いことがあった時に、人のせいにできるから。そんなこと私にはできない。全て自分のせいじゃないですか。あの人がこう言ったから、世間がそうだから。親が……って。そんなの他人の人生ですよ。私はそういう人生が一番嫌い。
——潔い……。
下重:でも、「誰かに決めてもらう人生でいい」と自分の意思で決めるのなら、それでもいいんじゃないかしら。私と同じ考えを持てなんて言いませんよ。それこそ自分のものさしを押し付けるだけになる。みんなそれぞれ違いがあって、それが個性。だから好きなように生きればいいの。
産むのは無条件に良いことか
——子どもがいる人の方が信頼できる……という趣旨のことを言う人もいますよね。子どもがいるというだけで、もらえる手当が増えるなど、社会に優遇されている気もします。
下重:今は国が子どもを産むことを奨励していますよね。なぜかというと、家族でまとまっている状態が、一番管理しやすいから。戦前もそうだったんですよ。国が戦争をするというと、家族はみんな応援するという形が、手っ取り早かったから。
敗戦後、私はそれが崩れていく過程を見てきました。だからこれは間違いだということはよくわかっています。子どもを産むのが無条件に良いと思っている人たち、家族の絆を大げさに押し付けてくる人たちの言葉を耳にしたら、その意図をよく考えてほしいと思いますね。
——歴史を見てきた下重さんがおっしゃると……。
下重:重いでしょう。もう少し、重たい話に付き合ってくださいね。戦後私たちが勝ち取った権利というのは、“個人”なんです。個の権利。それは憲法13条にもあります。個人の尊厳が何よりも大事だと。家族が一番大事なんて書いてありませんよ。昔の修身教育ではあったかもしれませんけど。今まさに、その頃と同じことを言いだしているんです。
——不穏な流れですね。
下重:家という考え方が根付いたのは江戸時代にさかのぼります。治安が安定して豊かになっていく中で、国を安泰に保つためには、領民たちの“忠義心”が必要だったの。その忠義心の元となるのが、親への“孝行”というわけ。「家族が大事」というのは、江戸時代、明治時代からずっと刷り込まれてきたものなんです。
その考え方から抜け出して、個を大事にしようというのが近代化。夏目漱石をはじめとして、文学者たちはみんな家と戦って、それを書いたんです。みんな個として生きていこうと。そして、やっと憲法でも保障されて個になった。それをまた逆行させようというのが今の風潮です。
風潮って、何のこと?
——風潮ですか……。子どもがいないと一人前じゃないという風潮は強いかなと思います。
下重:風潮というのは、勝手にそう思っている人がいるというだけの話よ。よく考えてみて。風潮ってなんですか? たくさんの人が言っているとか、世間が言っているっていうことでしょ。そんなものは自分が考えていることではありませんよね。
自分で本当に子どもが欲しいなら、産めばいい。それは誰にも反対できない。その人の選択、考え方ですもの。だけど、子どもがいなくてもちゃんと自分で自己表現をして、自分の生き方を持っている人は、なぜそんな風潮に合せる必要があるの?
——合わせておけば、レールの上を歩ける……というか、安心感があるから?
下重:結局、自分で責任を持ちたくないのよ。自分で責任を持たない人生なんてね、ラクしたいわけですよ。自分で全ての責任を持つのはしんどいもの。人に何か言われるのは、自分がそれを選んだからでしょう。たとえ嫌なことを言われたって、「私が選んだんだからしょうがないでしょう」というだけの話。だけど、いちいち相手するのは面倒よね。
——下重さんもしんどいことをたくさん言われたのでは?
下重:それが意外とないの(笑)。言っても変わらないとみんな知っているからかしら。でも、全く私のことを知らない人には言われましたね。まあ、「あ、そう。私はこれが好きなので」と答えるだけだけど。
子どもは親の都合で生まれる
——強いなぁ……。
下重:私ね、子どもは、親の都合で生まれてくるものだと思っています。生まれてくる子どもの意思はそこに反映されていませんよね。
自分の血を分けた存在がほしい、愛する対象がほしい、跡取りがほしい、将来自分の世話をしてほしい、自分が生きた証を残したい……。ね、親の都合でしょ。
——そうですね。理由を挙げてみると、親が子どもに期待することばかりですね。
下重:その期待を子どもが受け入れてくれるかは別問題ですけど。私の母は父と結婚する前から女の子をひとり産むと決めていました。そして見事に女の子を産んだ。それが私です。彼女は途端に「暁子命」になってしまってね。私にしたら迷惑な話よね。
とてもしんどかった。彼女は優秀な人だったから、「どうして自分の能力を活かして生きないの」と思っていました。私は中学生の時に、母に、「あなたの生き方は間違っている」と説教したこともあるのよ。
期待は自分にするもの
——わかる気がします。親が自分のために我慢するなんて、ちっとも嬉しくないですよね。「あなたのために」って言われると、「あなたのせいで」と聞こえる気がします。
下重:期待は、自分が自分にするものですよ。私は自分にものすごく期待をしている。これから、どんな人になるだろう、どんな仕事をするだろうって。自分に興味があるってとっても面白いのよ。自分にしか興味がないって言ってもいいぐらい。
——周りに期待されることで、自分の存在価値を確かめている人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。でもそのせいで無理をしてしまったり、苦しくなったりすることも……。
下重:そうでしょう。でも、必要とされることと期待は違いますよ。私は自分がどんなふうに変わっていくのか、自分を作り上げることに興味がある。その結果として誰かが私を必要としてくださるというのはとても嬉しいこと。
誰かが必要としてくださるから本も書ける。テレビにも出られる。自分の意見を言うこともできる。だけれども、本を書きたくて「求められる私」を演じたりなんかしないの。