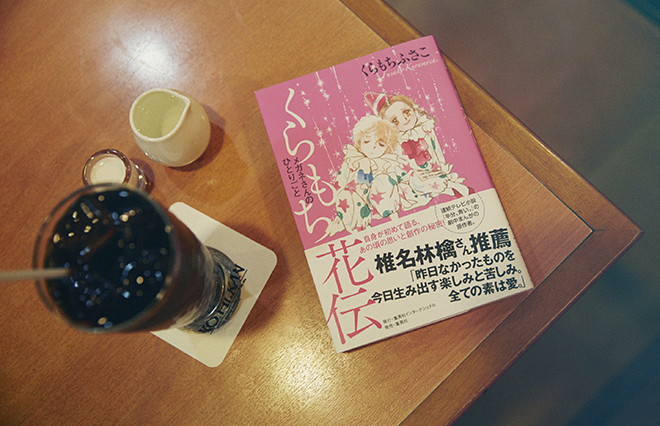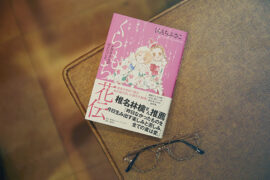一番興味のあることをするのが一番効率がいい
理想の社会がここにはある。
「したいことを選ぶ」ができるのは子どものころから培われていることがあるからではないかと思った。なぜなら、フィンランドの教育は世界一といわれる。また、5年前の訪問で、幸せの秘訣は「個を尊重する教育」にあるのではと実際に感じたからだ。
次に向かったのは、最近できたばかりの Oodi(オーディ/ヘルシンキ中央図書館)というハイテク図書館だ。ここでは、フィンランド人の夫と子どもを持ち長年住み続けている日本人女性に会うことになっていた。フィンランドの現役の先生にも声をかけてくれていたので、これは教育のことを聞くチャンスだ。
さっそく、「教育って、何を重視しているのでしょう?」と聞いてみる。
「大事なのは、いかに自分の将来につながるか。例えば、企業が大学に期待するのは成績ではなく、すぐに使えるスキルを身に付けているか。だから、会社に入って即戦力になるのが普通なのですが、それができないと、大学に文句がいきます」
「えー ! 大学に文句が……」
「国にとって重要なのは、国民にしっかり仕事をしてもらい税金を納めてもらうことですよね。そのために教育がある、という位置づけ。だから、教育への投資は手厚い。授業料は、基本は国が負担しますし、社会人の教育も盛んです。大人が学ぶ場所がたくさんあり、キャリアチェンジがしやすい。普通、1つの会社で 1つの仕事をずっとしていたら飽きますよね。人が成長するにつれて、その時点で一番興味のあることに取り組めるようになっているのですが、それは誰にとっても効率がいいですよね」
当然そのほうがやる気が出る。というのは、日本人もみんなわかっていることだ。
しかし、なかなかできないのはなぜだろう。
「どうしてフィンランドはそれができるんですか?」
「第二次世界大戦後、フィンランドはソ連に賠償金を支払わなくてはいけなかったんだけど、そのときはお金ではなくモノで返していたの。フィンランドは人口が少ないし、寒くて資源もない国。みんなが効率よく生産性を上げて働かないと、賠償もできないどころか、生きていけない。一人の力さえも無駄にできない状況だからこそ、『人』への投資としての教育が重視されていった。フィンランドではよく語られるジェンダー平等が形作られたのもそう。女性も男性と同じように働かないと国が回らないため、男性と同等の権利が与えられたの」
なるほど……。今のフィンランドがある裏にはそうしなくては生きていけなかった歴史があったのだ。よくよく考えてみれば、どの国も、過去の歴史や環境が今の国の形を作っているのかもしれない。