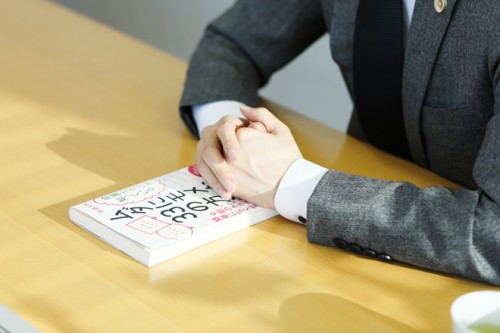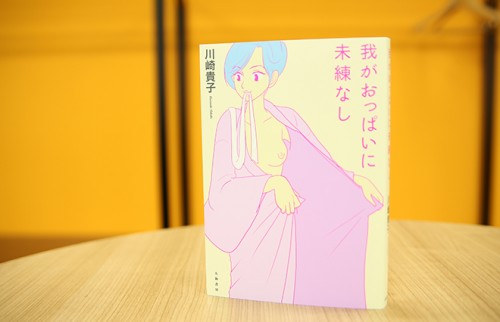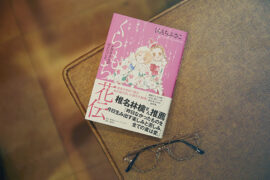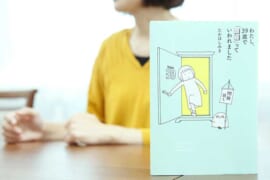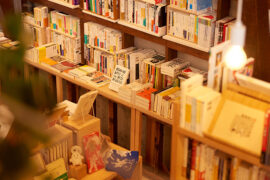「上司にミスを指摘したら、なんだか冷たくなった」
「正しいことをしているはずなのに、周りが理解してくれなくて孤立気味」
自分の主張が通らなかったり、自分の立ち位置が見つからなかったりして、ふとした瞬間に人間関係がギスギスしちゃうことってありますよね。
「モメごとが小さなうちは、コミュニケーションの方法を少し変えるだけで、案外早く解決することができる」と、レイ法律事務所代表で弁護士の佐藤大和(さとう・やまと)さんは言います。
2018年2月に著書『弁護士だけが知っている ムダにモメない33の方法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を上梓した佐藤さんに、全3回にわたって人間関係をなめらかにするためのコツについて話を聞きました。
第1回目のテーマは「人間関係のベストポジションの探り方」です。
ハラスメント問題はコミュニケーション不足から生じる
——佐藤先生がウートピ世代の女性から相談を受ける場合、どのような内容が多いですか?
佐藤大和さん(以下、佐藤):20代後半〜30代の女性だと、ハラスメント問題や男女トラブル、ママ友トラブルなどが多いですね。それから、企業内のコミュニケーション不足によって生じるトラブルに関する相談も増えています。
——ハラスメント……。最近はハラスメントの種類がどんどん増えている印象がありますね。
佐藤:ハラスメントの種類は今、30〜40種類あると言われています。においハラスメントや、マタニティハラスメント、シルバー世代に対する「シルハラ」と呼ばれるハラスメントもあります。
——なんでもハラスメントに変わってしまいますね。
佐藤:そうですね。そもそも、ハラスメント問題の根幹にあるのは、法律トラブルでも感情トラブルでもなく、コミュニケーショントラブルです。人とどうやって関わっていけばいいか、人にどうやって自分の思いを伝えればいいか。そういうことがわからずに、悩んで人間関係をこじらせてしまうんです。
人間関係のベスポジを探るコツは「五方美人」になること
——確かに、どのように返答をするべきか悩む場面は多いですよね。例えば、上司や先輩から「昨日は終電まで働いちゃったよ」とか「この映画おすすめ。特に感動するのは(以下長文)」とか、LINEで“オレ通信”が届いて困るという声をよく聞きます。
佐藤:フレンドリーさの履き違えですね。私もよく相談を受けます。
——正直、「何が言いたいんだろう…」「仕事に関係ない話はやめてほしい」と内心思うけれど、そのまま伝えてしまうと角が立ちますし、かといって毎回返事をするのもしんどいですし……。やんわり指摘するといっても、立場上、伝えにくいときもありますよね。
佐藤:女性のみなさんは、「角が立たないように丸くしなければいけない」と考えるタイプの人が多いなと感じます。それは大事なことですが、「少しくらいの不快さは我慢しなきゃいけない」と思うのはよくありません。今回の本にも書きましたが、人間関係のベストポジションを探るには、八方美人にならずに、「五方美人」くらいでいいんです。
——「五方美人」?
佐藤:例えば周りに8人いたとしても、全員に気遣うのではなく、まずは5人との関わりを深める。要するに、人間関係の優先順位をつけるということです。私の仕事で言えば、8人いれば、8人の頼みごとを引き受けるべきなのかもしれません。でも、「これは無理だな……」と思う時は正直に「できません」とお伝えしています。
我慢して引き受けてもどこかで不和が生じて、信用や信頼をなくしてしまうことがあるからです。「五方美人」の判断基準は、「この人なら信用できる」という自分軸で構いません。だから、ダメなものはダメと言って大丈夫。
「自分が正しい」は「独りよがり」と紙一重
——「自分がなんとかしなきゃ」「自分が我慢しなきゃ」と抱え込まなくていいんですね。
佐藤:もちろんです。私は、企業が主催するハラスメントの講演会でよくスピーカーを務めますが、その時はハラスメントが引き起こすトラブルの顛末だけでなく、「人に不快な思いをさせないためにどうすればいいか」という、コミュニケーション技術も一緒にお伝えしています。
ハラスメントの恐怖とコミュニケーションの重要性は車の両輪のようなもの。双方を理解していないと、本当の意味で納得するのは難しいんです。例えば、先ほどのような“オレ通信”によってみなさんが不快な思いをするのは、送り手側のコミュニケーション技術に問題があるからです。
——コミュニケーション技術の問題とは?
佐藤:自分と他人とでは、そもそもの価値観が違う。これは、コミュニケーションの大前提です。人は生まれ育った地域も、親の教育も、所属していたコミュニティもそれぞれ異なりますよね。育ってきた環境が異なれば、価値観もコミュニケーションの距離感も違って当然。それなのに、自分の価値観が絶対だと思うから「終電まで働くオレってすごいだろ?」「オレが感動した映画は君も観るべき」とメッセージを送ってくるおじさんが現れるんです。
コミュニケーションに問題があるのは、おじさんだけではありません。こう言うと怒られるかもしれませんが、アラサー世代の女性は、「正義」に絶対の軸を置いている方が多い傾向があります。「自分は間違ったことをしていない。だから正しい」と主張してしまうんです。だけど、いきすぎた正義は人を傷つけるし、企業内コミュニケーションにもズレを生じさせます。
——心当たりがあります(苦笑)
佐藤:その人が間違っていないのは、もちろん周りも知っています。でも、「自分の正義」を無理やり押し通そうとすることで、残念ながら「独りよがり」のレッテルを貼られ、正しいことをしているはずの人が孤立してしまうんです。主張をするのは、何かを変えたいからですよね。決してモメごとを引き起こしたいからではないはずです。自分の正義を貫きたいなら、周りに対する配慮も必要です。
火が小さいうちに「消火スイッチ」を押そう
——どのような配慮をするといいでしょうか?
佐藤:今回の本では「消火スイッチ」という言葉で表していますが、相手の怒りの本質をつかんで、すぐに謝ったり冷静に話し合いをしたりすれば、早い段階で解決することも多いんですよ。
これは、ニュースでよく見る、騒音やにおいなどの近隣トラブルも同じです。例えば「上の階の人がうるさい」と思っていたとします。最初のうちは、みなさん我慢できるんです。でも、少しずつストレスが溜まり、あるとき爆発して、近隣トラブルとして表面化する。ストレスがインフラを起こしてしまうと、「トン」と音がするだけで「うるさい!」となってしまいます。
——そんな状況になると、話し合いもできませんね。
佐藤:そう。ストレスがマックスになってから解決しようとすると、ちょっとした意見のすれ違いでも「あの人嫌い」「顔を見るのも嫌」となってしまう。怒りを鎮めて、関係のポジションを調整するには、相手が何を求めているか、聞き役に徹することも大切です。
「自分にも言い分がある」と思ってしまうかもしれませんが、正しさを主張しあっても人間関係は複雑になる一方です。勇気を出して「どうしたいの?」「どんな状況になるとベストなの?」と落とし所を探ってみると、大きなモメごとになる前に「消火」できますよ。
(取材・文:東谷好依、写真:面川雄大)
*次回は3月27日(火)公開予定です。