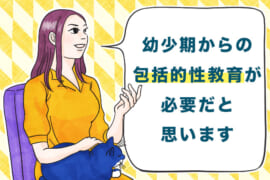読者から届く体調不良の声の中でも、「逆流性食道炎」のお悩みが目立ちます。そこで改善の方法について、消化器病指導医・専門医で、著書に『胃は歳をとらない』(集英社)がある三輪洋人(みわ・ひろと)医師に連載でお話しを聞いています。
今回・第19回は、東洋医学によるアプローチ法についてお尋ねします。これまでに詳しく紹介してきた症状や診断法、検査法、治療法、セルフケア法などについては、文末のリンク先を参照してください。
エビデンスがある漢方薬「六君子湯」
——逆流性食道炎の治療に、東洋医学的なアプローチの方法もあると聞きました。具体的にどういうケアをすればいいのでしょうか。
三輪医師:まずは、漢方薬の服用が挙げられます。西洋医学、東洋医学といったくくりに関わらず、「六君子湯(りっくんしとう)」という漢方薬は、さまざまな研究報告によって、逆流性食道炎の治療に有用である可能性が示されています。日本消化器病学会の診療ガイドラインにも同薬の処方について紹介していますが、特に女性や、やせ型の人、高齢者で効果があるとされています。
このため治療にあたっては、患者さんの症状や体質、希望によって、ほかの薬と考え合わせながら処方する場合があります。
西洋薬の場合は、あるひとつの症状に対して局所的に早く治癒するように作られていますが、漢方薬は個人の体質や体力、不調の全体を見て、ゆがみやひずみを改善し、本来の健康な状態に戻すことを目的としています。
漢方薬では、例えば、けん怠感が強い、めまい、頭痛、肩こりがある、イライラするなど複数の症状がある「不定愁訴(ふていしゅうそ)」や、「胃が痛いのに、内視鏡検査をしても異変がないと言われた」という場合にも対応しています。
また、「体力がある・ない・中間ぐらい」という違いや、体質として、「冷え性だ・汗をかきやすい・血圧が高めだ」などを考慮し、同じ症状であっても違う薬を選ぶケースもよくあります。
——六君子湯とはどういう効能があるのですか。市販もされていますね。
三輪医師:六君子湯は、胃もたれ、食欲不振、消化不良、胃痛、胸やけ、悪心、おう吐など、胃の不定愁訴とも言える複数の症状に対して、これひとつだけで対処します。
また、検査をしても胃に病変がない「非びらん性胃食道逆流症」や、「機能性ディスペプシア」という胃の病気、また、胃の手術後に伴う症状にも有用ということがわかっています。
ほとんどの漢方薬には複数の生薬が配合されていますが、六君子湯の名は、「人参(にんじん)」「半夏(はんげ)」「茯苓(ぶくりょう)」「朮(じゅつ)」「陳皮(ちんぴ)」「甘草(かんぞう)」の6種類の配合生薬を6人の君子に見立てたといわれます。実際には、これらに「大棗(たいそう」、「生姜(ようきょう)」を加えた8種類で生成されています。
六君子湯が向くのは、体力が中等度以下で、顔色がよくない、疲れやすい、手足が冷えやすい、全身のけん怠感があるといった人です。逆流性食道炎の症状は、こうした体力、体質の人に多いため、多くの人に適用します。
ただし、六君子湯は酸の分泌を抑制する効果はないので、逆流性食道炎に対する効果は「プロトンポンプ阻害薬」(第17回参考)などの酸分泌抑制薬には及びません。このため逆流性食道炎の症状がプロトンポンプ阻害薬だけで十分に収まらない時に併用して使うことが一般的です。
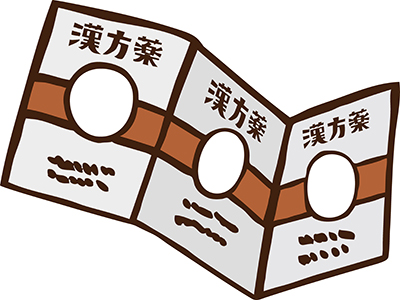
——六君子湯のほかにも、逆流性食道炎や胸やけ、胃もたれに効く漢方薬はありますか。
三輪医師:エビデンス(医学的根拠)の確立はこれからですが、胃の不快感に加えて、のどがつかえる感じや違和感、憂うつ感がある場合は「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」、胃酸の逆流感や胸の灼熱感、げっぷがひどい場合は「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」を処方する場合もあります、どちらも、いくつかのメーカーから市販もされています。
ヨガの「ネコのポーズ」「コブラのポーズ」
——漢方薬のほかに、東洋医学的なアプローチの方法はありますか。
三輪医師:逆流性食道炎の原因のひとつに、「猫背」や「前かがみの姿勢」があります。デスクワークの人や運動不足の人、高齢者に多いと言えます。そこで、自分でケアする方法として、姿勢の改善を指導しています。
その方法は、以前(第11回参照)にも紹介した、ヨガの「ネコのポーズ」や「コブラのポーズ」、また、深呼吸も有用と考えられています。
——六君子湯は市販されていること、またヨガのポーズや深呼吸はすぐに実践できそうです。
三輪医師:胃に複数の軽い不調がある場合は試してみるとよいでしょう。ただし、胃の不調は体調不良のサインです。胃や食道など消化器官に病変がある、また、ほかの病気が隠れているケースも多いので、まずは早めに消化器内科か内科を受診してください。そのうえで、こうしたセルフケアを行うのが得策です。
聞き手によるまとめ
逆流性食道炎には、漢方薬の六君子湯が医学的エビデンスに基づいて改善に有用だとわかっていること、ほかに、半夏厚朴湯や半夏瀉心湯も処方されているということです。また、ヨガの猫のポーズ、コブラのポーズ、深呼吸を日常に取り入れて、セルフケアや予防に役立てたいものです。次回・第20回は東洋医学的アプローチとして、エビデンスに基づいたツボケアを紹介します。
(構成・取材・文 品川 緑/ユンブル)