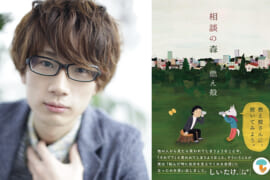トイレに行ってもどうもスッキリしなかったり、おしりの痛みでスムーズに出なかったりすることはありませんか。おしりのつらさはなかなか人に打ち明けられません。
そこで、大腸肛門病専門医で指導医でもある、大阪肛門科診療所(大阪市中央区)の佐々木みのり副院長に尋ねると、「そうしたおしりのトラブルには、本人も気づいていない頑固な便秘が潜んでいることがあります。毎日排便していても、出残りの便があると便秘なんです」との回答があり、詳しく聞いてみました。
気づかないうちに、排便したのに残っている「出残り便秘®」
——「毎日出していても、自分でも気づかない便秘」とは、どういう状態なのでしょうか。
佐々木医師:多くの人は「快便」の条件を「毎日排便があること」と認識されているようですが、実は、たとえ毎日排便があっても、便を出し切ったわけではなく、まだ出口あたりに残っていることがあります。この現象は、実は本人が「スッキリした」と感じていることとは関係がありません。
——おなかがはって出にくいときや、時間がないときは切り上げざるをえないことがあります。出口に便が残っていても、次のトイレのときに出せば問題ないように思っていたのですが……。
佐々木医師:いえ、それが問題なのです。出口に残ったままの便は、時間が経つにつれて水分が直腸で吸収され、硬くなっていきます。すると、ますます出にくくなるわけです。その排出されずに残った便は時間とともに古くなって、出口をふさぎます。これを当院では「出残り便秘®」と呼び、注意を促しています。
——出残り便はどうなるのでしょうか?
佐々木医師:まず、正常な便のサイクルを説明しましょう。食べ物は胃で消化された後、小腸に運ばれ、栄養素が消化・吸収されてからドロドロの状態で大腸へと送り込まれます。次に、大腸を巡って最下部の直腸へと運ばれますが、その間に水分が吸収されて、液状だったものが次第に固くなり、やがて固形になって便として排出されます。
直腸とは肛門のすぐ奥にある部位です。ここに便が溜まると脳で便意を感じる仕組みになっているのですが、排便しきれなかった便が直腸に残っていると、一晩で水分が吸収されて硬くなります。そして翌日、その上に新たな出来たての便が重なります。このとき直腸では、古くて硬い便の上に新しく柔らかい便が二段積みになって溜まっているとイメージしてください。硬い出残りの便が肛門にふたをして、新しい便が出るのを妨げているわけです。
排泄すると、先端は硬くなった昨日の便、後半は柔らかい当日の便という状態になります。もし、トイレタイムを十分にとれないなどで出し切れない場合、肛門括約筋でちぎって排便を終わりにすることになります。するとまた、直腸に便の一部が残ったまま硬くなっていきます。これが「出残り便秘®」です。
——「出残り便秘®」という言葉は、大阪肛門科診療所の登録商標とのことですが、どうして登録されたのですか。
佐々木医師:「出残り便秘®」と、後で説明する「鈍感便秘®」も登録商標にしています。便が肛門付近の直腸まできているのに、排便反射が起こらず、直腸に便が停滞してうまく排便できない状態を「直腸性便秘」と言い、多くの情報がありますが、当院では、その学術的な定義とは少し違う状態を「出残り便秘®」と表現して患者さんに説明をしています。間違った情報が広まるのを少しでも避けたいからです。
出残りに慣れると、次に「鈍感便秘®」になる
——直腸に便が残っていると便意を感じると言いますが、気づかないのはなぜでしょうか。
佐々木医師:便を出し切れていない場合、「残便感」と呼ばれる気持ち悪さがあるでしょう。ですがそれが続くと、すぐにその感覚に慣れるようになります。つまり、残便感を覚えなくなるわけです。これは、直腸の異変に対して鈍感になっているということであり、当院ではこの状態を「鈍感便秘®」と呼んでいます。
——「鈍感便秘®」になると、どのような問題が起こるのでしょうか。
佐々木医師:「鈍感便秘®」とは、直腸や肛門に便があるにも関わらず、便意を感じなくなっている状態なので、症状が進むと大量に便が溜まらないと便意が起こらなくなります。そのため、数日間排便がなくなります。
こうなるとさすがに、自分は「便秘だ」と自覚するでしょう。そのときに、「出残り便秘®」が積み重なって、「鈍感便秘®」になっている可能性があることを知ってください。
出残り便に下剤は効かない
——何日も便秘が続くと、薬を飲んで改善したい人が多いと思いますが、「出残り便秘®」、「鈍感便秘®」は下剤で改善できるのでしょうか。
佐々木医師:内服する便秘薬の多くは下剤と呼ばれるタイプで、これから新しくつくられる便を柔らかくする、直腸までの運搬をスムーズにするように働きます。そのため、すでにできあがって肛門の近くに下りてきている便や、ましてや出し残しの出残りの便には効きません。口から入るものはお腹、腸に効くのであって、出口には効かないのです。
だから腸がちゃんと動いていて毎日お通じがある「出残り便秘®」の人が下剤を飲むと、腸のぜん動運動が過剰になって腹痛や下痢を起こすのです。
出始めが硬い、コロコロしていると「出残り便秘®」の疑いあり
——自分が「出残り便秘®」かどうかが気になります。
佐々木医師:「出残り便秘®」の場合、毎日お通じがあっても、「出始めが硬くて出にくい」などの特徴があります。次のような症状がひとつでもあれば、自分はそうではないかと疑ってください。
(1)便の出始めが硬い
(2)時々切れる
(3)温水便座を愛用している
(4)何度も紙に便がつく、拭く回数が多い
(5)下着に便がつく
(6)紙で拭くたびに便がつく
(7)1日に何度も便が出る
(8)食べるたびに便が出る
(9)くさいオナラがよく出る
(10)おなかがはる
——「出残り便秘®」を放っておくと、どうなりますか?
佐々木医師:出始めの硬い便で切れ痔(裂肛・れっこう)になったり、便による圧迫でいぼ痔(痔核・じかく。脱肛・だっこう)になったり、残便で下着を汚したり、過剰衛生症候群と呼ぶ洗い過ぎによって肛門の皮ふ障害を起こしたりと、いわゆる痔だけでなくさまざまなおしりのトラブルを起こします。
おしりはなかなか目で確認しづらいため、気つかないうちにそういった状態になることが多いのです。おしりの健康を考えると、「出残り便秘®」を早く改善することが重要になります。
——どうすれば「出残り便秘®」は防ぐことができるでしょうか。
佐々木医師:何よりもまず実践してほしいのが、便意を我慢しないことです。もよおしたらすぐにトイレに行くように習慣づけましょう。便意をもっとも感じやすいのは朝食後です。朝の時間の中心をトイレタイムに置いて、余裕を持って過ごしてください。また、職場や外出先ではつい我慢をしてしまうことがあるかもしれませんが、できるだけトイレを優先しましょう。
そして、日ごろから栄養のバランスが整った食生活を送る、睡眠の質や量とも充実させる、ストレスを溜めないようにするなど、生活習慣を見直して、便の状態を改善しましょう。
市販薬を選ぶ場合は自己判断をせずに、薬局の薬剤師に相談してください。
——ご指摘のいくつかは思い当たります。ありがとうございました。
「毎日便通があるから便秘ではない」とは、間違った思い込みであるようです。出づらい、またおしりに違和感があれば「出残り便秘®」かもと認識を改め、トイレタイムや生活習慣を改善し、また薬を選び直して真の快便を目指したいものです。
(取材・文 堀田康子・藤井空 / ユンブル)