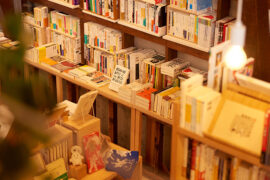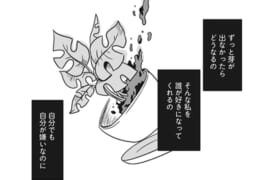PRプランナーとして34歳のときに起業した吉戸三貴(よしど・みき)さん(40)。コミュニケーションを軸に、企業や個人の課題解決に向けたサポート、執筆活動や講演も行っています。
まさに「コミュニケーションのプロ」の吉戸さんですが、子どもの頃は極度の人見知りだったといいます。人一倍コミュニケーション下手だった吉戸さんがコンプレックスを“得意”に変えるまでには決して前向きな動機だけではない6度の転職があります。
「人生で何が正解かはわからない。でも、自分で選んだ道を正解にする努力はできるはず」
と話す吉戸さんに、話を聞きました。
22歳 慶應義塾大学卒業後、某官公庁の契約スタッフに。半年後、契約満了につき退職。
23歳 都内にある国際会議の運営会社を試用期間中に退職。
25歳 沖縄にある国際会議・イベントの企画会社を留学のため退職。
27歳 国立劇場おきなわ(契約スタッフ)を転職のため退職。
31歳 美ら海水族館を転職のため退職。
34歳 都内のPR会社を起業のため退職。
「慶應は出たけれど……」挫折感いっぱいの社会人スタート
慶應義塾大学を卒業後、官公庁の契約スタッフとして契約期間いっぱい勤務したのち、国際会議の運営会社に就職した吉戸さん。しかし、人間関係のストレスで試用期間中にリタイアするという挫折を味わいました。
一旦実家がある沖縄に戻ることにした吉戸さんは、当時九州・沖縄サミット関連の仕事で多忙を極めていた国際会議やイベントを請け負う会社にアルバイト入社しました。地元での新生活スタートでしたが、仕事のスキル不足を補おうと無理をするあまり、あるとき過労で倒れてしまいます。
「前職での失敗もあり、最低1年、できたら3年はこの職場でがんばろうと心に決めていました。今思えば体調管理やペース配分ができておらず、とにかく力任せに働いていました」
「第二新卒」という言葉もなかった当時。吉戸さんは、外資系企業や大手企業で働く大学時代の同級生たちに大きな引け目を感じていたといいます。
「『私、今こんな仕事をしてるんだ』と言えない、後ろめたさのようなものがありました。職場に不満があったわけではなく、周囲に甘えてどうにか居場所をもらっているだけの自分がイヤで仕方ありませんでした。勉強では、中学受験をした小学生の時から大学受験まで全部自分で行きたいところを選んできたのに、仕事では何も選んだり決めたりできなかった。いきなりお手上げになったんです」
「腐ったパン」を投げられた先に見えたもの
「留学してみたら? 何かが変わるかもよ」
八方塞がりだった吉戸さんに声をかけたのは海外帰りの同僚でした。思いもよらぬ言葉をかけられ、最初は戸惑ったものの沖縄県国際交流・人材育成財団の奨学金留学の試験に挑戦することに。同僚の協力のもと、一からフランス語を猛勉強した末に、1年間のフランス行きの切符を手にします。当時勤めていた会社も「留学が決まったなら」と快く送り出してくれました。
「今までダメダメだったのに、奨学金でパリに留学できる。それってちょっとオシャレじゃない!? と、社会人になって初めてテンションが上がりました」
しかし、期待に胸を膨らませてパリに留学したものの、いきなり下宿先の大家さんの脱税が発覚。真冬のパリで、フランス語で敷金の返還を交渉しつつ新しい家を探すという大ピンチに陥ります。怒った大家さんから腐ったパンを投げつけられたことも。それでも丁寧に交渉を重ねて、どうにか敷金の回収に成功。
新たな下宿先も見つかり、異国の地で大きな壁を乗り越えた吉戸さんは「コミュニケーションは、相手に伝わって初めて成立するもの。自分で思っているだけでは何もしていないのと同じなんだ」ということに気づきました。
と同時に「自分は笑顔のつもり、がんばっているつもりでも、相手はそう思っていないこともある。私はこれまで『一生懸命やっているのに、どうしてわかってくれないの?』と独りよがりのコミュニケーションを繰り返してきたのかもしれない」と反省するきっかけになったと言います。
何度辞めたって、自分が変わらなければステキなことは起きない
コミュニケーションについての大きな気づきを得て帰国した吉戸さんは、留学でお世話になった財団の紹介で「国立劇場おきなわ」を運営する団体で、契約スタッフとして働き始めました。
「これまでのコミュニケーションは間違っていたと気づいたので、まずは表情と挨拶を変えました。とにかく昔から『無表情で何を考えているかわからない』と言われていたので、大きな笑顔と明るい挨拶を心がけるようにしたんです。急に筋肉を動かしたので、家に帰ると毎日ほおが痙攣して大変でした」
「苦手な人をできるだけつくらないように心がけ、難しい調整が必要な相手でも日参してとにかく笑顔で対応する」ことを日課としていた吉戸さん。そんな吉戸さんの働きぶりに目をつけた上司のはからいで、宣伝編集の部署に異動になり、こけら落とし公演のパンフレット制作など大事な仕事にも関わらせてもらえるようになりました。さらに、契約期間が終わることを心配した上司が転職情報を持ってきてくれたり、折に触れて仕事のチャンスをくれたりと、明らかに新しい風が吹き始めました。
「職場を変えたら自動的にまわりが優しくしてくれる、ステキなことが起きる、なんてことはありません。まずは自分が変わらなければ見える景色は変わらない。ようやくそのことに気がつきました」
この時27歳。年齢的にもそろそろ正社員にならないと……と焦っていた矢先、沖縄・美ら海水族館で中途採用の募集がかかっているという情報を耳に。「とにかく安定した仕事がほしい!」、その強い思いで高倍率を突破した吉戸さんは、沖縄を代表する人気施設の広報職を得ます。
奥底にあった「東京で通用しなかった」コンプレックス
オープンから間もない美ら海水族館での仕事は、これまでの吉戸さんの足りない社会人経験を補ってあまるほどの密度の濃さだったといいます。入社から4年……仕事も面白く、職場の人間関係にも恵まれ、人気施設の広報という周囲が羨む看板もある。
それなのに吉戸さんは5度目の「辞める」決断をしようとしていました。
「自分は東京で通用しなかった人間なんだというコンプレックスをずっと引きずっていました。東京が一番だとは思わないけれど、社会人として受け入れてもらえなかった、何か大きな忘れ物をしてきたという感覚が、ずっと心の奥に残っていました。また、このままでは、人気施設の看板に甘えて勘違いをしてしまうのではないかという恐さも感じていました」
吉戸さんは美ら海水族館を辞めることに半年間悩んだと言います。
「私が持っている美ら海のカードは、トランプでいえば一番いいカード。知名度や安定性でいえば、これまでの人生で手にしたなかでベストな1枚だった。周囲も親も安心してくれる。どうしていいカードを捨てて、不確かなものに手を伸ばしているんだろうって。この時31でしたから、当然、結婚や出産のことも頭をよぎりました。沖縄で結婚をして子どもを産み、実家の助けも借りながら仕事と家庭を両立する。私が『そうしたい』って言ったら、それは全部叶いそうだった」
それでも「辞める」ことを決断した吉戸さん。「たくさんの人に、もったいない、何やってるの? と言われました。でも、何が幸せかは自分しか決められない。誰かが私の人生を引き受けてくれるわけじゃない。私は、自分で自分にOKを出したかったんだと思います」
独立は「消去法」? 会社を興したワケ
美ら海水族館を退職したのは31歳。その後入社した東京のPR会社では、広告代理店への出向、海外出張、官公庁や外資系メーカーのPRを担当するなど、多忙ながらも新卒の時に思い描いていたワークスタイルを手にします。しかし3年後、またしても人生の岐路が――。
「30代半ばに近づき、プレーヤーとしてだけでなく、売上やマネジメントなどを求められる年齢に差し掛かってきました。PRの仕事に入った年齢が遅かったこともあって、得意・不得意がはっきりしていたんですが、今後私に求められるのは後者のスキルでした。これからの長い時間、不得意な仕事という大きな穴を埋めて均一にしていくことに力を注がなければならない。それはツラいなって」
会社がイヤなわけでもなくPRの仕事は好きだったという吉戸さんに同業他社への転職という選択肢はありませんでした。「会社がないなら、自分で何かするしかないのかな」と「消去法」で独立を決断しました。
最後の会社を辞めたのち、吉戸さんはコミュニケーションスタイリスト*というまったく新しい肩書きを携え、34歳で株式会社スティルを立ち上げます。
*2011年当時。
個人事業主ではなく会社を興したのは「信頼を得るため」だったといいます。
「コミュニケーションスタイリストは誰も知らない新しい肩書きなので、会社があった方が怪しまれないなと(笑)。謎の肩書きで会社を作るなんてバカだと言う人もいましたが、せっかくイチから始めるなら、全部、自分がやりたい方法でやってみようと思いました。それなら、失敗しても自分のせいだと諦めがつくから」
吉戸さんが作った会社「スティル」は今年の10月で丸5年を迎えました。
「ここへきてようやく、ほんの少しだけれど人生の主導権を取り戻せている気がします。はたから見たら、小さくて地味な車かもしれないけれど、少なくとも、私はいま、自分自身でハンドルを握り進む道を決めている」
吉戸さんにとって「辞める。」とは、“自分スイッチ”を入れることだと言います。一つは、心に明りを灯し自分が欲しいものを見つめ直すという意味のスイッチ、そしてもう一つは人生の進路を変える意味でのスイッチ。
「いろいろな理由で会社を辞めましたが、全部が前向きな理由ではありません。逃げや挫折に近い部分がたくさんあったと思います。でも、転職を重ねて感じるのは、体裁を気にした『立派な辞め方』より、『自分はどうしたいのか?』が大切なのだということ。今の会社に残るのも辞めて次に行くのもいい。いずれも“選択”であることに変わりはありません。あとは、自分が選んだ道を“正解”にする努力をしていくだけだと思うんです」
(江川知里)