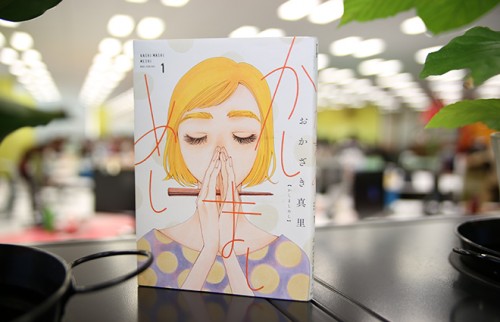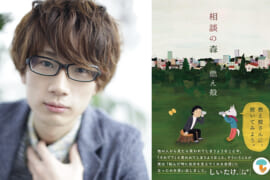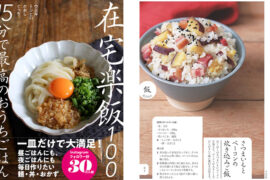10月11日は国連が定めた「国際ガールズ・デー」。
女の子が可能性や能力を社会で存分に生かしていくために制定された国際ガールズ・デーを前に、10月9日、東京都内でイベント「Go,Learn,Change! 未来を変えるガールズ・パワー ~ルワンダの女の子たちを迎えて~」が開催されました。
ジェンダー・ギャップ指数、ルワンダは6位 一方日本は…
イベントは、国際NGO「プラン・インターナショナル」が主催。ルワンダから女子中学生のフランソワーズさん(15)とレベッカさん(14)、ジェンダー専門家のグレース・コブホロ・カナムギレさんが来日してスピーチをしたほか、“男装をやめた東大教授”として知られる東京大学の安冨歩教授が講演を行いました。
レベッカさんは「女の子はいろいろな理由で勉強を続けるのが大変。その原因は、女の子のほうが男の子に比べて能力が低いと、女の子も含めて思い込んでいるから」とルワンダの少女たちが置かれている状況をスピーチ。フランソワーズさんは「周りの女の子のために教育の大切さを訴えるために国際的なジャーナリストになりたい」と訴えました。
一見、日本より「遅れている」ように見えるルワンダの社会。確かに「暴力は男らしさである」との伝統的な考えが根強く、多くの女の子や女性が男の子や男性による暴力の被害に遭っているという女性があとを絶ちません。しかし、2015年にスイスの「世界経済フォーラム(WEF)」が発表したジェンダー・ギャップ指数でルワンダは6位にランクインしました。ルワンダは、1994年に起きた虐殺以後、国家再建の過程でジェンダー平等を推進し、2003年には議席の3割以上を女性とするクオータ制(割当制)を導入しました。
一方、日本のジェンダー・ギャップ指数は101位でした。
安冨教授は「日本は101位。そのことを考えるとサポートを受けるべきはどちらの国かと思う。ルワンダの暴力は露呈した見えやすい暴力。日本にはそういう見えやすい暴力はないけれど、結果は一緒というより(ジェンダー・ギャップで見たら日本のほうが)低い」と指摘。
「日本の女性差別の構造は、ルワンダと一緒。例えば出産。出産という問題を社会から排除している。女性らしく生きようとすると社会的なポジションから排除する。女性だけではなく日本社会全体を苦しめている」と呼びかけました。
”立場主義”に捉われる日本
安冨教授によると、日本の女性差別は”立場主義”と結びついているとも。
「日本社会は個人同士がつながっている社会ではなくて、立場と立場がつながっている社会。日本人が恐れることは、立場を失うこと。立場に相応しい役目が課されていて、役を果たすために生きている。そんなイデオロギーにがんじがらめにされている」
「男女の区別、差別が最初の区分けとして機能して、区分け(自分の役割)に応じて振る舞うトレーニングを積んでいくことで秩序を保つ社会を作ることに成功している。それが日本社会における男女不平等の根幹にある。隠蔽された暴力がある限り、”立場”は幸せになっても人間が幸福を感じることはない」と力を込めました。
エンパワーされるのは私たち?
”見えない暴力”にさらされている日本。そんな日本に住む私たちが進むべき道は?
安冨教授は「1人1人の人間が男性とか女性とか関係なく、女性の服を着ているとか男性の服を着ているか関係なく、それぞれの人間が自分自身を表現し、議論したりしながら秩序を生み出していく。そういう生き方を生み出さないと、私たちが抱えている問題を解決することができないし、将来を切り開いていくことはできない」。
「男女差別を乗り越えるために(ルワンダのような)先進的な国から学ぶ機会が与えられている。そこにある露骨な暴力を凝視する機会が与えられている。ルワンダの”かわいそうな女性”をエンパワーするのではなく、私たち1人1人がエンパワーされる機会が与えられている」と訴えました。
最後に「13歳で結婚。14歳で出産。恋は、まだ知らない」というコピーを引き合いに「『33歳で結婚。34歳で出産。恋は、まだ知らない』という人は日本に多いのでは? “立場上”結婚してしまった人もいるのでは? 捉われているものを打ち払って本当の人生を実現していくのが大事なのでは」と締めくくりました。
(編集部)