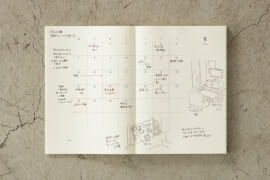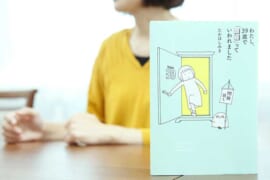むし歯、歯周病、口臭、口内炎など、口の中に起きるトラブルを「口バテ」と呼び、そのメカニズムやセルフケアについて提唱する歯学博士の照山裕子医師に、連載にてお話しを聞いています。
第1回では、口バテの状態や原因と口臭のセルフチェック法について、第2回では唾(だ)液の分泌を促すにはガムよりグミが有用という最新データの紹介や、自分でできる唾液マッサージについて触れました。今回は、口バテをセルフケアする「毒出しうがい」の方法について尋ねます。

照山裕子医師
「毒出しうがい」で口内のばい菌や食べかすを洗い流す
——「毒出しうがい」といううがい法を提唱されていますね。どういう意味ですか。
照山医師:「毒」とは、 歯垢(しこう。プラーク)のもとになる口内のむし歯菌や歯周病菌などのばい菌や食べかすのことを指します。
ものを食べたり飲んだりすると、歯の表面や歯の周りに糖分が付着し、ばい菌のえさになります。ばい菌が増えると集落をつくり、かたまって目にも見えるほどの歯垢になります。軟らかい歯垢は歯みがきで取り除くことができますが、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目はブラッシングがしにくく、歯垢が残りやすい場所です。
磨き残しの歯垢は2~3日で歯石となります。歯の周りに歯石のようなでこぼこした障害物があると、そこはさらにばい菌が増える足場となります。また、かたくなった歯石は自分では取り除くことができなくなるので、軟らかい歯垢の段階で、歯ブラシや歯間ブラシなどでていねいに除去することが重要です。
さらに、なるべく歯垢を溜めない習慣を身につけると、日々のセルフケアが楽になります。毒出しうがいは、歯垢の元になる食べかすを洗い流すための、口内のうがい法として提唱しています。「普段から口の中をきれいにしておこう」という感覚で取り組むと継続しやすいでしょう。
実践! 毒出しうがい
——毒出しうがいの具体的な方法を教えてください。
照山医師: 1日3回、食後のタイミングのほか、間食後や口の中がネバネバするとき、口臭が気になるときなどいつでも簡単に取り入れられる習慣です。次のように行ってください。
① おちょこ1杯分ほどの量(約30ミリリットル)の水を口に入れ、口を閉じます。
② 口の中の水を上の歯に向けて、クチュクチュとできる限り大きな音をたてながら強めに速く、10回ぶつけてから吐き出します。
③ ②と同じように、下の歯に向けても10回ぶつけて吐き出します。
④ 右の歯にも同様に行います。
⑤ 左の歯にも同様に行います。
口の周りが疲れてくるかもしれませんが、それはうまくうがいができている証拠です。また、口に含む水の量が多いと口が十分に動かせません。逆に少ないと汚れが落としきれません。目安は30ミリリットルですが、自分にとってちょうどいい量になるように何度か試みてください。

刺激が少ない常温の水やぬるま湯が最適
——毒出しうがいとは、誰でもすぐにできる方法なのですね。どのように口バテを改善するのでしょうか。
照山医師: 毒出しうがいをすると、口内を洗浄し、歯周病菌やむし歯菌の増殖を抑えることができます。また、口内や口のまわりを動かすことでサラサラとした質のいい唾液の分泌を促すことができるため、口臭の予防にもなります。
さらに、疲れていて口がだらんと開きがちのときは口内が乾燥する、ばい菌や異物が口の中に侵入しやすくなるなどの口バテで、口呼吸をしている状態でしょう。毒出しうがいは口周りの筋肉を鍛えるトレーニングにもなるため、口呼吸の改善になり、口内を健全に潤すように導きます。
——お茶や洗口液などで毒出しうがいをしてもいいのでしょうか。
照山医師:毒出しうがい用には、口に含んでも刺激がない常温の水、ぬるま湯が最適です。抗菌作用や消臭作用がある緑茶でも問題はありませんが、茶渋で歯が着色することがあるので頻繁な使用は避けましょう。
洗口液を使用する場合、アルコール成分が含まれるものは口の粘膜への刺激となることもあるため、1日に1~2回にとどめましょう。
うがい薬の場合は、口内環境に合っていないものを使い続けると必要な菌まで殺すことがあるため、注意が必要です。どんなものが適しているかは歯科医院で相談してください。
刺激の強い炭酸水、歯に油脂や色素が付着するコーヒー、糖分が含まれるジュースやお酒は毒出しうがいには適していません。
口内炎、むし歯、歯周病に毒出しうがいは有用?
——口内炎ができているとき、むし歯や歯周病と診断された場合でも、毒出しうがいは有用ですか。
照山医師:口内炎の場合は、痛みが治まっていればOKですが、痛みがあるときは傷口に刺激を与えて治癒が遅れることがあるので避けてください。
むし歯や歯周病の場合は、積極的に取り入れましょう。これらの原因は歯垢です。歯垢は歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどの補助的清掃用具を使って取り除く必要があります。しかし、毒だしうがいをセルフケアの一環とし、歯垢を溜めない習慣を身につけることは口の環境を良好に導く第一歩です。
ただし、歯を抜いた後やインプラントの手術をした後は歯科で「うがいを控えるように」と指導されます。治る過程で血のかたまりのかさぶたができますが、強くうがいをするとそれを流してしまうからです。そのため、出血があるうちは毒出しうがいも避けてください。
つまり、口の中にケガなど、痛い何かがある場合はやめておきましょう。それ以外の日常では、いつでも何度行っても大丈夫です。
聞き手によるまとめ
毒出しうがいを実践すると、口の中のネバネバ感が取り除けたようで爽快感があります。「毒」とは口内のばい菌を増やす原因となる食べかすのことで、毒出しうがいとはそれらを洗い流し、口臭予防にもなり、口周りの筋肉の衰えを防ぐトレーニングとしても有用だということです。いつでも手軽に実践できる習慣として生活に取り入れたいものです。次回・第4回では舌苔の正体やセルフケアについて紹介します。
(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)