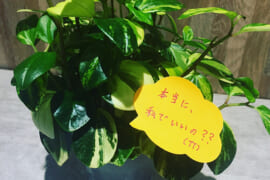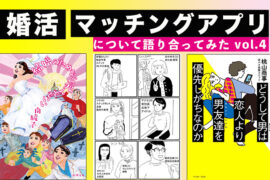疲れているとき、気づけばマスクの中で口をだらんと開けている、口呼吸をしていることはありませんか。実はその行為、歯学博士の照山裕子医師によると、「『口バテ』を引き起こす原因です。口臭、口内炎、歯周病、むし歯などの口のトラブルの原因になります」ということです。
そこで、「口バテ」とはどういう状態か、そのメカニズムと対策、口臭ケアについて、連載でお話しを伺います。第1回は、口バテの状態と口バテによる口臭のセルフチェック法について聞きました。

照山裕子医師
口の疲労「口バテ」で口臭が悪化
——「口バテ」とはあまり聞きなれない言葉ですが、どういう状態をいうのでしょうか。
照山医師:口腔(こうくう)の疲労のことを私は「口バテ」と呼んでいます。夏に暑くて全身が疲れることを夏バテというでしょう。口も同じように、いろいろな原因で疲れるとバテるわけです。
口バテは一年中起こりますが、とくにストレスがたまっているときや病気の時、また、体が疲れやすいシーズンには注意が必要です。
——口バテがそうしたときに起こりやすいのはなぜですか。
照山医師:ストレス、病気、また季節の変わりめなどは体調を崩しやすいでしょう。そういうときは、心拍、血圧、体温、発汗などをコントロールする自律神経に負荷が強くかかり、免疫にも影響します。自律神経のバランスが乱れると免疫の力が低下し、平時は自然に排除している口内の歯周病菌やむし歯菌が増殖します。そうして歯周病やむし歯、口臭などが発生し、悪化しやすくなるのです。
また、疲れると口をだらんと開けがちになり、口呼吸をするようになります。マスク着用時はなおさらでしょう。これも口内の乾燥をまねき、口バテを引き起こす原因となります。
——そういえば、疲れているときは、マスクに口臭が付着してにおいます。口がバテると口臭が強くなるのですね。
照山医師:口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(VSC)というガスは気体です。このガスは水に溶けるので、サラサラした質がいい唾(だ)液が十分に分泌しているときはほとんどにおいがしません。唾液は口内を浄化する作用があり、唾液の量や質のありようは口臭予防の鍵となるのです。
しかし、疲れていて口呼吸になると口内が渇くでしょう。唾液の量が減少し、質もネバネバして悪くなります。こうなるとガスを浄化できずに、口臭が発生しやすくなります。
生理的口臭は誰にでもある
——逆に考えると、口臭が強いということは、口バテのサインだということですか。
照山医師:そうです。歯科では、口臭を「生理的口臭」と「病的口臭」などに分類しています。口バテによって歯周病菌やむし歯菌が増殖すると話しましたが、これらが原因となる口臭、また、慢性鼻炎など耳鼻咽喉系、呼吸器系、糖尿病など全身の病気が原因の場合は病的口臭に分類されます。
一方、生理的口臭は、誰にでもある、文字通りに生理的な現象です。とくに、においが強い飲食物を口にしたときや、起床時、空腹時、緊張時、疲労時、また口バテ時には強めに発生します。ですが、食事や水分をとる、歯磨き、また疲労や口バテが回復してサラサラの唾液がたくさん分泌されるとにおいは弱まります。
病的口臭の場合は原因となる歯周病やむし歯を治療する必要がありますが、生理的口臭は治療の必要はなく、気になる場合でも生活習慣や口バテの改善でおさまります。
簡単にできる口臭セルフチェック3つ
——マスクに口臭がついていると、強さの程度が心配になります。調べる方法はありますか。
照山医師:においの目安がわからず、不安になることもあるでしょう。簡単に自分でできるチェック法を紹介します。
(1)口を閉じて1分間、鼻で呼吸する。
(2)未使用のビニール袋にゆっくり息を吐いてためる。
(3)袋の入り口をそっと開け、中のにおいをかぐ。

不快に感じるにおいかどうかを確認してください。わかりにくければ、家族や身近な人に確認してもらいましょう。気になる場合は、口臭検査を実施している歯科医院で検査をしてみるのもよいでしょう。
におうと感じた場合、主な原因は、「唾液量の不足」「唾液の質の悪化」です。それには、体の病気、むし歯や歯周病、体調不良、睡眠不足、食事の栄養バランスが乱れている、ストレスがある、口呼吸などが影響しています。そうした生活習慣を見直してみましょう。
聞き手によるまとめ
口バテとは口が疲労している状態のことをいい、口呼吸や自律神経のバランスの乱れなどによる唾液の減少や質の悪化が原因だということです。その口バテのサインでもある口臭の程度をセルフチェックで試し、日ごろの体調やストレスケアにもつなげたいものです。次回・第2回は、口バテによる口臭をケアする食事について紹介します。
(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)