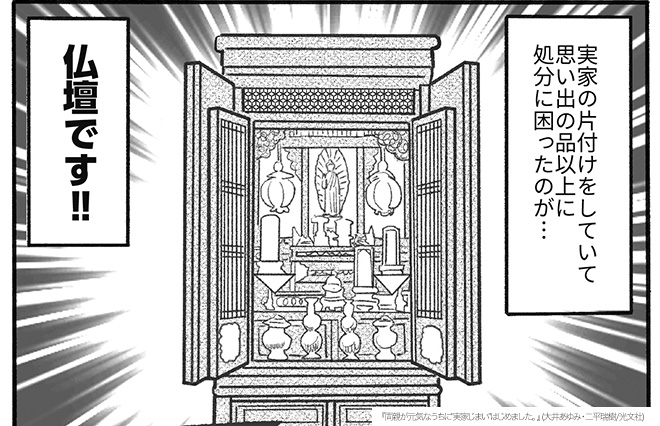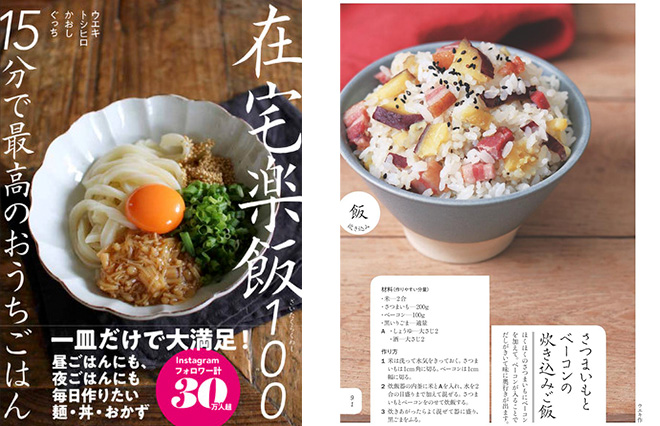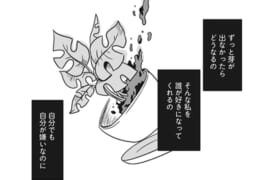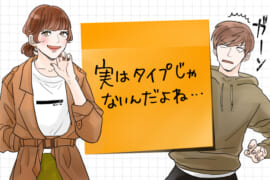健康に美しく生きるために、最先端の研究を学ぶYoutube番組「生命科学アカデミー」を配信する協和は、同番組に同志社大学生命医科学部の米井嘉一教授を招き、「良いAGEsと悪いAGEs!」ほか全5回を配信。米井先生に、老化の原因となる、体のサビ「酸化」と体の黄ばみ「糖化」が起こるメカニズムと対策法についてたっぷりとお話しいただきました。
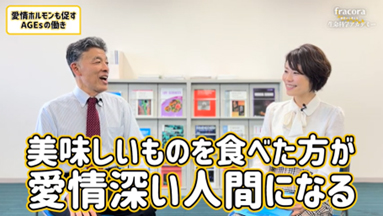
米井先生(左)と、聞き手で生命科学アカデミー学長のHIROCOさん(右)
※本記事はYouTubeチャンネル「生命科学アカデミー」で配信された内容を、ウートピ編集部で再編集したものです。
老化を促進する危険因子「糖化ストレス」
——老化に大きな影響を及ぼす酸化と糖化、このメカニズムを研究している同志社大学の米井先生にお話をうかがいます。さっそくですが、先生が今研究されている内容についてお聞かせください。
米井嘉一先生(以下、米井):僕はもともと内科医で消化器内科を担当していました。2005年からは、同志社大学でアンチエイジング医学(抗加齢医学)の研究をしています。「糖化ストレス」の研究を始めたのは2008年ぐらいから。体の老化を考えるうえで、老化を促進する大きな危険因子としての「糖化ストレス」というものが、非常に大事だと思ったんです。
「酸化ストレス」は聞いたことある人も多いのではないでしょうか。抗酸化サプリメントもあります。だけど、「糖化」はあまり聞かないと思いませんか? 人類は何十万年前から酸化ストレスと闘ってきて、今は酸化の研究も進んでいます。でも、糖化ストレスと闘い始めたのは、たかだか数十年前なんです。戦後の混乱期にはなかったものが、ここ数十年でだんだん強くなってきた。
「糖化ストレス」のひとつの結果として、糖尿病があります。糖尿病自体はそれほど症状がないんですけど、いろいろな合併症を引き起こす万病のもとです。今では、予備軍も含めると、患者数は2000万人くらいに増えてきています。そこには糖化ストレスが関係している。その橋渡しをするために、糖化ストレスの臨床と基礎研究を進めているところです。
——「糖化ストレス」とは、どういうものなんでしょうか?
米井:糖化反応とはもともと食べ物の反応です。1912年にフランスのメイラード先生が発見しました。どんな反応かというと、たとえばホットケーキを作るときに、小麦の中の炭水化物とタンパク質が反応して、熱を加えることでキツネ色になり、いい香りがする。これをメイラード反応生成物と言い、AGEs(エージーイー。終末糖化産物)ができます。
食べ物の場合には、香りもよくなるし、美味しくなります。でも、それが反応しすぎると、焦げてアクリルアミドという発がん物質になってしまいます。そういう糖化反応が進みすぎたAGEsは毒です。病気を誘発する可能性があります。
愛情ホルモンをアップする、よいAGEs
——ということは、AGEsの中には、良いもと悪いものがあるんですね。
米井:そうですね。特に、メラノイジンと呼ばれているものは良いAGEsの代表です。血圧を上げにくいとか、防腐作用、抗酸化作用を有します。
——メラノイジンが含まれるものは、食材でいうとどういうものでしょうか?
米井:たとえばコーヒー、味噌、醤油。我々関西人がよく食べるお好み焼きやたこ焼きにも、AGEsはいっぱい入っています。でも、食べすぎは良くないですよ。
——良いAGEsを食材からとると、体にどういう影響があるんでしょうか?
米井:先ほども言ったとおり、血圧を上げにくいとか抗酸化作用もあるんですけど、今注目されているのは、愛情ホルモンを発揮するのにAGEsが必要だということです。AGEsと特異的に結合するRAGE(レージ)という受容体があります。脳血液関門(BBB)に存在するこのRAGEが、脳に愛情ホルモン(オキシトシン)通過させることがわかったのです。
つまり、AGEsを食事からとることによって、愛情ホルモンが脳で作用するようになる。「美味しいものを食べたほうが愛情深い人間になる」というのが最新の研究結果の中で僕がいちばん好きなものです。
——幸せなお話が聞けてうれしいです。
米井:AGEsは人類の進化にも関係してるんですよ。50万年前から人類は火を使い始めましたが、火を使うと、食品中のAGEsが増える。そのころから、人類はほかの霊長類(チンパンジーやゴリラ)に圧倒的な差をつけて脳が発育しました。つまり、AGEsを食物からとれば、脳も発育するし、愛情も深くなるということです。
自分の身体で作られるAGEsに注意
——逆に、「悪いAGEs」をとると、体にどういう影響があるんでしょうか。
米井:例えば、超高温で調理すると焦げますよね。食材が焦げ付く手前にできる物質がアクリルアミドという発がん物質です。
——焦げたものは身体によくない、という話をよく聞きますね。
米井:そうですよね。つまり、行き過ぎた(反応が進んだ)AGEsの一種に発癌物質(アクリルアミノ)があるので、調理時には気をつけたほうがいい。
——なるほど。では、老化と「悪いAGEs」の関係というのは……? 焦げた食べ物に気をつけるということ……?
米井:いえ。食品からAGEsをとるのが問題というより、食品からではなく体の中にあるタンパク質がAGEsになってしまうことが問題なのです。
一般的な人の場合、AGEsができやすいのは食後。いわゆる「食後高血糖」というものです。最近では「血糖スパイク」と呼ばれています。
——「怖いもの」というイメージだけあります。
米井:まず症状から話すと、「血糖スパイク」があると血管の内皮細胞を傷つけ血栓をできやすくします。すると、血管にダメージが蓄積されてしまうのです。
血糖スパイクの血糖値が上がりきったところで何が起きるかというと、グルコース(ブドウ糖)が開環して一部が化合物(アルデヒド)になります。それが同時多発的に手あたり次第、まわりのタンパク質と反応するんですよ。それが進むと、アルデヒドがAGEsになってしまいます。なので、体内でアルデヒドを作らないことをまずは意識していただきたい。
——そのAGEsは蓄積されるなど、体に影響が?
米井:タンパクによって代謝して体外に排出されることもあります。でも、たとえば目の場合、眼球の表面のレンズのタンパク、クリスタリンタンパクというのがあるんですけど、それは代謝が非常に悪い。そのため、白濁化し黄色くなったらもとに戻りません。
皮膚の表面のコラーゲンも、弾力性が失われて硬くなります。一方で、もっと表面にケラチンというタンパクがありますが、これはだいたい6週間でターンオーバーします。代謝するところとされないところ、両方あるんですね。
正常な老化、避けがたい老化
——先生は著書の中で、「自分の体の中でどこが老化しているのかを知ることがすごく大切」とおっしゃっていました。これはどういうことでしょうか。
米井:体というのはいろんな部品でできています。その部品が、全身バランスよく老化しているのが、一番元気なんですよ。百寿者、100歳を超えてもボケもない、大きな病気もない方々はたいていそうです。
たとえば、骨以外はまったく健康な人でも、骨が老化し骨粗しょう症になって転んでケガをしたら、寝たきりになって全身まで悪くしてしまう。一番の弱点である骨の老化を早めに見つけておけば、予防もできます。
みんな1年1年、平等に歳をとっていきます。正常な老化、避けがたい老化はいいんです。問題なのは、病的な老化により体の機能が低下すること。つまり、体の機能を保つのがアンチエイジングです。僕はアンチエイジングドックとか検診を推奨していますが、それは老化を促進する危険因子を探るためです。
——危険因子には、先生の専門である糖化ストレス、そして酸化ストレスなどがありますね。
米井:あと、昨今のコロナウイルスみたいな免疫ストレス、それからメンタルのストレス、加えて生活習慣もあります。でもやはり、大きく分けると糖化と酸化が大きいですね。分子レベルの老化と言いますか、体のいろいろな物質を直接変化させるわけなので、その仕組みを研究することで、どう予防するかの研究につながると思います。
(第2回へ続く)
■動画で見る方はこちら