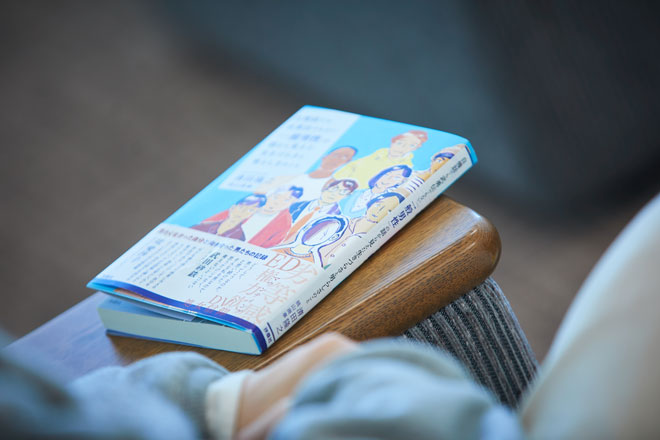恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表の清田隆之さん。ウートピでの連載「結婚がわからない」を担当する安次富が、新刊『自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から見えた生きづらさと男らしさのこと』(扶桑社/以下、『一般男性』)についてインタビューを行いました。
「ジャッジをせずに人の話を聞くことが、だんだん難しくなってきました」という素直な悩みを打ち明け、話を聞くことについて語り合いました。今回は、普段のカジュアルなトーンを織り交ぜつつお届けします。全3回の、第3回。
結局、炎上しましたか?
ウートピ編集部・安次富(以下、安次富):前回までは“一般男性”たちの話を聞くところまで話を聞きました。炎上の可能性も心配していたとのことですが、反応はいかがでしたか?
清田隆之さん(以下、清田): この企画は電子文芸誌「yomyom」で連載が始まり、その後WEBメディア「WEZZY」に転載されてから書籍化に至ったんだけど、恐れていたような反応は特になかった(そこまで読まれてないってことかもしれないけど……)。SNSなどに投稿された感想も、「発言が生々しくてゾワゾワする」「いい意味でヤバい」「こういう男性の自分語りは珍しい」など、肯定的なリアクションが多めだったので安心しました。
安次富:ゾワゾワ、ヤバいとは?
清田:たとえば、本書に出てくる東大生が「恵まれている人には恵まれるに足る理由があるんですよ」と言うんだけど、「そういうことが東大生の口からサラッと出ているのがヤバい」とか。普段は表に出ることのない本音がダダ漏れになっていることに驚き、「男性ってそんなことを考えてるんだ……」と衝撃を受けたと語ってくれた人もいた。
安次富:なるほど。語りを通じて、その中に宿る男性性みたいなものを見つめていくっていうコンセプトですもんね。そういう「ヤバい」みたいな感想って、話している人の見えているものと、見えていないもののギャップなのかなと思いました。参加した男性たちは、原稿チェックで改めて自分のエピソードを読むわけですよね? 反応はどうでしたか?
清田:ここに出てくれた男性たちは基本、自分を分析して言語化することに長けた人たちなんだとは思う。例えば「結婚したいというより“結婚歴”がほしい」とか、自分の求めるものに対してある程度客観的に見えている。それでもなお、原稿を読んでもらったときには戸惑いの声が多かった。「確かに自分が語った内容だけど、改めて文章化されるとしんどいものがありますね」とか、中には「俺ってこんなに気持ち悪いやつなんですね」という声もあって。
安次富:あー。私も文字になったときに自分の発言にそう感じることがあります(苦笑)。
複雑なものは燃えにくい
清田:せっかく取材に協力してくれたのに気分を害してしまったらどうしようと不安だったけど、幸いなことにみなさん「自己理解が深まった」「いい経験になった」と言ってくださり、懸念していたようなネット上での反応も今のところは見かけてないかも。
安次富:変に燃えなくてよかった。本書を紹介してくれた『一般男性』の担当編集・Mさんが「複雑なものは燃えにくい」とおっしゃっていて、確かにそうだなと思いました。
清田:もちろんインパクトの強い発言だけを抜き出せば炎上リスクも上がるのかもしれないけど、個人の体験を共有しながら内在している問題を見つめていこうという主旨の本で、その背景やプロセスには複雑な事情が絡んでいる。そこを含めて読んでもらえているのかなって。
安次富:ちゃんと企画意図が届いているってことですよね。複雑と言えば、以前、プライベートで悩み相談をされたときに、私は「それは社会の構造がおかしい」とかって思ったことがあって。「古い価値観に囚われなくてもいいのでは?」みたいなことを言ったと記憶しているのですが、今思うと主語がデカくて恥ずかしいし、その人は寄り添って欲しかっただけじゃない?って。歳を重ねるごとに、人の話を聞くのが難しくなっている気がします。
清田:何が傷つけることになるのか、寄り添うことになるのか。何が肯定の言葉で何が否定の言葉になるのか。新しいとか古いってどういうことなのか。考えれば考えるほどその複雑さに打ちのめされるよね……。
安易な寄り添いがアダになることも
安次富:清田さんは、人の話を聞くときに決めていることはありますか?
清田:桃山商事の活動ではよく「現在地」って言葉を使うのね。今、その人の目にはどんな景色が見えているのかっていうのをなるべく理解しようと試みる。完全に理解するのは不可能だと思うけど、2時間という時間の中で共有、近づくことが最初のステップではないかと考えていて。だからどんな話であっても、まずは相づちや質問も挟みながらじっくり聞いて、この悩みの背景にはどんな問題や思考プロセスが存在しているんだろうってことを考えていく。善悪や新旧といった価値判断はいったん保留にしつつ、「どういうことなのか」「どうしてなのか」「どうなっているのか」という、意味や理由、あるいはメカニズムの部分をみんなで考えていくことをしているように思う。
安次富:許容できないものが出てきたらどうですか? たとえば、犯罪行為が楽しくて仕方ないみたいな。
清田:それは確かに難しいところだね。「なんでそれが楽しいんですか?」とか、冷静に聞けるかもわからないし……。今回の企画でも、DVの加害経験を語ってくれた人や、女性に暴力的な性欲をぶつけてしまうことを語ってくれた人がいて、重たい空気になるときも結構あった。聞けば聞くほど背景に複雑な事情や個人史が関係していることが感じられてきて、思わず感情移入してしまう瞬間もあったけど、かといって「暴力を振るってしまったのも致し方なかったですよね」とは言えない。
だからどうしても「暴力は絶対にダメですが、背景にはそんなことがあったんですね……」という反応の仕方になってしまうんだけど、「殴ってしまったのは悪いことですけど」ってポイントを押さえるかのような言い方も、相手からしたら「軽々しく言わないでほしい」「あなたに何がわかるんだ」って気持ちになるかもしれない、とか葛藤があって。
安次富:その時はどうされたんですか?
清田:いったん自分に引きつけて想像してみたのね。自分の中で最も暴力に接近する瞬間ってなんだろうって。たとえば家には2歳半になる双子がいるんだけど、何かにつけてイヤイヤするし、夜泣きもまだまだあって常に睡眠不足で……疲労が限界になると思わず「ウルセェ!」ってテーブルをバーン!と叩き、子どもたちを黙らせたくなる衝動にかられる。
たとえばああいう気持ちがもっと膨らんで、さらにブレーキをかける力が弱まっていたら、具体的な暴力を働いてしまう可能性だって全然あるよなとか。そういう話なんかも織り交ぜつつインタビューを進めていきました。安易に寄り添った気になって器用に話を進めちゃうと、その簡単さがアダになってしまうこともあると思うんだよね……。
安次富:反射的に「わかる!」と肯定してしまいがちですが、でも実はそこから先に進まない。やっぱり「わからないよ」ってことを互いに共有しないと対話にならないのかなって思います。
清田:共感を示すためだけの機能的なシンパシーって危険な面もあるもんね。
「人を傷つけないこと」は可能か
安次富:私が最近SNSを見ていて気になっているのが「人を傷つけないこと」への圧力です。大事なことなので、それ自体は否定しません。ただ、それが自分を抑圧したり他者への強要になるとちょっと怖いな、と。
それが絶対の正解になると、こうあるべき、あれはだめ、これもだめっていうのがどんどん出てきて、常に「正しさ」の中に身を置き続けないといけなくなる気がしていて。それって窮屈な感じがするんです。
清田:傷つけないように心がけた振る舞いが結果的に相手を傷けてしまうこともあり、本当に難しい問題だなって思う。
安次富:そうなんですよ、複雑。もちろん、あらゆる差別、暴力には反対です。故意に他者を傷つけようとするのは論外。だけど、結局、人が2人以上いればどんな関係でも衝突や摩擦は避けられないんじゃないかと。清田さんは「傷つき」についてどう考えますか?
清田:完全に避けることは無理だけど、かと言って「傷つけちゃうのは仕方ない」と開き直ることもできない。自分も『一般男性』がきっかけで誰かを傷つけてしまうかもと考えるとすごく怖い。SNSとかで「この本に出てくる男が気持ち悪い」って書かれちゃったとして、彼らがそれを目にすることもあるかもしれないじゃない? あるいは、こうして自分が答えてるインタビューなんかを読んで、「清田さん、実は取材中にそんなこと思ってたんだ」ってショックを受けるかもしれないし。
傷つける意図はありませんというメッセージを万全の配慮で張り巡らせたとしても、誰がどう受け取るかはわからない。わずかでも傷つける可能性があるのなら、一切言及しないっていうやり方もある。でも、これは言い方がとても難しいんだけど、それだと文章を書いたり言葉を発したりする行為の意味自体が失われかねないという。
安次富:そうですね。
清田:誰かを傷つける可能性は覚悟の上で発信するんだって思っていたとしても、実際に傷ついた人が出てしまったときに「それは覚悟の上なので」と開き直るのも違う。どこに問題や間違いがあったのかを学んでいくしかないとも思うんだけど……。
安次富:あなたの学びのために傷ついたわけじゃない、って言いたくなるかもしれない。
清田:本当にそうだよね。勝手に他人の傷を学びの肥やしにするんじゃねえっていうのもあるはずだから。確かに、がんじがらめになっている感じは……。正直、どうしていいかわからないっていうのはある。確かにあるんだけど、それって逃げてはならない、抱えるべき葛藤でもあると思う。
これまでも、発信行為で傷ついた人ってたくさんいたはずだけど、声をあげる術や、それが広く共有される文脈や流れがなかったから、たまたま目に入ってこなかっただけで。そういう声がなければ、発信する側は今なお伸び伸びしていられたかもしれないけど、もう声は可視化されるようになった。これは不可逆的な流れだと思う。
安次富:そうですね。
清田:我々はそういう状況の中で「じゃあどうするか」ってことを考え続けていくしかないと思う。傷つけるのは仕方ないんだって開き直りに近い覚悟を固めることもできないし、誰かを傷つける可能性の芽を完全に取り除くこともできない。漠然とした答えで恐縮だけど、その間で揺れ動きながら試行錯誤していくしかないような気がしています。
(取材・文:安次富陽子、撮影:面川雄大)