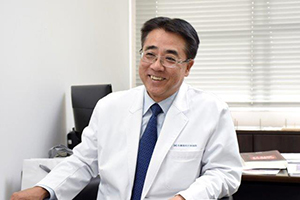「胃が重い、苦しい…機能性ディスペプシアを治したい」と題し、消化器病指導医・専門医で著書に『胃は歳をとらない』(集英社新書)がある三輪洋人医師に連載でお話しを聞いています。
胃の検査をしても異常がないのに、胃もたれや重苦しさ、痛みがつらい病気を「機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)」といい、その特徴や原因、治療法について紹介してきました(リンク先は文末参照)。今回・第4回は、機能性ディスペプシアを自分でケアする食事習慣について尋ねました。

胃の苦しさは食事習慣に密接に関係する
——機能性ディスペプシアの改善や予防のために、自分でできることはありますか。
三輪医師: いくつもあります。機能性ディスペプシアはおもに内服薬で治療(第3回参照)をしますが、いったん改善したとしても、再発しやすいことがわかっています。予防のためにもセルフケアはかかせません。
機能性ディスペプシアのケアのポイントは2つあります。1つはまず、つらい症状は食後に多く見られることから、食事習慣と密接な関係があると考えられます。
次に、ストレスや不安が症状に関係することもわかっています。つまり2つめとして、これらをケアする生活習慣が有用になります。
——では1つめの「食事習慣」についてのセルフケアはどうすればいいでしょうか。
三輪医師: 具体的に次のことが挙げられます。
・食事のとりかた…機能性ディスペプシアの人は、健康な人に比べて「早食い」「食べすぎ」「よく噛(か)まない」「食事をする時間が不規則」という習慣の人が50~80%であるという調査報告があります。
また、「急いで食べたとき」「食べすぎたとき」「脂っこいものを食べたとき」と回答した割合が高いこともわかっています。
さらに、「食事中に心配ごとがあるとき」と答えた人の割合は、機能性ディスペプシアの人では67%で、健康な人の24%に比べて有意に高くなっています。
ご自身の食生活において、こうしたことに心あたりがないかを見つめてみましょう。
・食事内容……脂肪分が多い揚げ物、炒め物などは、機能性ディスペプシアの症状を誘発します。また、麺類やパンなど小麦粉を使用した食事は、腸で発酵されて症状を起こす場合が多いことも知られています。
さらに、お酒にも問題があります。食欲増進作用があって過食になりやすく、つまみには高カロリー、高脂肪、高スパイスの食べものを選びがちだからです。また、カフェインが含まれるコーヒー、紅茶、緑茶などは胃酸の分泌を高める作用があるため、これらを過剰に摂取することは避けてください。
早食いを避ける方法は
——早食いを避ける方法はありますか。
三輪医師: 食事をすると胃の上のほうの食道に近い部分がふくらんで、より多くの食べ物を受け入れるように反応します。この反応は食事開始後、15~20分後に最大になります。
しかし、それまでに食べきる早食いの場合は、胃がふくらむ前に食べていることになり、胃の内圧が上昇して胃もたれや重苦しさ、吐き気につながるのです。
これを避けるには、意識をして15分以上かけてよく噛(か)んで食べることです。お客さんの回転が早い店は避けて、早食いの人と一緒に食べるのもつられるので避けて、場所と相手を選びましょう。

食べすぎを避ける方法は
——では、食べすぎを避ける方法はありますか。
三輪医師: 食べすぎの場合は、胃の拡張反応や、消化を促進する消化管ホルモンが、胃の運動や排出の作用に支障をきたすように働いて、症状をまねきます。
過食を避けるためには、自分の体に合った食事の量をイメージして、どのぐらいの量を食べるかを決めてから食べ始めるようにしましょう。その決めた量を食べた後は、「もの足りないな」と思っても、箸を置いて15~20分ぐらい食べるのをやめると、だんだんと満腹感を覚えて食べすぎを防ぐことができます。
——夕方や残業時など、次の食事までの間におなかが減って困るときはどうすればいいですか。
三輪医師: 栄養補助食品のバー1本や、おにぎり1個、ヨーグルト1個など、200キロカロリーまでの間食をとりましょう。これを「補食」といいます。目的は、その後の食事の量を増やさないために「補っておく」ということです。
1回の食事量を減らして適量にすると、胃の負担が軽減して重苦しさも軽減します。それを体感し、継続していきましょう。やがて、早食いや食べすぎが胃に悪いということに気づき、その体験をきっかけに適量を規則正しく食べる習慣が身についていくでしょう。
聞き手によるまとめ
胃の上部がふくらむピークは食事開始から15~20分後であり、自分にあった食事量をイメージしてそれ以上の時間をかけてゆっくり食べようということです。胃の負担を軽減するために、すぐに実践したいセルフケアです。
次回・第5回は、セルフケアの続編として、食事中の心配ごとやストレスが影響する機能性ディスペプシアの改善法について尋ねます。
(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)