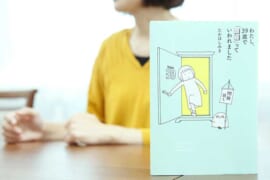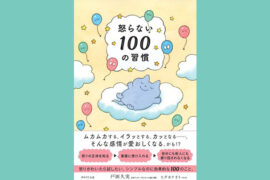ランニングやジョギング、ウォーキングをする、週末にテニスやジム通いをするなど、適度な運動の習慣を持つことは健康のためによいとされます。
ところが、臨床内科専門医で正木クリニック(大阪市生野区)の正木初美院長は、「激しい運動をしていると、『スポーツ性貧血』になる人がいます。これに悩まされるアスリートは多いという現実もあります」と話します。詳しく聞いてみました。
運動時、鉄の量が不足して貧血に
正木医師は、スポーツによる貧血についてこう説明をします。
「貧血の原因の多くは、病気である場合も含めて鉄の不足による『鉄欠乏性貧血』です。血液には、全身に酸素を運ぶという重要な役割があります。この働きを担うのが、血液中の赤血球の中にあるヘモグロビンです。ヘモグロビンの『ヘモ』は鉄分を含む成分で、『グロビン』とはタンパク質です。このヘモグロビンを合成するには、鉄が欠かせません。鉄はヘモグロビンの原料になります。
貧血とは、赤血球またはヘモグロビンの量が正常時よりかなり少なくなった状態で、そのため全身に酸素が運ばれずに酸欠となり、めまいや立ちくらみ、頭痛、吐き気、けんたい感、動悸(どうき)などの症状が現れます。
スポーツ性貧血の多くは、鉄の欠乏によります。鉄は食べたものを素材に体内で合成されますが、日々の活動や病気でその量が追いつかずに不足することがあるのです。激しい運動をしたときもそうなることがあります」
足の裏への衝撃で赤血球が破壊されることも
次に正木医師は、運動時に鉄が不足しやすい理由について、次の要素を挙げます。
・鉄の需要の増加……運動時は多くの酸素と、酸素を運ぶヘモグロビンが必要になる。
・過剰な鉄の損失……大量に汗をかくと、汗とともに体外へ排出される。
・鉄の摂取量の不足……ダイエットや偏食などで栄養不良が生じ、必要な鉄が取れていない。
「女性は男性に比べて貧血の頻度は3倍という報告があります。月経で喪失する血液量が影響しています」と正木医師。
また、ランニングやジョギングなど、足の底を床に打ち付けるスポーツの場合、スポーツ性貧血になりやすいと聞きますが、どういう現象でしょうか。
「テニスやバレーボールやバスケットボール、サッカーなど、走る、飛ぶなどで足の裏に強い衝撃を受け続けると、赤血球が破壊されることがあります。これを『溶血(ようけつ)』と呼びますが、そうすると血液中の赤血球の数が減少するため、貧血になることがあります」(正木医師)
いずれにしろ、激しい運動をするときは貧血に注意する必要がありそうです。
持久力の低下、疲れやすい、だるくなる
ここで、スポーツ性貧血のおもな症状と、貧血だと医学的に診断される基準について、正木医師に紹介してもらいましょう。
「運動時には、持久力が低下する、だるい、疲れやすい、息切れしやすいなどの症状が現れます。当然、パフォーマンスは低下し、これまではできていた運動を思うようにこなせなくなります。
貧血が疑われるとき、内科では、血液検査で定量の血液の中に含まれる『赤血球数』、『ヘモグロビン濃度(Hb)』、赤血球の容積の割合である『ヘマトクリット値(Ht)』、血液中の液体成分である血清に含まれる鉄分の『血清鉄』を調べます。
通常、ヘモグロビン濃度が低下している場合、貧血と考えます。血液は、少しとるだけでこれらの検査ができます。
また、軽い貧血では分かりづらいこともありますが、下のまぶたを引っ張って内側の色合いでチェックすることもできます。下まぶたの内側は、血管が集中していて皮ふが薄いので、通常は赤っぽいのですが、貧血が進むと白っぽく見えます」
鉄、タンパク質、ビタミンCを摂取する
続いて、スポーツを楽しんでいるときに突然のめまいや、貧血のように感じる症状が現れたときの「セルフケア法」を正木医師に教えてもらいました。
「まず、スポーツ中に貧血が疑われる症状があったら、できるだけすぐに休んでください。めまいや立ちくらみなどの症状が続いて、月経異常や婦人科系の病気の疑いがなければ、内科を受診しましょう。貧血と診断されたら、鉄剤の処方や、食事指導などがあります」
鉄はサプリメントも豊富に市販されていますが、その利用について正木医師は次のように指摘をします。
「市販のサプリメントと病院で処方された鉄剤を比べると、鉄の含有量や吸収のよさでは鉄剤のほうが優れています。また、鉄だけでなく、ヘモグロビンの材料となる良質なタンパク質、鉄分の吸収を助けるビタミンCの摂取も欠かせません。
サプリメントを利用するのはかまいませんが、何よりもまずは栄養のバランスが整った食事を心がけましょう」
ランニングをしていると充実感があって、しんどくても休憩しがたいことがよくあります。しかし、貧血を避けるためにも運動の継続には注意をして、食事や休息に気を配りたいものです。そして、不調が続くときは医療機関を受診し、検査をしてもらうようにしましょう。
(取材・文 堀田康子、岩田なつき / ユンブル)