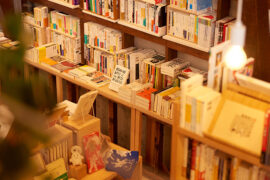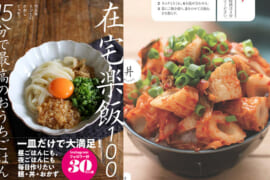職場でも、プライベートの友人でも、ついつい自分の意見を正論として押し付けてくる人っていませんか?
精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)先生によると、そういうタイプの人は、「過去の自分」をやり直そうとしているからなんだとか。
どういうことなのでしょうか?
「情念」とは怒りの結晶である
「私たちはときとして情念に動かされ、これを熱心さと思い違える」トマス・ア・ケンピス
中世の神秘思想家トマス・ア・ケンピスの有名な著作『キリストにならいて』からの一節です。15世紀に書かれたとされるものですが、見事にいまの僕たちをも侵し続ける心のからくりを射抜いていますよねえ。
まず「情念」とはなにか?ありていに言うと、人間の内から湧き上がってくる抑えきれないほどの強烈な感情、という具合に説明できますけど、おそらく根底にあるものは「怒り」の結晶でしょうね。
その結晶は、普段の何気ないひと言でも作られちゃうんですよ。たとえば会社の上司に「キミは頭もよくないしトロいんだから、もっとまじめに仕事しろ」なんて注意されたら、これは激しく傷つきますよね。向こうは無自覚だとしても、実はものすごい言葉の暴力。すると受けた人間にとっては、その言葉が自分の中で溶けてしまわずに、ひとつの塊のようになって残ってしまうわけですよ。
それって黒砂糖のような、あるいは新幹線の中で買うなかなか溶けないアイスクリームのような(笑)、ガチッとフリーズされた怒りの結晶というイメージをもっていただいてよいと思います。そして過去に感じた怒りは、また同じようなシチュエーションに直面すると、再び痛み出すんですよね。
その時、怒りの結晶が体内で疼(うず)いている人にとっては、世界のすべてが自分の過去と結び付けられるんです。
たとえば、何年も経って自分が上司から、かなり横暴な言葉を掛けられたとする。あるいは自分じゃなくてもいい、他の誰かがかつての自分と似通った目に遭ったとする。そうするとその人は正義の怒りに駆られて、「私はあの上司を絶対に許せません!」と激しい憤りを表明する。これって実際よくあることだと思うんです。
「正義の人」は強要しがち
ただね、そこから性急に「あなたも許せませんよね、あなたもそうですよね?」と、周りの人たちに同意を求め出すパターンに流れると、ちょっとやっかいな場面になります。
そんな過去の怒りや苦しみを持っていない人の場合、でもとりあえず理屈はわかるから「たしかによくないことですよね」とか、ちゃんと返事するでしょう。そうすると「じゃあなぜ立ち上がらないんですか?」なんて厳しく問われてしまったりする。
「これは社内改革が必要です!」とか「法に訴えましょう!」とかヒートアップされると、こっちは正直キョトンとしてしまいます。でも、熱っぽく正義を説いている側からすると、あいまいなこちらの態度は、なんていう無知だ、なんていう無関心だ、挙げ句はなんていう偽善者だ、という風に、勝手に断罪されてしまうことになる。
もちろんね、彼らの正義はそれなりに正論ではあるんです。本当は現実の矛盾に気づいているくせに、それを声高に訴えると、自分が不利益を被るから黙っているんだろう、とか。特に日本社会だと目立ちすぎると角が立つもんな、とかね。ただ、それを薄汚い保身であるかのように責められても、みんな各々自分の人生を自分のやり方でそれなりに苦労して生きているんだから、そのスタイルを突然責められたら、当惑したりとてもストレスになってしまうのは当然だと思うんですね。
だからある程度の保身は当たり前なんですけど、そういう少し距離を置いた冷静な態度に触れると、余計に当人は怒りが類焼していって、部署や会社の問題を通り越して、「この腐った日本社会を変えなければならない」とかね。どんどん正義の人として先鋭化していく。
それが切実に社会全体の問題意識と共鳴し合って大きなうねりになっていくものならね、一概に悪いとは言えない。かつてのアメリカの公民権運動みたいに、社会全体を是正する方向に向かわせた例も歴史にはたくさんあります。当然、全く逆にナチズムが台頭していく時のような、大衆の暗い熱狂を生み出す例もあるわけですけど。
原因は「自分の過去」にある
ともかく内なる情念に衝き動かされて、ある種の熱狂状態の中で正義や正論を説こうとしている人というのは、実は「自分の過去をやり直そうとしている」というのが心の本質だと思うんです。
しかもその「やり直し」の作業って、ほとんどの場合、自分の努力で過去の痛みを昇華するという方向は取らないんです。自分を傷つけた相手の行動を「変えさせたい」という形を取るんですね。
特に自分でも説明のつかないような、心の底から湧き上がってくる「情念」っていうのは、往々にして10歳以前、あるいは思春期までの幼少期に原因があることが多いんです。
誰だって子どもの頃は無力ですからね。特にいまの時代、学校教育の期間が長いでしょう。大学進学率もだいぶ高いですし、実社会に出て働くのを先延ばしにしていると、“子ども時代”が温存される。そうすると親や学校に保護されているようで、実は自立心をのびのび発揮できず、長期に渡って屈辱を感じやすい状況に置かれるとも言えるわけです。
しかも高校や大学を卒業したら、あまりにも急に「社会の中で責任を果たせ」と放り出されるわけでね。これは成熟の構造として無理があると思うんです。
本当はもっと細かく段階を追って、ごく若い頃から社会の成員として育てていくことが理想的だと思うんですけどね。だって仕事に有用な能力でも、細かく腑(ふ)分けすれば「瞬発力」とか「持久力」とか「暗記力」とか、いろんな種類があるでしょう。そう考えると、14歳の男の子には軽々できちゃうのに、57歳の僕には決してたやすくこなせないことが、少なく見積もっても100くらいはあるはずですから。
たとえば馴染みのないスペイン語の単語を1時間以内に40個覚えろ、とか、いまの僕では絶対無理(笑)。だけど頭の柔らかいローティーンの男の子なら、結構平気で覚えちゃうかもしれない。
「許せない」と感じたら気をつけて
子どもって、本当は無力じゃないんですよ。彼らにしかできない「仕事」もあるねん。
こういう見地から、教育における「実践」っていう言葉や概念も見直したらいいのにな、と僕は思っているんですね。いまの風潮だと、これからは社会の中で役に立つ実践的な教育が必要である、なんて議論になった時、じゃあ文学部を廃止しろ、なんて話にもなりかねない。でも社会の中で役に立つっていうのは、別に「すぐにお金になる」とかじゃないんです。
たとえば古代の文書を読み解く「実践」もある。シュメール文字に興味のある子どもがいたら、14歳から専門で勉強させたらええやん。その頃の吸収力って、ハタチ過ぎてからとは比較にならないですからね。あるいは仏像の修繕でもいい。それを10歳から修行したいという子がいたら、何千年という歴史の層をいまにつなげる大切な仕事になる。
きっと歌舞伎なんて、そういう「仕事」の好例ですよね。3歳とか4歳の頃からお稽古しないと、相応の歴史性を伴った「実践」性は真に身につかないってことなんでしょう。
ちょっと話がそれました。ただ、もし僕たちが子どもの頃から、それぞれの能力や好みに応じた適切な「実践」の場を与えられていたら、ネガティヴな情念に苛(さいな)まれる人生がずいぶん減るのになあ、とは思うんですね。
みなさんも、自分が過剰なほど「正しさ」にこだわる局面、そこに反応が鈍い他の人たちを「許せない」と感じてしまうことがあったら、ちょっと落ち着いてセルフチェックしてみて欲しいんです。それは自分が傷ついた「過去」を取り戻したいだけではないのか?と。
もしそのまま暴走すると、他のみんなの「いま」や「未来」とすれ違ったままになっちゃいますから。