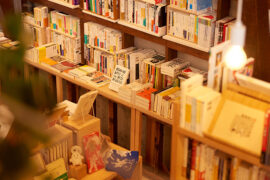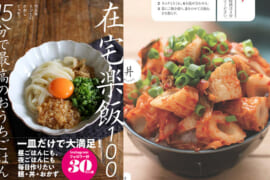誰かに理不尽な思いをさせられて、「本当に死んでほしい」と心から願ってしまうことも、年に1、2度はあるはず。精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)先生によると、そんな時に「一番いい復讐の方法は、できるだけ時間をかけてじわじわ攻めること」なんだそう。
名越流、「一番スカッとする復讐法」とは?
これまでに読んだ中で「めっちゃ怖い本」
前回「人間というものは、殺された父親のことは忘れても、奪われた財産のほうはいつまでも忘れない」というマキアヴェリの言葉を紹介しました。
僕たちはいつも、この言葉を留意していないと道を踏み外すよ、ってことを言いたい。だから逆に、課題はいかに財産(物)への執着を消していくか。その「所有」への執着を消さないと、あなたの人生は前に進めないよ、ってことを説いたのが仏教なんやろうね。
ある部分では“仏教vs.『君主論』”くらいの思想的なスケールがあるんですよ。やっぱりマキアヴェリはすごいな。深いよ。だってこの人、官僚として政治や軍事の現場で実際活躍しながら政変の時に追放処分を受けて、いったん拷問で殺されかかってるんやもんな。凄まじい人生の中で、人間のいろんな闇の本性を見てきたと思うんですよ。
僕、マキアヴェリについては一時期ね、集中して読んでいたことがあるんですけど。『君主論』は一度さら~っと読むだけでね、なんか性格が変わりそうな(笑)。人間ってこんなに汚いぞ~っていう。文庫本で本編そのものは150ページほどの短さなんですが、めっちゃ怖い本やで。
今こそマキアヴェリが必要な時代
皮肉な話ですが、いまは『君主論』を読み直すのにちょうど最適な頃かもしれません。なんせ、ドナルド・トランプが米大統領に選ばれたりする時代ですからね。実際はヒラリー・クリントンのほうが獲得票数は多かったようですが、それでも民主主義とか人権主義、平等主義などの大義名分、美しいお題目が陥りがちな生々しい現実に対する上っ面具合に皆が気づきはじめた。
自由、自由とスローガンを唱えていたら、結果、収入格差が各国共通してどんどん開いてきている。そこで忘れられた民衆の不満を背に受けて、「言いたいこと言ってやるぜ」と台頭してきたトランプが勝つ。それまでの倫理観や道徳、「こうしましょう」「これは言ってはならない」という作法を、身もふたもない本音のパワーでことごとくぶっ潰す。
ところが、主に白人の低所得者層に支持されたとされるトランプですが、実際は彼、新たなエスタブリッシュメント(既得権層・支配勢力)を作り出そうとしていることが早くも明らかになってきた。この悪循環。ますます世界は混迷の度合いを深めるしかないですよね。
その根本にある人間知というのは、このマキアヴェリのひと言で、大げさに言うとすべて言い表されているところがあると思います。トランプは『君主論』を熟読していたのではないか?というくらいに。
「奪い合い」が日常化している今の時代
だからこの人間の恐ろしい根本、自分たちの中の身もふたもない本音を、どう自覚して適切にコントロールしていくか、ということが課題になってくる。
欧米のような「オレオレ」ではない、日本の謙虚さが美徳とされるような文化の中でも、そのポーズに隠されて、こういう本音があるということ。ただ裏を返せば、日本人は本音を隠して、表に出す感情を穏やかにコントロールすることが得意だと思うんです。
人間の自我を丸出しにして暴走した時の恐ろしさ、社会的な悲惨さというのを、僕たちはひとつの知恵として、御していかないといけない。
たとえば自分をひとつ脇に置いて、ある程度の損を引き受けながら、誰かに協力してあげるとかね。その姿を見ている誰かがいて、その人の評価が上がって、その人が知らない間に出世したり、リーダーになったり。こういう自己実現の方向性があってもいい。すごく日本的な「自我」観だと思う。
状況の中に自分がいる、ということ。周りのおかげで自分が立っていられる、ということを発見していく文化。その希少な文化を伝統的に持っているのが、日本だから。
だけど現在の世界は、お金に限らず、自分の「所有」しているものに関して大きな執着を持ちすぎています。これは、倫理的な側面から言っているのではないんです。だって、所有しているものは奪われやすいでしょう。だから、執着しすぎないほうがいい。金融の世界ってそうやんか。「奪い合い」の世界ですからね。僕たちの世界は、生産する世界から、どんどん奪い合う世界に移行しているのかもしれない。
大きな戦争はずいぶん減ったけど、戦争の根本が「奪い合い」であるならば、経済が戦争になっているのが今の世だと思う。
人から奪い続ける人の末路
そして人間は、そこで激しく傷つくんです。奪われたら、ものすごく傷つく。
そうして相手から奪った人は、どれだけの禍根を残すか。
だから良質なビジネスの世界では、よくWin-Win(ウィンウィン)ってことを言いますよね。自分と相手、双方に良い結果をもたらす関係や取引を模索するということ。たとえば、どうしても相手から奪わざるをえない時には、ちゃんと理由づけするとか。別のメリットを用意するとか。
相手からある種の納得を引き出さないと、1年や2年では見えてこなくても、5年や10年のスパンでは必ずしっぺ返しが来ると思うんです。
積極的な仕返しの行為ではなくても、こちらが困っている時に助けてもらえなかったり、無視されたり、陰湿ないじめにあったり。それは充分ありうるから、アフターケアはできるだけ丁寧に、注意しなくちゃいけないってことでしょうね。
では、奪われたら、奪い返したくなる衝動は、どうすればいいのか?
それは敵討よりも怖い。
「向こうがひどいことをしたんだから」ということで、ものすごく攻撃的になる。残虐になる。ハムラビ法典の「目には目を、歯には歯を」は「受けた仕打ち以上の過度な報復はいけない」という制限法ですけど、その歯止めがなくなる。
しかしそこで強引に奪い返してしまった人は、憎しみの連鎖を生じさせてしまう。たとえば若い頃に「奪い合い」を繰り返した人は、人生の後半において禍根を残す場合が多い。
40歳も過ぎると、体力や気力がどんどん落ちてくるからね。そうすると苛烈な「戦いの世界」の中にずっといるってことは、その人の運命をすごく縮めることになってしまう。つまりたくさん奪った人は、もうその時点で人生に復讐されかかっている。
だから、もし奪い返したくなったら、それよりも「別のところ」で儲けることを考えたほうが僕は合理的だし、効率的であると思いますね。奪った相手に直接仕返しにいくと、あまりに無駄な労力、過剰なエネルギーが費やされる可能性がある。
本当に胸がスカッとする復讐とは?
では復讐はいかにすべきか?
僕の考えでは、相手の奪ったことに対し、できるだけ長いスパンで復讐することやと思います。じわじわと(笑)。しかも「奪い合い」の世界に入るんじゃなく、自分がなにかを生産することに集中する。
たとえば仕事で、誰かにコテンパンにされたと。すごい屈辱。悔しい。でも、もし相手が強大やったらどうする? まだ自分に奪い返せる実力がなかったら、どうする?
ほならね、1年後とか、そんなセコいことは言わない。本当に強い敵やったらね、20年越しとかの長い目でリベンジを考えたほうがいい。なぜそうしたほうがいいかというと、そのためにいっぱい努力するでしょう。努力すると、自分の実績が上がるでしょう。実績が上がると、協力者が増えるでしょう。そうしたら自分の相対的なステイタスが上がるんですよ。もしかしたら、ふと気づいた時には相手よりステイタスが上がっているかもしれない。
こうなれば、もうわざわざリベンジしなくてもいい。本当の意味での満足感を得られるんですよ。
イヤラシイことを言うようですけど、へりくだった態度で相手が自分の目の前にやってきたら、もう「ざまあみろ」を通り越して、きっと相手が可愛く見えてきたりしますよ(笑)。
この提案にも賛成・反対あるでしょうから、なんとなくピンとくる人だけが気に留めてくれたらいいと思います。ひどいショックを受けた時は、目の前で仕返しするのではなく、リベンジは長期間でやれ(笑)。そうしたら、そのあいだ表面的には服従していたとしても、「負けじ魂」で一生懸命に努力して、すごく人間的に成長できる。
結果的に、自分に深い満足感を得ることができる。屈辱も、奪い返したいという怒りや衝動も綺麗さっぱり消えている。それこそが本当の、深い意味での「復讐」やと思います。