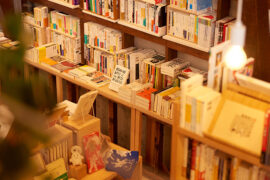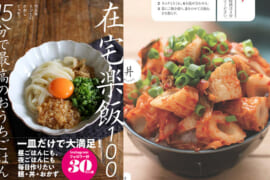こんなに働きかたが多様化している時代なのに、なぜ私たちは「誰か」が決めた仕組みの中で右往左往しなくてはいけないの?
女性が働きかたを積極的に選びとれるような環境を作りたいという願いから、AsMama(アズママ)をスタートさせた甲田恵子(こうだ・けいこ)さん。
どんな条件が揃えば、私たちは「これしかない」ではなく、「これがやりたい」で働きかたを選べるようになるのでしょうか。
【第1回】突然のクビ宣告を受けて、思ったこと
【第2回】「仕事につながらない勉強」を続けるワーママたちを見て…
「誰か、やらない?」と回り続けるも…
——職業訓練校で、子どもを預ける先がないことが社会的に負の連鎖を生み出していると分析して、ニーズの調査も行った。その結果をまずは行政の窓口に持って行ったそうですね。
甲田恵子さん(以下、甲田):はい。今は「株式会社」として、AsMamaの代表をしていますが、当時は自分の事業としてやるつもりはありませんでした。だから、「ここに課題があります」と、誰かに解決してもらおうと行政の窓口に行ったのですが……。
——たらい回しにされたとか。
甲田:そう。「子どもを預けたいなら子育て支援課や、子供保育課に持って行ってください」と。「いえいえ、仕組みが必要だと思うんです」と私が言うと、「なら、創業支援課ですね」って。検討しますというテーブルにも乗らなくて、これではダメだと思いました。
もっと、焦燥感を持って取り組んでくれる人に当たらなくてはと、次に企業家の友人に持って行きました。でも、課題やニーズの説明を聞いた直後に「いいと思うけど……。お金にならないよね」と。「その仕組みでお金が発生するタイミングは?」とここでも全然相手にされませんでした。
——もどかしい反応ですね。
甲田:今でもですが、私は儲ける仕組みよりも、水道、電気、ガスなどをフツーに使う感覚で、安心して子どもを預けられる環境を、インフラのように整備したいと思っているんです。マッチングアプリみたいに、預けたい人と預かる人を条件で組み合わせるのではなく、顔見知りの友人知人に安心して預けられるようにしたい。それを、ちょっと大根を買いにいくぐらいの料金で。だって、フツーのお母さんはシッターさんに何万円も払えませんよね。
社会貢献じゃなくてビジネスとして
——そろそろ、甲田さん自身の転職活動も再開しないといけませんし。
甲田:そう。自分のことも考えなきゃいけないけど、周りの人たちの困りごとも見える。だから、もう放っておけないと腹をくくることにしました。今は、自分のやりたいことや困っていることを、自分でなんとかする時代。私自身が解雇された経験も踏まえて、大きな会社だから大丈夫、自治体が何か用意してくれるはず、と思っているだけではダメなんだ、と。
——それはつまり……。仕事ではなく、社会貢献に力を入れていこうと?
甲田:いいえ。私自身は仕事がすごく好きなので、「仕事」としてやっていくと決めていました。でも、「起業しようと思う」と夫に相談したらさすがに動揺してました(苦笑)。
——びっくりしちゃいますよね。
甲田:大手のIT企業から、ベンチャー企業に転職する時も何も言わなかったんですけど、起業ってやっぱり“転職”とは違うんだなって。でも私としては、ニーズが明確だから「やる」と決めていました。難しいことかもしれないけれど、世の中の困りごとを解決する仕組みを作れば必ずお金にもなるし、ビジネスとして成立するという根拠のない確信もありました。
——世の中のために「いいこと」をしています!という感覚ではなかった、と。
甲田:はい。これまで築いてきた次のキャリアとしての「子育てシェア」だと考えていました。ちゃんと自分が働いた分だけの稼ぎを得るとか、世の中にインパクトを与える仕事を作るとか。慈善事業ではなく、「仕事」としてやる意義を持たなくてはいけないな、と。
「社長」になるのはすごく簡単なんですよ。登記してしまえばいいだけなので。だから、実体のない社長にならないように、会社員として働いていた以上のパフォーマンスを上げなくてはと意識していました。
創業メンバー13人中、11人が辞めて…
——動き始めてからスタートまではどうでしたか?
甲田:本格的に動き出したきっかけはブログでした。以前、「頼りたい人は頼らせてくれる人と出会えれば、やりたいことを続けられるんじゃないか」ということを書いたらたくさんのコメントがついて。その中に50人ぐらい、「一緒にやりたい」と言ってくれた人がいたんです。立ち上げ時にその人たちに声をかけて、最終的には13人でスタートすることになりました。
——だけど、そのうちの11人が離れてしまったそうですね。
甲田:これもある意味解雇に近いのかもしれませんね(苦笑)。まさか社長になって、社員に背を向けられてしまうなんて。解雇された時より辛かったかもしれません。
——原因は何だったんですか?
甲田:創業当初に思い描いていた通りにはいかなかった、ということ。思い通りにいかないのは当たり前のことですけど。ビジョンミッションを実現する活動と収益モデルを両立する施策が見つからない、という状態でした。暗中模索の中、どうしていいのかわからなくなってそのままの思いを創業メンバーに吐露すると「いまさら何を言ってるんだ!?」と愛想をつかされてしまいました。
——思いがあっても、それぞれに生活もありますからね。ビジネスの厳しい面を最初に突きつけられたんですね。それでも、諦めずに続けたのはすごい。
甲田:ゼロからの再スタートでしたね。「そもそも私たちが助けたいと思っている人たちのニーズってなんだっけ」とそこから見直して、1000人に街頭アンケートを行いました。でも、それが怪しい勧誘に見えたみたいで通報されちゃって(苦笑)。娘の保育園ママたちにもひそひそと噂されたりしました。
ママ友から陰口を叩かれた日々も
——どんな噂をされたんですか?
甲田:ある時、娘が「ママってお鍋を売っているの?」と聞くんです。「どうして?」と聞き返すと、「A君にそう聞かれた」って言うんです。どうやらその子のママが吹き込んでいたみたいで。お迎えの時に、娘が友達に手を振ると「あの子としゃべっちゃダメ」と言われたりもしました。悔しかったですね。私、何のために、誰のために頑張っているんだろうって。無力感と切なさが込み上げてきて、帰り道、自転車をこぎながら、娘に背中を向けて、前を見てボロボロ涙をこぼして泣きました。
——助けてあげたいって、その人たちのことなのに……。一番応援してもらいたい人たちにそっぽを向かれてしまうなんて、もどかしいですね。
甲田:でもね、そこで苦労していなかったら、アンケートが簡単に集まっていたら、AsMamaは成功しなかったと思うんです。苦しい思いをしたから、本当に困っている人はどこにいるんだろうと本気で探したし、リアルが見えてきた。その声があったから、協力してくれる企業や、AsMamaの掲げるビジョンに共感して、活動したいというAsMama認定サポーター、通称「ママサポーター」が集まってきたんです。
——協力者が見つかってよかったです。
甲田:人が集まり始めて、ビジネス面でもうまく回るようになりました。子育てを応援したい企業と情報がほしいママたちをつなぐことで企業から報酬をもらう収益モデルが見えてきたんです。子どもを預けたい人以外からの収入源がようやく見つかり、その後は会社も軌道に乗りました。
「誰にも奪われない資産」を持とう
——これまで、話を聞いていて思ったのは、甲田さんが本当にパワフルだということ。でも、自分を省みてもそんなに一生懸命やれるかどうか……。
甲田:頭で考えすぎないで。がむしゃらに働けるうちは働いたらいいと思いますよ。仕事って、地球の裏側にまで影響を与えるぐらい力のあるもので、人生の中で最高のチャレンジだと思うんです。頑張った分だけ、自分の中にいろんな資産がたまっていく。しかも、それは誰にも奪われないものなんですよ。
それをしっかり貯めておけば、いざ働けなくなったり、それこそ解雇されたりした時にも次の手が考えられるはず。それなのにブレーキを踏んじゃうのはもったいないですよ。失敗したって、経験に変わるだけ。それって、20代、30代の頑張り次第です。今、仕事が好きじゃなかったとしても、目の前のことに対して精一杯取り組めば、ちゃんとその先につながりますよ。
(取材・文:ウートピ編集部 安次富陽子、撮影:池田真理)