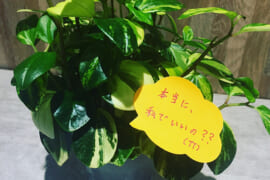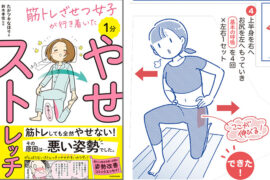「フリー編集長」と「社畜プロデューサー」というまったく異なる立場から、ウートピ編集部というチームを運営している鈴木円香(34歳)と海野優子(32歳)。
脱サラした自営業者とマジメ一筋の会社員が、「心から納得できる働きかた」を見つけるため時にはケンカも辞さず、真剣に繰り広げる日本一ちっちゃな働きかた改革が現在進行中です。
「男社会」って、結局もう終わったの?
確かに、職場の男女比率も半々に近いし、制度的にも女性が働き続けられる環境は一応整いつつある。まあ、男女平等っちゃ平等って感じはします。
でも、なんか、「女性であること」からくる居心地の悪さはなくはない。その居心地の悪さって、一体何なのでしょう?
今回は、ポーランド出身で、モルガン・スタンレーやグーグルで人事のプロとして活躍、現在は起業家兼作家のピョートル・フェリークス・グジバチさんが有識者会議のゲスト。
外資系企業の日本オフィスで長年人材育成にたずさわってきたピョートルさんに、「男社会って、ホントに終わったの?」という質問をぶつけてみました。
モヤモヤはもう古いんじゃないですか?
鈴木:こんにちは、ピョートルさん。ピョートルさんは2000年に来日して以来、十数年にわたり外資系企業の日本オフィスで人事のプロとして活躍されてきました。その視点から、今の日本のワークスタイルについて思うことをズバズバ本音で斬っていただきたいな、と。
海野P:はい、20代後半から30代のウートピ読者も、これといってすごく大きな不満を抱えているわけじゃないけれど、今の職場の環境や仕事の進めかたで日々モヤモヤしているんです。でも、原因がイマイチわからない。
ピョートル・グジバチさん(以下、ピョートル):またモヤモヤですか?
海野P:(……?)
ピョートル:ちょっと、今の日本はモヤモヤがはやりすぎじゃないですか? 女性はみんなモヤモヤしてますね(笑)。モヤモヤばっかりじゃないですか。
海野P:(苦笑)
ピョートル:正直、もうモヤモヤは古いと思いますね。モヤモヤはもうやめて、そろそろ行動しましょう。そのためのヒントになるような話を今日はできたらいいな、と思います。
鈴木&海野P:よろしくお願いします!
ハッキリ言って、まだまだ男社会です
ピョートル:「男社会」って、結局もう終わったの?という今日のテーマについて、結論からハッキリ申し上げれば、日本はまだまだ男社会ですよ。特に日系の大企業は。
鈴木:具体的にどのあたりが男社会なんですか?
ピョートル:そんなの、役員や部長クラスの顔を見ればすぐにわかりますよ。いまだにほとんどみんなバーコード頭のオッサンです(笑)。政府がいくら2020年までに女性管理職比率を30%にするといった目標を掲げて動いても、そのオッサンたちに変わる気が全然ないから、日本は依然として男社会なんです。
鈴木:この2017年においても、まだそんな古くさい構図があると。どうして変わる気がないんですか?
ピョートル:インセンティブがないからですね。今、日本の大企業の中で数十年がんばってやっと、肘掛つきのイスに座ったまま何もしなくてもいいというポジションに辿り着いた男性たちには、「女性社員とうまくやっていくメリット」がわからないんです。
だって、そのオッサンたちには、女性と一緒に働いてうまく成果を出した経験が一度もないから。だから、今さら一緒に働けって言われても……と腰が重くて動こうとしない。
鈴木:本心では「女性と一緒に働くメリットがない」と感じている?
ピョートル:そうです。それに実際にデキる女性と、オッサンが一緒に働こうとすると摩擦が起きます。おたがいに「このオッサン、訳わかんない」「このオンナ、訳わかんない」となっちゃう。
異質なものが一緒に仕事をすれば、摩擦が起きて一時的に生産性が下がるのは当たり前なんですが、日本人は摩擦が少しでも起きるとすぐに逃げ出しちゃう。本来なら、その摩擦を乗り越えて土台ができた時に生産性は一気にアップするのに、その手前で止まっちゃってるんですね。
鈴木:オッサンも女性も、結局みんな摩擦がめんどくさい?
ピョートル:はい。みんなめんどくさがっちゃって、前に進まないんです。
これ、ホントに2017年の話です!
鈴木:っていうか、バーコードのオッサンって、まだいたんですね(笑)。
ピョートル:まだまだいっぱいいますよ。
鈴木:髪型としては絶滅しつつあるけど、バーコード思考のオッサンは組織の中で確実に生存し続けている、と。
ピョートル:はい、あちこちにいます。つい最近も、とある大手企業の若手女性社員からこんな話を聞きました。社内プロジェクトとして新しいアイデアを男性の上司に提案したら、「誰もやったことがないことをやるな」と言われた、と。これ、冗談じゃなくて、ホントにあった話ですよ。
イノベーションを起こしたいとトップは口を揃えているけれど、「新しいことはやるな」というのがバーコードのオッサンの本音です。
海野P:2017年の今の話ですよね?
ピョートル:そうです、ついひと月前の話です(笑)。
日本の女性と「世界基準のリーダーシップ」
ピョートル:まあ、そんなふうに組織の中ではバーコードのオッサンがいまだに権力を握っている状態ではありますが、私は個人的に日本の女性のリーダーシップには期待しているんですよ。
海野P:というと?
ピョートル:日本の女性って、もともと本物のリーダーシップを身につけているんです。
海野P:(……ん?)
ピョートル:つまり、日本の女性は「空気を読むこと」と「人を立てること」を知っている。女性が人を立てるというと、男性にへつらう様子をイメージするかもしれませんが、そうじゃない。本物のリーダーシップは、相手が心地のいいように親切にすること。気持ちを察して気配りをすることです。
その結果、まわりが恩返しをしようとがんばって働いてくれるんです。みんな気づいてないけれど、このスキルは世界で通用するリーダーシップと完全に重なります。
鈴木:「人を立てること」と「空気を読むこと」。どちらも、ともすると古くさい日本人の特徴のように思われるけど、そうじゃない、と。
ピョートル:全然(笑)。素晴らしいリーダーシップです。日本の女性には、実はリーダーの素質がすごくあると感じています。その意味で日本の女性は世界的に見ても「最強の生きもの」だと思いますね。
鈴木:ただ、実際の組織では、そういう女性的なリーダーシップってあまり見たことがないような気がします。
ピョートル:それはありますね。役員まで上り詰めたエグゼクティブの女性について、女性たちから「男みたいで共感できない」「一緒に働きたくない」という声を聞くことはよくあります。
男性/女性を問わず、「異性っぽい部分」はある程度あった方がいいと思うんです。例えば、「共感能力が高い男性」や「空気を壊す勇気がある女性」は、どちらも異性っぽい部分を兼ね備えている人といえますが、そういう人は組織の中でリーダーシップを取りやすいですね。要はバランスです。
鈴木:女性から煙たがられる女性リーダーは、男性っぽい部分を取り入れ過ぎちゃったのかもしれませんね。
社畜としての人生をまっとうするなら…
海野P:オッサンの下で日々「仕事、つらいなあ」と思いながら働いている女性は結局どうすればいいんですか?
ピョートル:いい質問ですね。
モヤモヤで終わらせずに、行動しましょう。具体的には、転職するか、組織の中でトコトンやるか、どっちかですね。市場価値を上げたいなら、転職がオススメです。海野さんのように社畜としてトコトンやるなら……
海野P:トコトンやるなら???
ピョートル:権力を動かしなさい!
海野P:けんりょく……(ムリ!)
ピョートル:そうです、権力を動かすんです。そのためにはトコトン戦略を練ること。例えば、ボスがどういう人間で、どういう好みの持ち主で、何をすれば可愛がられるかしっかり見きわめる。
その結果「部長、お願いしま〜す♡」みたいな媚びが有効だとわかれば、それをやりきる。
海野P:やると決めたら、やりきれ、と。
ピョートル:はい。権力に戦略的に近づいて建設的に動かすんです。ただ、ここで注意が必要なのは、部長のようなポジションに就いている人が権力を握っているとは限らないことです。組織では目立たない人が黒幕として力を持っている場合も結構ある。
海野P:いるかも……。
ピョートル:そう。部長を動かしている「あいつ」。あいつに言われたら部長が動く。あいつが納得すれば部長も従う。そういう影の権力者を見つけて、近づいておくんです。とにかく、転職しないで「この会社で働き続ける」と決めたなら、トコトンやらなきゃダメです。
海野P:社畜として生きるなら、そこまでやるしかないのか……。
ピョートル:ただし、その前に転職活動だけは必ずやってください。
海野P:なぜ……?
ピョートル:自信を回復するためです。言い換えれば、「自分はモテる」と確認するため(笑)。「この会社は好きだから辞めたくないけど、仕事はつらい」という人は、たいてい自信を失っているんです。がんばってもがんばっても組織は変わらないし、新しいことも生み出せない。結果、「どうせ、自分なんか……」と思っちゃってる。
だから、その会社で今後もしっかりがんばりたいなら、まずは転職活動をやってみて、と。転職活動をすれば、他社が自分に対してどのくらいお金を出すのか、自分のスキルをどのくらい買ってくれるのかが見えてくる。そうやって自信を回復してから、今の会社でがんばればいいんです。
海野P:労働市場で「自分がモテる!」とまずは確認してから、がんばる。
ピョートル:そうそう! 動くなら、自信がある時にすべきです。
鈴木:はたして、社畜プロデューサーの海野ちゃんが権力を握る日はやってくるのでしょうか? さて、次回は「モヤモヤするばかりで何も変わらないのは、なぜ?」という問題について、引き続きピョートルさんと考えていきたいと思います。
(構成:ウートピ編集長・鈴木円香)