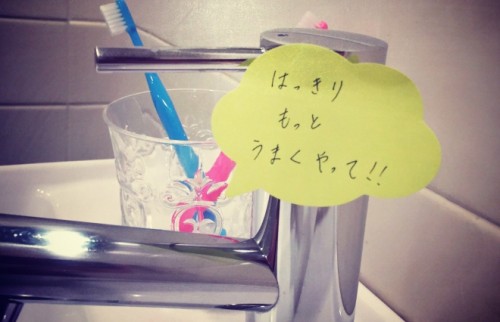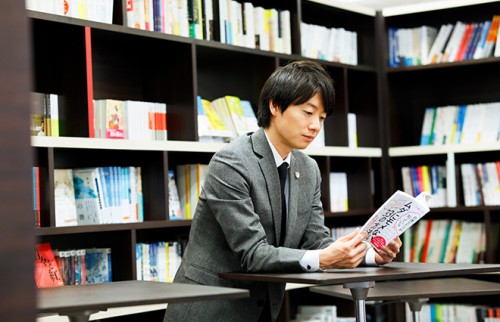社会人になると日々の仕事をこなすので精一杯で、本を読んだり勉強したりといったインプットの時間を取るのは難しいもの。
朝活や読書会、セミナーなど独学以外にもインプットの手段はたくさんありますが、学校や大学院に通うのもその一つです。大学院と言うと学部を卒業した後の進学先として通うイメージも強いですが、社会人が通いやすいように社会人に向けて門戸を開いている大学院もたくさんあります。
仕事との両立はできるの? 学費はどのくらいかかるの? 1日のスケジュールは? なぜ行こうと思ったの? 社会人になってから通うメリットって?
今年4月に開校した社会情報大学院大学に通う30代の働き女子3人に疑問をぶつけてみました。3回目のテーマは、大学院に通い始めて変わったこと(仕事編)です。
【1回目】何か新しい刺激が欲しい。仕事を続けながら大学院に通ってみたら…
【2回目】「Suicaをチャージする時間ももったいなくなる」ってどういうこと?
田中雅代さん:総合商社/(34歳)/事業投資先広報歴1年
越野佳代さん:物流会社の広報/(36歳)/広報歴5年
雨宮朋子さん:女性向け運動施設の本部広報/(32歳)/広報歴9年
仕事が楽になった
雨宮:越野さんは社命で来ているんですよね。大抜擢だね!
越野:社命できている分、じわじわとかなりのプレッシャーを感じていて。ここで学んだことをどう会社に還元しようかなと思っているんです。私は社内報を作ったり社内イベントを企画、開催したりするのがメインなこともあって、みんなみたいにここで学んだことを仕事で即実践するという場面はあまりなくて。
講義を聞いていろいろと思うところはあるけれど、それを自分の会社に当てはめる、変換することが現時点ではあまりできていないんです。それができるようになれば会社内での動き方が変わるというか自分の力で会社を変えるという大仕事にひと役買えたことになるのかなと思いながら学んでいます。
——田中さんは通ってみてどうですか?
田中:私はもともと広報関連の語彙力がゼロなので講義のインプットの量が他の方と比べて圧倒的に多いです。おかげで、会社で「この単語の意味は何だろう?」と調べる時間が少なくて済むようになりました。
社内で会話をしていても講義で学んだことに基づき、本質を理解したうえで広報用語を使うようになりました。打ち合わせにただ同席するだけでなく、自ら発言し、提案するようになりました。
越野:上司の反応は?
田中:上司も期待してるよと言ってくれていて、「これはどういうことだろうね」などと聞いてくれるようになりました。学校で学んだことをフィードバックすると会社の人も喜んでくれるし、上司と対等に話せるようになりました。
もちろん、上司は経営という視点、私はまちエネのサービスを良くするという視点で話しているのですが、一緒に会社を作っていっている、という感じです。卒業する2年後が楽しみですね。雨宮さんは?
雨宮:私は、広報歴9年目で何をと言われそうですが、広報という仕事の枠組みがだいぶわかってきました。もともと心配性で。
例えば、記者さんとのやり取りでも「原稿こないなー。明日掲載なのに」とか「あの取材の時、なんであの角度で写真撮っちゃったんだろう」とか「あの取材でなぜあの話をできなかったのか」とかいちいち心配だったり、反省していたりしたんです。でも、学校に通い始めてからどーんと構えられるようになりました。
くすぶってるくらいなら通ってみたら?
——その変化は、なぜおきたんでしょう?
雨宮:小さなことにこだわるより、もっと未来を見据えられるようになったのかな。多分今までは、会社のあるべき姿はわかっていても広報としてのあるべき姿が見えなかったんです。私は広報の責任者なのに未来像を描けていないという不安があって……。実は、学校に通ってみてわかったことがもう一つあったんです。
——それは何ですか?
雨宮:数年前、とあるPR会社との提携の案件があったんです。先方と一緒に仕事をすれば絶対うまくいくという確信はあったのに、私の知識不足ゆえに、上司を説得することができなかった。
それまでは外部の人とうまく協力すれば物事はうまく進むと思っていたんですが、自分の能力がないと、いかにすばらしい取引先や協力相手がいても、その方々と一緒に仕事をすることで生み出される価値を最大化することができないということに気づいて。
今思えば、「広報」という仕事の本質を理解してなかったんですよね。いい相手がいるから何かを一緒にできるっていうのは甘えだったのだと確信しました。そういう感じで、私の中で何かくすぶっていたのもあって、くすぶっているくらいだったら大学院に来ようと思ったんです。
社会に出て大学院に通う意味って?
——なるほど。社会人になってから学校に通うのは大学生の時とは違いますか?
越野:違いますね。学部生の時は受け身だったけど、院生の今は前のめりで学んでいて、全部吸収しているように感じます。
田中:大学生の時は何を学びたいのか、どんなことが役に立つのかわからないままアプローチしていたのですが、今は実際に抱えている問題や直面している課題がある。インプットからアプトプットまでの時間が短いのが何より魅力ですね。
雨宮:学部生の時は、身につけた知識を実践する場はなかなかないんですが、今は実践する機会があるので、そこが圧倒的に違います。社会に出て、働きはじめてから何かくすぶっていると思う方は、大学院に通うのを考えてもいいと思います。
——皆さん大学院生活を満喫されているようですね。今回はありがとうございました!