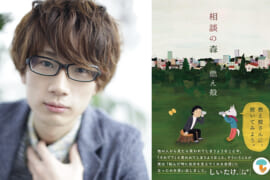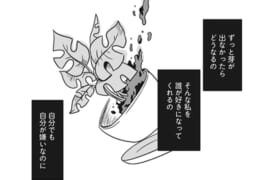同僚、上司、家族、友人……人からの評価や評判を耳にすると、「気にしないようにしよう」と思いながらも、つい心がざわついてしまうもの。精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)先生によると、「あらゆる評価は相対的なものに過ぎず、絶対的な評価というものはありえない」のだそう。
他人からの評価に惑わされずに、いつでも心をニュートラルに保ち続ける方法とは?
10億円のコートを着れたら、幸せか?
前回、イギリスの作家サキの「どんな大金持ちでも、贈り物のことになると、妙にしみったれて、出し惜しみする人がいるもんよ」という言葉を引用して、そこから「五感で感じる幸せには限界がある」という話をしました。
今回も引き続き、このテーマで話をしようと思います。
このテーマについて考えるとき、ちょっと妄想することがあるんです。
それはね、こんな妄想。昨年(2016年)亡くなったミュージシャンのプリンスは、自宅の豪邸で時々プライベートライブをやっていたらしいんです。そこのチケットを取ろうとしたら、せいぜい数百人しか入れない。とんでもない額のプレミアがついて、それを買おうとしても手が届かない。だったらね、もし自分が桁外れの大富豪だったら、何億円もギャラを出して、プリンスを自分の邸宅に呼んで演奏してもらう計画を立てるかもしれない(笑)。
でも実際、プリンスなんか家に来てもらったら、もう緊張するわ気を遣うわで、僕とかヘトヘトになると思うんですよ(笑)。洗面台とか水回りも完璧に片付けやなあかんし、楽しんで演奏してくれてるのかなとか、音響がちょっと悪かったんちゃうかな?とか。あるいは来てくれる招待客で、「あの人、呼び忘れたな……」とか。
つまりは必ずね、どんだけゴージャスな快楽を追求したつもりでも、すべてがイッツ・オールライトにはならないわけですよ。
われわれ俗世に生きている人間の喜びっていったら、一番わかりやすい例は「感覚」である。でも至上の感覚を得ようと思えば思うほど、微に入り細に入り、その状況に気を遣わねばならない。心を砕かなければならない。そうしたら、新たな苦悩が始まりません?
めっちゃ簡単に言うと、10億円のコートを着て街の中を歩くことってできないと思うんですよ。常に道行く人たちから襲われる不安と恐怖を感じるかもしれんし、ちょっとどこかに裾が引っ掛かっただけでも大損害でしょう。そこにダイヤモンドの指輪とか金のネッックレスとかじゃらじゃらつけたら、まずはもう重くて歩けないわけやから。
「お金持ちはセコい」と思ってしまう理由
やっぱり僕たちが最もコンフォタブル(快適)なものっていうのは、限りがあって。どんな大資産家でも、彼らの生活の近傍(きんぼう)、つまりそれぞれのサイズで身の回りにぐるっと描いた円状の範囲の中で生きているわけであって、それは豪勢なものだけで彩られているわけではない。その内実って彼らの収入からすれば、実はかなり慎ましいものではないかと。
そういう「生活実感」って、意外とその人の経済力とか総資産とは関係ないかもしれませんよね。
例えば資産100億円のお金持ちでも、その人の財布口から100円玉がころころと転がって、そのへんのおっちゃんがパッと拾って、ふところに入れてピュッと逃げたら、「ドロボー!」って叫ぶと思うねんな(笑)。もしかしたら1円取られても「それ、私のお金ですよ!」って怒りを顕わにするかもしれん。
ところがその光景を他人が見たら、サキの言葉のように「妙にしみったれて」と思ってしまうわけ。そう考えると、けっこうシニカルな話ですよね。「あの人、宮殿みたいな家に住んでんのに、セコいことにこだわるなあ」みたいに受け取られてしまう。
例えばちょっとした手土産とかご進物でね、もし5000円の菓子折りをいただいたとする。通常、僕だったら「こんな立派なものを!」って思いますわ。お菓子で5000円ってごっついやんなあ。でもその人が長者番付に載るようなお金持ちやったら、「あっ、この人も、みんなと同じようなもんくれはんのや」って反射的に思うかもしれない(笑)。
ほんなら、出世している人ほど大変ですよ。有名な大企業の社長さんなら、みんなが見たことないようなもの。お金は張らなくても、「えっ、こんなものが京都にあったんですか!」みたいなものをあげないと、そのネームバリューや家柄にそぐわない、みたいなことが出てくる。
あらゆる評価は相対的なもの
つまり、僕たちはそういう感覚の相対的な世界で、絶えずネガとポジとか、背景と人物とか、ふたつの関係性で物事を見ているんですね。
例えば、さわやかでイケメンの政治家がソツのないことを言ったら「さすがスマート!」と讃えられる。でも悪人顔の政治家が同じことを言ったら、「どうも胡散臭い」とかさ。貫禄のあるボスタイプの人がシンプルな格言を口にしたら「なんか重みがある」、でも頼りなさそうな男の子だと「どこかで聞いたようなこと言って。誰かのパクリじゃないの?」とか(笑)。
絶えず僕たちの感覚はネガとポジのあいだで、背景と主体のあいだで、その人を見ている。逆に言うと、僕たちが依怙贔屓(えこひいき)をなるべくしないためには、「この人を、この人の背景込みで見ているんだ」っていうことを意識として押さえとかなくちゃいけない。
これは「評価」ってことの本質に関わってくるんですよね。例えば会社の同僚でもね、この部署の課長さんはいかに評価されているか。基本的な個性の印象はだいたい共通していたとしても、評価のグラデーションは見る人や立場によっていろいろ変わってくるじゃないですか。彼は上司なのか部下なのか、それだけでも人と背景を見るアングルが変わってくる。
これはあらゆるところでそう。評価はあくまで相対的なもの。絶対的な評価というものはありえない。
端的な例で言うと、「色」の見え方ってすごく相対的ですよね。例えば日本人は桜の花が大好きでしょう。でもそれは春に咲くってこと込み、なんです。
ありえない話ですけど、もし桜が5月とか6月に咲くものだとしたら、どうなるか? 新緑の青々した中に、あんな白いふわっとした花が咲いても、主張が足りないと思われるかも。ソメイヨシノって、一輪一輪見るとすごく華麗で、綺麗な花やけど、か弱い感じがしませんか。あれ、まだ周りにほとんど新緑もない頃に、あの色の桜が咲くから人の心をつかむんやけど、もし5月に咲くんなら、もうちょっとピンクが強いほうがバランスがいいのかもしれない。
世の中はすべて相対的である、っていうのはちょっと気をつけたら誰でもわかることやけど、相対的とは何かっていえば、主体と背景との間のコントラストである。これは、ひとつ覚えておいたらいいのかなって思います。
心の中の「他人」が教えてくれること
それをちょっと頭に置いておくと、「絶対主義」にとらわれない。つまり自分の勝手なものさしで計ったり、誰かの評判を鵜呑みにしたりして、「あいつはダメなヤツや」「めっちゃいいヤツや」とか、相手を短絡的に評価することを避けられる。絶対主義とは「偏見」に近い、と思っておいたほうがいい。
絶対主義に陥るということで、一番まずいのは、違う意見を認めなくなる。自分の周囲で共有しているものと違う意見を聞いたとたん、「こいつバカじゃないの? 何もわかってない」とか思い始めてしまう。人の話をニュートラルに聞けない、ということは、例えば仕事でひとつのプロジェクトを進めるうえでも、必ず失敗する巨大な要因になりますから。
じゃあ、どうしたらええかっていうと、相談相手をもったらいい。一番身近な相談相手は、じつは自分の心の中にいる他人です。「私の中のもうひとりの私」ってやつです。
僕たちは普段、瞬間瞬間で移ろいゆく「心」っていうものにまどわされている。でも心が静かに落ち着くと、その奥に「自分の声」がある。前面化している自分の意識と、自分の心の中の声――これは「二者の対話」みたいなもんなんですよ。しかも言葉じゃない。感覚やね。
つまり内側にある感覚。こういう話をさせてもらうと、心の声は自分が辛い時に自分を救ってくれるというイメージが湧いてくるかも知れないんやけど、役に立つのは意外に違う場面だったりするんです。
例えば、いま自分は仕事が絶好調で、気持ちはイケイケドンドンだけど、どうやら勝利の感覚に上気している。どうも気分がドキドキして胸の緊張がとれない。そういえば今朝も知らず知らずのうちに他人をないがしろにして、あら捜しをしてしまっている。これは危険な落とし穴かもしれない。だから、十分注意して、ちょっと落ち着いて、寛容さを取り戻そう、とか。
これもひとつの対話でね。自分の心との対話というのはそうやって起こってくるんです。これは確実に、大きな失敗を避けるための人生の知恵として活かせます。