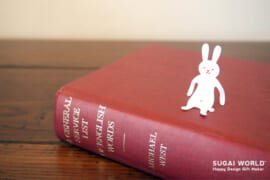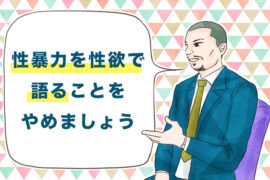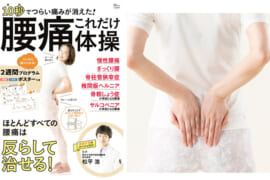「朝と夕方とで意見がコロコロ変わる」「大事なメールを見過ごす」など、トラブルメーカーの上司との接し方に悩んでいませんか?
あるいは、「発想力はバツグンなのに、いつも企画倒れになってしまう」「瞬発力はあるのに、ミスが多くて結局遠回りになる」。そんな部下や後輩に振り回されることもあるかもしれません。
一緒に働く仲間が“脳のクセ”を持っている場合、ケアレスミスや締め切りの遅延が多発し、仕事がスケジュール通りに進まないことも。仕事をゴールに導くためには、どのようにサポートしていけばよいのでしょうか?
ADHDの専門家・司馬クリニックの司馬理英子先生にお話を聞きました。
第1回:ズボラな自分に悩む貴女へ ADHD脳が原因かも
第2回:自己肯定感の低さがキャリアの妨げに…
第3回:チャンスを逃す汚部屋を変える方法
部下の仕事のチェックはルーティン化する
——職場に、困った上司や同僚って多いですよね。彼/彼女たちにも“脳のクセ”に気づいてほしい。でもやっぱり自覚していないとなかなかクリニックには行きませんよね?
司馬理英子先生(以下、司馬):そうですね。うちの場合は、私の本を読んで「ちょっと当てはまるかも?」と感じた人や、ネットで調べて来る人など、本人が自発的に来るケースが多いですね。たまに、会社の上司に勧められて来る人もいますが、本人が困っていなかったり、仕事の能力について本人と上司との間で認識のズレがあったりすると、いらしてもあまりいい結果にはならないかな。
——たとえば部下や後輩に「遅刻グセ」や「後回しにするクセ」などがあっても、「ADHD脳かもしれないよ」とは伝えない方がいいんでしょうか?
司馬:その人との関係性によりますね。たとえばすごく仲のいい部下で、「一度この本読んでみて」と言える関係ならいいですが、そうでなければパワハラと受け止められる場合もあると思います。
——それはリスクが大きい……。では、ADHDの傾向がある部下にはどう接したらいいのでしょう?
司馬:まずは「こういうやり方でやってみて」と仕事の順序を示してあげて、「チェックをしたいから1週間ごとに打ち合わせをしよう」と提案してみたらどうでしょう。抜き打ちチェックをすると、監視されているように感じてムッとする人もいますが、ルーティン化してしまえば受け入れてもらいやすいです。
——定期的にチェックすることで、トラブルの芽を摘むこともできますね。ほかに、誰でも実践できるコツはありますか。
司馬:分からないことをパッと聞ける人もいますが、中にはトラブルが起こるまで聞けないというタイプの人もいますよね。だから「なんでも聞いて」という雰囲気をつくっておくことも大事です。忘れっぽくて、同じことを何度も聞いてくることもあります。そういう状態だと、サポートする側もうんざりしてしまうので「何かのときには参考にしてね」と付せんなどに書いて貼っておいてあげるのもいいと思います。
——1つのミスを注意されたことによって、焦ってさらにミスを引き起こしてしまうタイプの場合はどうサポートすべきでしょうか。
司馬:「誰も慌てさせていないよ」「ゆっくりやってミスが少ない方がいいんだよ」と声がけしながら、焦らない練習をしていくのが一つの方法です。もしくは、「電話はとらなくていいからこれだけやってね」と、業務量を減らしてあげることでいい結果につながる場合もあります。
上司の脳のクセは「メモ」と「リマインド言葉」でコントロール
——部下ではなく、上司にADHDの傾向がみられる場合もありますが……。
司馬:上司の場合は、朝はA案がいいと言っていたのに夕方になったら変わっている……ということが起こりがちです。なので、「○日までにこういうふうに進めるということでよろしいですね? 課長にコピーをお渡しします」と確認のメールを送っておく。口頭で伝えるだけだと、悪気がなくても忘れてしまう場合があるので、文字で残しておくのがいいと思います。ただし、メールを送りましたよと言っても、「え? きてたっけ?」みたいになることもあります。送ったことも逐一確認、内容も逐一確認、を繰り返すことでトラブルを防ぎましょう。
“脳のクセ”と上手に付き合えば相乗効果も
——これまでネガティブ面を聞いてきましたが、ADHD脳ならではの強みはありますか。
司馬:「こういうやり方に従いましょう」という固定概念がない分、誰も考えないようないい企画を思いつけたり、他の人が躊躇するような仕事でも「絶対なんとかなるからやってみましょう!」と飛びつけたり。企画倒れになっちゃうこともあるけど、自由に色々なことが頭に浮かぶ柔軟さは強みですよね。
——なるほど。まわりがサポートしながら、本人も改善のための一歩を踏み出すことで、活躍の場を増やせるかもしれませんね
司馬:そうですね。私の患者さんでも、ホウ・レン・ソウを心がけるようにしたところ、周りから仕事を手伝ってもらえるようになったという人がいました。また、「忘れやすい、集中が苦手という脳のクセがあるので、サポートをお願いします」と上司に伝えたところ、「早く教えてくれればよかったのに」と言ってもらえて、職場に貢献できるようになったという人もいらっしゃいましたよ。
ADHD脳の人は覚えておけることが本当に限られています。いくら努力しても洩れてしまうことはあるし、「なんでできないの」と怒ったところで萎縮してしまうだけ。サポートする側も相手の記憶力をあまりアテにせず、脳のクセをうまく導く“仕掛け”を一緒につくってあげることが大事だと思います。
(取材・文:東谷好依、写真:青木勇太)