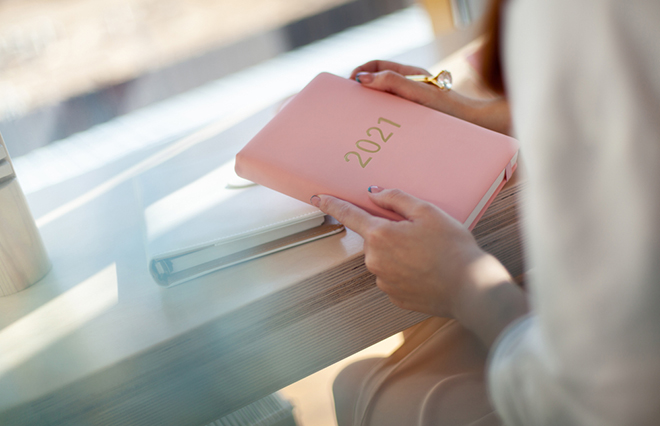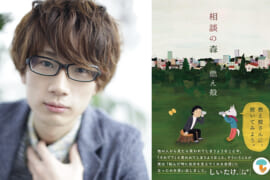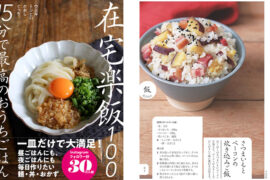こんなに頑張ってるのに、イマイチ努力が報われない。それって、貴女があまりに正しすぎるせいで、周囲の反感を買っているからかも。精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)先生によると、才能のある人ほど「嫉妬をコントロールする力」が何より大事なんだそう。
「とぼけ方」は3種類ある
前回、本当に賢い人は「とぼける技術(阿呆の真似)」を使って、上手にまわりを動かしているという話をしました。
今回は、他人を見る時に、それがどの程度の「阿呆の真似」なのかを見分けるやり方を、僕なりにお教えしましょうか(笑)。おそらく人間の「とぼけ方」って三種類くらいに大別できると思うんです。
まず「ずっととぼけている人」。そして「とぼけているけど、ちょっと何かをほのめかす人」。普段はおチャラけているけど、時折“オレって実はキレ者なんだぜ”っていう自意識を漂わせるタイプですね。最後に「上手にボケる人」。話が緊迫してきたら、ものすごく自然に、ふっと違う話題に流して場を和ませるような人です。
この中で「ほのめかす人」っていうのが一番ダメですね(笑)。三流以下の「阿呆の真似」です。自分の能力を主張したい、だけどちゃんとした自信がないから変に屈折した態度になっちゃう。ほとんどそれだけだと思います。
「ずっととぼけている人」は、最も見極め難いんです。単に臆病なのか、怠惰なのか、面倒なことに関わりたくないだけなのか。あるいは“能ある鷹は爪を隠す”的な、本当に物事をわかっている思慮深い人なのか。だからこのタイプで、肝心な時にすっと俊敏な行動ができる人は、信用していいと思いますね。
自分の内面を充実させると「ボケ力」は育つ
そして一番、シェイクスピアの言う「阿呆の真似」に近いのは「上手にボケる人」です。まあ天然ボケの場合もあると思いますけど(笑)、頭脳的にそれをやれる人は本当にかしこい。
たとえばボケをかまして、話をそらすことによって、より本質的なことを示唆しているのかもしれないですよね。その場合、むしろこっちの知性や教養の質が試されているわけですよ。僕だって随分あとになってから「あの人が言ってたことはそういう意味やったんか!」って気づくことがありますもん。お笑い芸人さんの中には、こういう道化的な知恵を持った賢者がたくさんいるんじゃないでしょうか。
もちろん大前提として、なんにも冴えたことを思いついていないのに「阿呆の真似」だけをしても仕方がないんですよ(笑)。
まずは地道な努力が大切なんです。時を惜しんで本を読む。自分の分野以外でも文化や歴史に興味を持って、出かけることを厭(いと)わない。自分とは違う意見にもよく耳を澄ます。
こうして日々、ゆっくり心と頭を練っていくと、別に外界に向けて「私はすごいんだ」的なアピールをしなくても、自分の内側が充実してくるし、自然と自信や余裕も備わってくる。
たとえば、僭越ながらこんな僕でも3ヶ月に1回くらいは「あっ、いいこと思いついた!」とほくそ笑んで、誰にも言わずにひとりでニヤニヤしていることがあるんですよ(笑)。
反論が返ってくるアイデアほど上等
ちなみに「いいこと」にも等級があるんですね。
みんながすぐに理解すること、「やってみようか」って簡単に始められること。これは最初のウケはいいんですけど、ほとんど役に立たない。せいぜい現場の混乱を整理することができるくらいで、実際的な前に進む力にはならない。
でも人間は誰でも保守的で、自分の現状を変えずにポジティブな気分になれることを喜ぶわけですよ。ただあくまで本当の名案が出てくるまでの急場しのぎ、一時の痛み止めとしては、こういうアイデアも大事なんですけどね。
対して、それを提案したら、現場の中で強い反論が返ってくること。こういうアイデアは、すごく上等な「いいこと」の可能性がある。やっぱり本当にイノベイティブな、根本的な改革につながるものは非常にアバンギャルドな意見なので、尻込みする人、拒否反応を示す人──つまり、今までの自分を否定された気持ちになる人──が多く出るわけです。それを実践するには、みんなの勇気が必要なんです。
この種の「いいこと」を会議で通すのは大変ですよね。そこで上手に「阿呆の真似」をすること──違う言葉でいうと「とぼける技術」が必要になってくる。肝心な局面でこそ突っ張らずに、明るく朗らかな態度で、みんなを冒険に駆り立てることができるかどうか。
それと同時に、たとえばまず自分のことを無条件に認めてくれる人に相談して、確実に支持を固めていく、などの根回しも重要になってくると思います。
嫉妬をコントロールする技術
今回の話は、これから仕事で、自分のアイデアをどんどん出していきたいと思っている意欲的な人には、かなりお役に立てるんじゃないでしょうか。
なぜなら頭がいい人、かしこい人って、それだけで周囲の嫉妬を生むんですよ。すぐ逆風にさらされる。
特に日本という島国、それはシェイクスピアのイギリスもそうですけど、閉鎖的な気風が大衆感情として染みついていますからね。島国根性の中では、レベル2くらいの突出度でも足を引っ張られるんですよ。
ある一定以上に有能な人が、一つの業界や集団の中で成功するか失敗するか──その8割以上を決めるポイントは、おそらく「嫉妬をいかにコントロールするか」ではないでしょうか。
これは悲しむべき現実ではあるんですよ。嫉妬が場の力を占めている分野があまりに多いせいで、本当に優秀な人材がたくさん淘汰されてしまう。
だから究極的に言うと、「阿呆の真似」っていうのは、その無益な嫉妬を回避するための技術ってことなんですね。
それを僕なりにカジュアルに言い換えると「変わり者」のススメ、ってところでしょうか。「あいつ、ちょっと変わってるんよね。だからしゃあないわ」っていう、特別枠に置かれるような「キャラ」になってしまえば、周囲も良い意味で適度な距離感を取ってくれるし、変な媚びも売らなくていい。ドロドロした出世レースにも巻き込まれずに済む。
日本には、集団のルールを破ったものを排除する「村八分」という言葉が昔からありますけど、インサイダーのままで自由を獲得するには、村六分から村四分くらいがベスト(笑)。ライト変人、マイルド変人として定着すれば、たとえば会社の中でもその実力に相応しい、正当なポジションに行ける気がするんですよね。