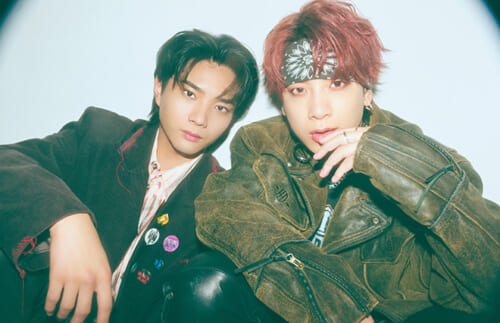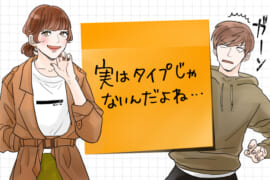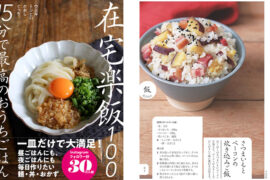5月11日に新刊『名曲の裏側:クラシック音楽家のヤバすぎる人生』(ポプラ新書)が発売されたばかりの音楽プロデューサー・渋谷ゆう子さんによると、今年はバレエの当たり年だそう。「バレエ」と聞くとなんとなく敷居が高い気がしてしまいますが、この機会にバレエ鑑賞に出掛けてみては? 「バレエに親しもう」と題して、渋谷さんにバレエの歴史や鑑賞の仕方について3回にわたって解説していただきます。
イタリアからフランスに持ち込まれたバレエ
白いタイツに美しい衣装を纏(まと)って優雅に踊る白鳥たち。チャイコフスキーの『白鳥の湖』はバレエ芸術の中で最も有名な演目です。2020年に公開されて大反響を呼んだ草彅剛さん主演の映画『ミッドナイトスワン』でも、この『白鳥の湖』が物語に大きな意味を持っていました。
『白鳥の湖』はそのタイトルだけでなく、音楽や物語の大筋もよく知られています。このバレエを中心に、これからバレエ鑑賞をはじめたいと思う方へ、その魅力や歴史をお伝えしたいと思います。
「バレエはイタリアで生まれ、フランスで成熟し、ロシアで完成した」といわれています。
ルネッサンス時代の15世紀イタリア。日本は室町時代後期、応仁の乱などがあった混乱期です。当時のイタリアは政治的にも経済的にも安定し、いくつかの都市が花開いていました。王家貴族の祝い事や一般市民の楽しみとしてさまざまなショーが催されていたような、華やかな時代です。絵画や彫刻で有名なレオナルド・ダ・ヴィンチは実は舞台監督としてもその名を知られていて、踊りを含めた数々のショーをプロデュースしていました。ダ・ヴィンチはマルチな才能があったのですね。それ以外にもたくさんの芸術家などがショーを演出し、その中心となっていた舞踏が、バレエの発祥とされています。ルネッサンス期のイタリアには才能あふれる文化人や芸術家が多出しましたが、バレエもやっぱりそこに起源があったようです。
16世紀になって、イタリアのメディチ家からフランス王アンリ2世に嫁いだカトリーヌ・ド・メディシスが、イタリアのバレエ文化をフランスにもたらします。自分が親しんでいたイタリアの芸術を持ち込むことは、単なる楽しみ、趣味だっただけでなく、イタリアの芸術水準の高さをフランスに示す意図もあったようです。結婚といえども政略的な側面がある時代の王家同士の結婚。当然といえば当然かもしれませんね。
ちなみに、現在使われているバレエ(ballet)という単語は元はフランス語です。1660年代に使われていたフランス語の「ballette」から、その前身はイタリア語の「balletto」、さらに大本はラテン語の「ballare」(踊る)からきている言葉だそう。こうして見るといかにヨーロッパでの歴史が長いかがわかります。
フランスで大きく花開いたバレエ
17世紀半ばにフランスではさらにバレエ文化が発展し、今に続く基礎が作られます。ルイ14世は無類のバレエ好きだったそうで実際に自分でもバレエを踊ったのだとか。さらにバレエ研究のための組織「王立舞踏アカデミー」を設立。これがパリ・オペラ座バレエ学校の元になり、また世界三大バレエ団のひとつ、パリ・オペラ座バレエ団の発祥でもあります。ルイ14世は残念ながら30歳ごろには踊るのをやめてしまったそうで、理由もどうやら太り過ぎだったというのだから、なんだか身につまされます。おいしいフランス料理やスイーツの発展と会食三昧がたたったわけです。ダイエットのモチベーションにはルイ14世の肖像画が効果を発揮しそうですね。
さてさて、バレエといえば白鳥に恋する王子や、妖精や人形に心奪われるお話などなど、どこか浮世離れしたロマンチックな話が多いのですが、そのきっかけは王妃マリー・アントワネットにあります。18世紀後半までバレエはキリスト教や神話をモチーフにしたものが大半で、まだあまり物語要素がありませんでした。王妃マリーがオペラ座の振り付け責任者に任命したジャン=ジョルジュ・ノヴェールは、起承転結を持つ演劇要素をバレエに取り入れ始めます。そして恋や愛をテーマにした物語には女性の存在は不可欠です。それまで男性ダンサーが中心だった舞踏から、ロマンチックな女性の踊りを見せるバレエに変わっていくのです。月光の森の中で白いチュチュ(ふわりと広がった短いスカートの衣装)を着て神秘的に踊る『ラ・シルフィード』や恋人に裏切られて亡くなったジゼルが精霊となる『ジセル』、人形に恋心を抱く『コッペリア』など今に続く傑作も生まれ、フランスでバレエの文化が発展しました。
そしてこの時期にバレエの衣装、足先や足の動きがよく見えるように短いスカートで踊ることや、硬いつま先のトゥシューズなども生まれ、バレエが成熟していきます。
振付師・プティパの元、ロシアで完成したバレエ
フランスのこうした文化芸術発展に刺激されたのが、18世紀のロシアです。ピョートル大帝の姪(めい)にあたるロシア女帝アンナ・イワーノヴナは近代化の一環として1738年に帝室バレエ学校(現ワガノワ・バレエ・アカデミー)を設立、フランスからバレエ講師を呼びました。国家政策としてバレエ発展を推し進めたロシアには、フランスなどから一流のバレエダンサーや振付師たちが公演に訪れるようになります。
このロシアにバレエ文化を決定的に大きくしたひとりの振付師が現れます。フランス生まれのマリウス・プティパです。プティパは三大バレエ、チャイコフスキーの『眠れる森の美女』の振り付けと、『白鳥の湖』を改訂して上演を成功させます。主役の男女を一緒に踊らせるアダージョ、その後に男性一人で踊るバリエーションと呼ばれる部分、女性のソロのヴァリエーション、そして再び男女一緒にラストコーダでテンポの速い華やかで高度なテクニックを披露するダンス、という構成グラン・パ・ド・ドゥを確立します。このプティパが生み出したダンスの構成は、今でもバレエの伝統として受け継がれています。バレエ鑑賞で最も楽しくエキサイティングする部分でもあります。男性が女性を抱き上げてリフトして踊ったり、高速で何度も回転したり。また高く飛んで空中で一瞬の美しい姿勢を保つ技もあります。こうして主役の男女がどんなパフォーマンスを見せるのか、観客はこの部分をひときわ楽しみにしているのです。
プティパが改訂した『白鳥の湖』にもこのグラン・パ・ド・ドゥが取り入れられています。
第一幕では王子ジークフリートが成人を迎えた祝いを宮殿で行う場面で始まります。母親から結婚相手をさっさと決めなさいと詰め寄られる王子。宮殿の庭から白鳥たちが飛んでいくところを見上げます。
第二幕では、悪魔ロットバルトに白鳥の姿になる呪いをかけられたオデット姫と王子が出会います。夜の間だけ人間に戻れるオデット姫はジークフリートに事情を切々と語ります。そして、この呪いを解くには永遠の愛が必要だと訴えるのです。王子は清楚で儚(はかな)げな姫に恋をし、結婚相手に選ぶと誓います。
しかし第三幕では、悪魔ロッドバルトがオデット姫にそっくりのオディールという娘を連れて宮殿を訪れます。王子はオディールの妖艶な誘惑にすっかり虜(とりこ)になってしまいます。様子を見に来たオデット姫のそばで、王子はオディールと結婚すると言ってしまうのです。その瞬間、宮殿は闇に包まれ、嵐の中を白鳥が飛び去るのが見えます。過ちに気がついた王子は必死でとりなそうとしますが、悪魔は聞き入れません。
そして第四幕では、闇の嵐の中、オデット姫を追ってきた王子ジークフリードに対し、オデットはもうどうすることもできないと告げます。この時、二人は残されたわずかな時間を二人で過ごします。夜明けが近づくころ、やってきた悪魔と王子は戦うのだが……という話になっています。バレエ『白鳥の湖』のラストシーンは、演出によってハッピーエンドに変えられたりもしますが、伝統的には悲劇的な最後を迎えます。
このバレエの見どころは、清楚なオデット姫と妖艶なオディールを同じダンサーが踊るところにあります。白と黒という衣装の違いだけでなく、表現される内面の差をどのようにダンサーが踊りで魅せるのかが特に楽しい一面です。
また、王子と悪魔という男性二人の踊りにも、勇敢さと清潔さ、一方は威厳ある恐怖を抱かせる様相の違いなど、見るものを飽きさせないキャラクターが揃(そろ)っています。
バレエの鑑賞に行く前には、ぜひこうしたあらすじを調べて、少し頭にいれていくとより物語が深く味わえます。
次回は、近代現代の新しいバレエの魅力と、いよいよチケットをとってバレエ鑑賞に行くときの疑問にお答えします。