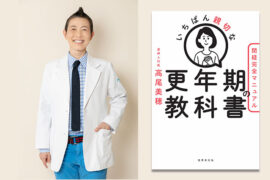説明上手な人の“口ぐせ”を真似(まね)するだけで、説明がうまくなるとっておきのフレーズ40個を厳選し、使用例とともに紹介した『得する説明 損する説明―できる人の話し方、その見逃せない法則』(SBクリエイティブ)を3月に上梓した、伊藤祐(いとう・たすく)さんにインタビュー。
「説明上手であることがなぜ大事なのか?」を伺った第1回目に引き続き、第2回目は、中間管理職やチームをまとめる立場でしんどい思いをしている人に向けてのアドバイスを伺いました。

著者の伊藤祐さん=本人提供
中間管理職がしんどい…向き・不向きはある?
——会社や組織で中堅と呼ばれる立場になると、部下や上司に説明する機会も確実に増えます。周りの30代や40代からは「ずっと現場でいたかった」「後輩や部下に対してどう指導して良いか分からない」という声もよく聞きます。管理職の向き・不向きというのはあるのでしょうか?
伊藤祐さん(以下、伊藤):管理職は一言で言うと「他人の管理」ですよね。人間関係に長けている人がなるイメージを持つ人が多いのではないでしょうか? 現場職は自分で手を動かして仕事をしている人ですね。そういう意味で、他人と一緒に何か大きなことをしたい人なのか、自分で何かを作り出したい人なのかで変わってくるかもしれないですね。
一方で、今の時代は、管理職と言っても完全に管理だけの仕事はない気がしています。もしかしたら、トラディショナルな会社はあるかもしれないですが、今はちゃんと現場のことを理解した上で、自分の力を使っていろいろなメンバーをサポートするのが管理職の役割です。より大きな仕事をしていく上では他人の協力は欠かせません。
僕自身は「社長」という肩書きですが、管理職に向いているかどうかはいまだに自分でもよく分かりません。やっぱり他人は自分が思った通りには動いてくれないし、課長や部長などと出世していくにつれて責任も重くなっていく。だから、プレッシャーを強く感じてしまって管理職を辞めたくなる気持ちはすごく分かります。
最初から「私には無理」と決めつけない
——そういう方に向けてアドバイスはありますか?
伊藤:管理職に限った話ではないですが、まずは1年なり、2年なり、「どうすればいいんだろう?」と悩みながらやってみるといいんじゃないかなと思います。その結果、「自分はやっぱり管理職に向いていない。他人と一緒に何かをやるよりも、専門職として一人でやっていくほうが向いている」と思えばそうすればいい。
ただ、生まれたばかりの赤ちゃんだって最初は何もできませんよね? 僕には生後1カ月の娘がいるのですが、今は泣くことしかできないし、ミルクを飲むことしかできません。でも、次第に立てるようになって、歩けるようになって、トイレも自分で行けるようになって、おしゃべりもできるようになって、読み書きもできるようになっていく。
ビジネスパーソンも一緒です。最初は何もできないけど、PCの電源の入れ方から学んで、社会人としてのコミュニケーションを学んで、どうしたら売上が立てられるかを学んでいく。その中の一つに、チーム成果の最大化、つまりは管理職があると考えています。そういう意味でも、最初から自分には「絶対無理」とか「できない」とか決めつけないほうがいいのではと思います。
個人的に思うのは、管理職に就いている時点で、できなくはないんですよ。いろいろなしんどさがあって、嫌になってしまってるだけだと思うので、管理職のポジションに就いて日が浅ければ「もうちょっと続けてみたら?」とは思いますね。
「基本的にはうまくいかない」前提で取り組む
——管理職やリーダーという立場になると「迷わずジャンジャン決断して指示を出していく」というイメージがありますが、「悩みながらやってみる」でいいんですね。
伊藤:僕もずっと悩んでいます。時代もどんどん変わります。今は、僕たちが上の世代から指導されてきたように、部下や後輩に対して強く言えないし、強く言ったところでやってくれるわけでもないです。「こうしたほうが、あなたにとっていいかもね」と伝えたとしても、絶対に伝わらない。だから僕は前提を変えることを意識しています。
——前提を変えるというのは?
伊藤:多くの人は「こうすればうまくいくかもしれない」「こうすれば売り上げが達成できるかもしれない」と思っているかもしれないですけれど、僕の場合は「基本的にはうまくいかない」という前提で考えています。「多分、この人はこの通りにやってくれないし、この通りには成長しないだろう」と。冷たく聞こえるかもしれないですが、たとえ「全然ダメだった」としても期待通りだし、ちょっとできたら「やった!」ってなるじゃないですか。
常にネガティブになる必要はないですけれど、「きっとうまくいく」とポジティブシンキングになり過ぎるのも危険だと感じています。9割9分はうまくいかない前提で、だからこそいろいろプランを立てたり、自分のメンタルをコントロールしていくのがちょうどいいのかなと思っています。「うまくいかないとは言っても、さすがにこれくらいはできるだろう」というレベルで心づもりしておくと気が楽になるのかなと。自分にも他人にも期待し過ぎないことが大事だと感じています。
——伊藤さんがそう考えるようになったきっかけはあるのですか?
伊藤:「うまくいく前提で考えない」というのは、経営者になってからですね。ここ2年弱くらいのことですが、経営者経験は自分にとって大きかったです。
コンサル時代は、本でも紹介した上司との出会いもあって、昇進もさせてもらって、仕事も楽しくて、結果も出せました。20代の頃は自分が頑張ればうまくいくんだと純粋に信じていました。もちろん、頑張ればうまくいくという体験は大事だし、良いことではあるのですが、経営者になってみて自分がいくら頑張ったからと言って必ずしもうまくいくとは限らないことに気付かされました。自分がいくら頑張っても、いくら考えても、いくら一生懸命やったとしても、思ったより結果が出ないことの連続です。信頼していた社員が辞めてしまうという出来事も起こります。日々起こることに「はあ……」といちいち落ち込んでいたらメンタルも体力も持たないので、いい意味で諦めるようにはなりました。
「評価」が気になるけど…まずはやるべきことに取り組む
——「期待」という話題で、周りからのプレッシャーや期待という観点ではいかがでしょうか? 上の立場にいけばいくほど期待される成果も大きくなると思うのですが……。
伊藤:期待を寄せられようが、寄せられまいが、自分ができることは100%頑張ることに尽きるのかなと。期待を寄せられていたら「評価をいただいているんだな」と思って、それはそれとして日々のことを頑張る。そして自分を評価してくれる人に対しては「最悪の場合はこういう感じになるし、うまくいけばこのくらいの結果が出ます」ということを伝えておく。「それで進めて」と言われたら、あとは毎日のスケジュールを組んで、しっかり仕事を進めていけばいいだけだと思います。
基本的には、目の前の仕事に集中すること。他人の評価って変えられないし、僕のことを好きな人もいれば、嫌いな人もいるだろうし、それは仕方ないですよね。だから、目の前にある今やるべきことをしっかりこなすことが、一番いいのかなと思っています。
(聞き手:ウートピ編集部、堀池沙知子)