人生100年時代と言われる現代ですが、長生きをしても「健康」でなければ自分の満足のいく人生を送れないかもしれません。健康を維持しながら長生きができれば、より自分らしい人生プランを考えることができるのではないでしょうか。
健康に生きるためにいま注目されていることのひとつが「睡眠」です。睡眠時間の長さだけではなく、「睡眠の質」について気にしている人も増えています。スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスで睡眠の状態をチェックしたり、運動やストレッチ、サプリメントや飲料などで睡眠の質を向上させたりしている人もいます。
「健康長寿」を目指し、最先端の研究を学ぶYoutube番組「生命科学アカデミー」では、今回、ゲストに筑波大学の柳沢正史先生をお迎えしました。同プログラムのHIROCO学長が聞き手となり、「睡眠」の奥深さについて迫ります。
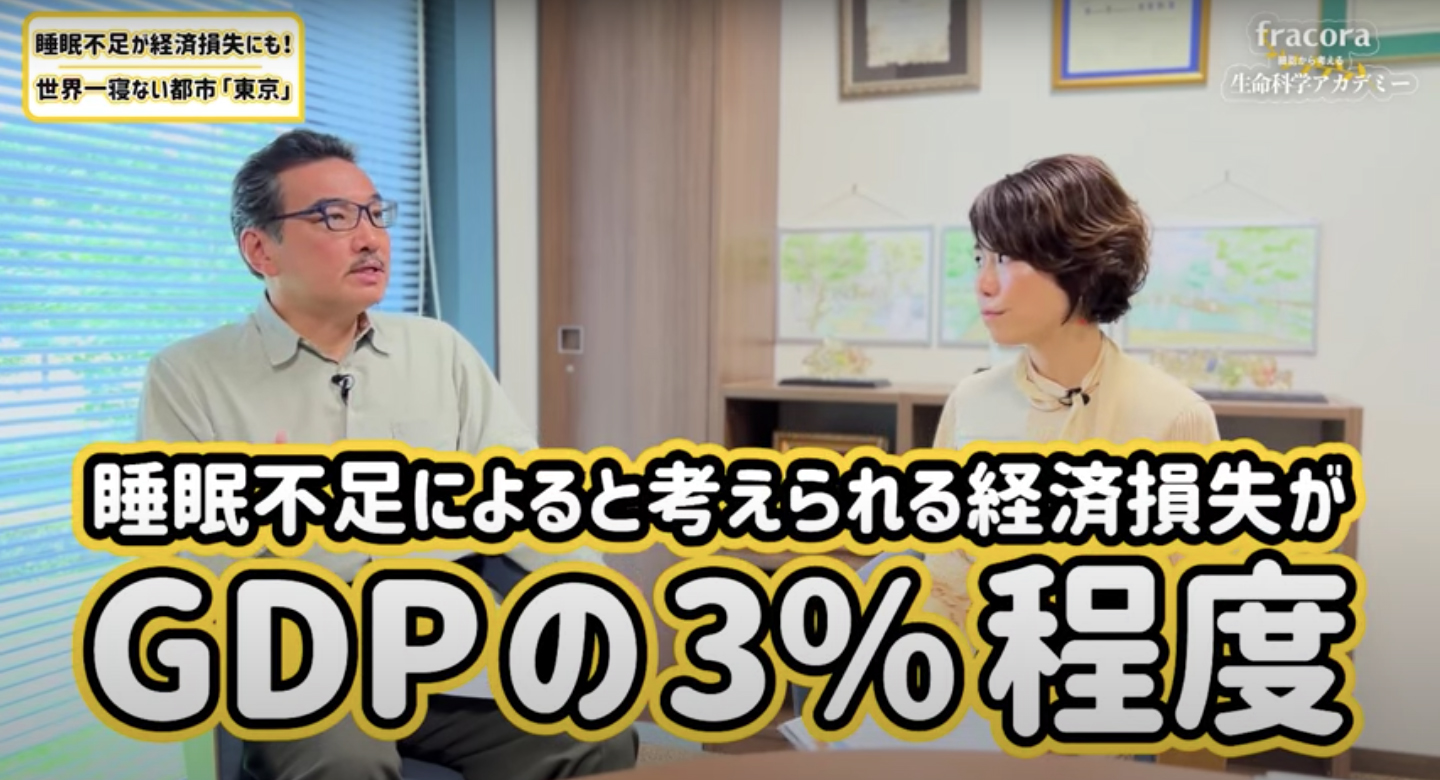
柳沢先生(左)とHIROCO学長(右)
レム睡眠とノンレム睡眠の違いって?
──「健康長寿」と「睡眠」のメカニズムについて、筑波大学の柳沢先生にお話を伺うこの連載企画。今回は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」について質問します。私たちもワードとしては聞き馴染みがあるのですが、その考え方や、実際どういう現象なのか詳しく聞かせてください。
柳沢正史先生(以下、柳沢): 我々の睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があるというのは聞いたことがあると思います。「REM」というのは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略です。レム睡眠の状態になると、目がキョロキョロ動くんですよ。それをもってREM(Rapid Eye Movement)と呼ぶわけです。
レム睡眠というのは、基本的に「夢を見る睡眠」です。ストーリーのはっきりとしたビビットな夢や、音や匂い、色のあるような夢です。
──覚えているような夢ですね。
柳沢:そうですね。その場合、ほとんどはレム睡眠で見た夢ということです。脳波をとりながら眠っていただいて、レム睡眠になったときに起こすと、9割9分が「夢を見ていた」と被験者は報告します。
ノンレム睡眠というのは、レム睡眠とはまた違った種類の睡眠です。よく世間で「レム睡眠は浅い睡眠、ノンレム睡眠は深い睡眠」と言われますが、それは誤りです。睡眠の深い浅いということ自体が、定義が難しいのですが……。
例えば、目覚まし時計などで音を出して聞かせ、どのぐらいの大きさの音になったら目が覚めるか。これを「覚醒閾値(かくせいいきち)」、聴覚に対する覚醒閾値と呼ぶのですが。それが大きい音でしか起きない程、眠りは深いと言えます。そういうやり方で眠りの深さをはかると、実はノンレム睡眠もレム睡眠もどちらも深い睡眠なんです。
──そうなんですね!
柳沢:実は、ノンレム睡眠には、第一層、第二層、第三層と3段階あって、一層は浅い睡眠、二層は中間、第三層は深い睡眠を指します。
レム睡眠というのは第二層か第三層くらいと言われていて、結構深い。レム睡眠はレム睡眠で、深い睡眠であるということです。
ノンレム睡眠の第一層というのは、まどろみのような非常に浅い状態ということになっています。
では、ノンレム睡眠とレム睡眠はどう違うんですか? ということなのですが、これを一言で説明するのはすごく難しいんです。
例えば、我々の脳の表面にある大脳皮質という、いわゆる思考したり計算したりする脳の部分があります。人間の場合、感情もほとんど大脳皮質がつかさどっていると言われています。大脳皮質にある神経細胞、脳細胞の活動のパターンが、レム、ノンレム、それぞれの睡眠で全然違うんです。レム睡眠中は、一見、大脳皮質の活動のパターンが覚醒中によく似ているんですよ。
睡眠のサイクルをおさらい!
──起きている状態に近いということでしょうか。
柳沢:大脳皮質だけを見ていると、起きているように見えます。けれど、外界とは切り離されている。知覚刺激に対して切り離されているだけではなくて、レム睡眠中は我々の体の筋肉の力が全部抜けるんですね。「レム脱力」と呼ぶのですが、基本的には動かない。完全に力が抜けている状態がレム睡眠です。
それに対して、ノンレム睡眠の大脳皮質は、多くの神経細胞が一緒に活動します。同期(シンクロナイゼーション)と呼ぶのですが、同期して活動するということになっていて……。そういうものだとしか言いようがないんですね。
コンピュータでいうところの、メンテナンスモードのような感じで。では、なぜ同期して活動して、そうすることで何をやっているんですか? と言われても、それはまだ答えられないんです。本当によく分かってないのですが、そういう違いがあるということですね。
そして、もう一つ大事なことがあります。健康な方の睡眠は、夜に寝入ると最初はノンレム睡眠になっています。まどろみから始まってガーッと深くなっていきます。そのあとに深いノンレム睡眠、いわゆる「深睡眠」が来て、それから平均60分から80分するとレム睡眠に切り替わります。
ノンレム&レム睡眠で約90分、それがワンサイクル。90分といっても結構いい加減で、一人ひとりの中でも揺らぎますし、個人差もあります。その約90分のサイクルを4回なり5回繰り返して朝になる。
夜の前半は、ノンレム睡眠の中でも深い睡眠が多く、レムは少ない。夜の後半はノンレム睡眠が浅く短くなってレム睡眠が増えてくる。それで、今わかっていることは、レム睡眠もノンレム睡眠も両方すごく大事なんですよ。一昔前に、よく「睡眠のゴールデンタイム」とか「最初の90分が大事」とか言われていましたが……。
──その言葉は聞いたことがあります。
柳沢:「最初の深いノンレム睡眠が大事」と言われていた。あれは事実であり、間違いではないのですが、じゃあレム睡眠は大事じゃないのかというと違います。ちょうどこの5年くらいの最先端の研究の領域でも「レム睡眠がすごく大事だ」ということが言われています。だから、夜の後半のレム睡眠も、結局大事なんですよ。結論を言ってしまうと、睡眠は全部大事です。
レム睡眠についてわかってきたこと
──寝ることそのものが大事ということですね。
柳沢:研究のレベルで昔から言われていた「睡眠の機能」という意味では、例えば、記憶を整理して、要らないことは忘れ、要ることはちゃんと覚えておくこと。記憶の整理整頓です。これは、主としてノンレム睡眠の間におこなわれると言われています。特に深睡眠の間ですね。
じゃあ、レム睡眠は何をやっているのか? ということについては、最近までよくわかっていませんでした。けれど最近、いろんなレム睡眠の機能がわかってきて、レム睡眠もすごく大事だと解明されてきました。極端に言ってしまうと、レム睡眠の短い人は寿命が短いという論文もあるんです。
レム睡眠にもいろいろな機能がある中で一例をあげると、レム睡眠中っていうのは脳の血流が覚醒中より増えます。脳の組織の中で、大脳皮質の血流が覚醒中より増える。何かいろいろなものを洗い流しているのではないかという説もあるのです。なのでレム睡眠を軽視するのは良くないのです。
◆まとめ
・ノンレム睡眠は深い睡眠、レム睡眠は浅い睡眠という通説は誤り!
・ノンレム睡眠もレム睡眠も、どちらも大切!
(第4回へ続く)
■動画で見る方はこちら





































