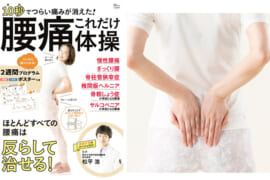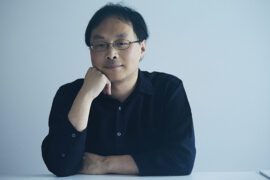この前、後輩の指導をしていたときに同僚から「もっと厳しくしたほうがいいよ」「◯◯さん(私)は優しすぎるんだよ」と言われてモヤっとしました。私もちょっと前までは「私って優しすぎるのかな?」と思い、厳しくしたこともあったのですが、キャラに似合わず空回りしてあまりいい成果が得られませんでした。しかも件の同僚は厳しくしすぎて部下や後輩が立て続けに退職してしまい、今は1人の部署で仕事をしています。
大抵の人は淡々と普通に伝えればわかってくれるので、変に厳しくするのも職場がギスギスするのでやりたくありません。そして、ここからはぼやきなのですが、「優しすぎる」と言われると、これまで私を大事に育ててくれた家族や友人など周りの人たちまでも否定をされているようでいい気はしません。
話を戻しますが、仕事においての優しさと厳しさの使い分けってあるのでしょうか?
人を育てるときに大事なこと
人材育成で最も大切なことは「仕事の楽しさを教えること」に尽きると思うのですが
仕事の何が楽しいかって、成果が出るのが楽しいんですよね。
楽しいから成果が出るわけではなく、成果が出るから楽しくなるのが仕事。
成果報酬で受けられる楽しさを求めてまた勤勉に努力を重ね、そしてまた楽しさを求めて勤勉に努力を重ねるという繰り返し。
そのサイクルの軌道に乗せてあげることが指導者の務めであり、まずは成功体験をさせてあげることが人材育成の最優先になるわけです。
基本的に仕事って学生時代の勉強に等しく、それ自体は楽しいものではありません。
楽しくないものに楽しさを覚える術(すべ)といったら、もう成果を出すしかないじゃないですか。
赤点必至のテスト用紙を目の前にして俄然(がぜん)やる気になる人なんていませんからね。
それなりの楽しさを知ってもらうためにも成果を前提にしたプログラムを組むことが必要になります。
そのためには優しいだけではダメ、かといって厳しいだけでもダメ。
硬軟織り交ぜた指導が必要となります。
失敗には寛容に、怠惰には厳しく
まず、失敗に対しては寛容になるように、しかし怠惰に対しては厳しく指導するようにしてください。
ひとつの失敗は成功への一歩ですから、それを叱責(しっせき)する必要はありません。
失敗ほど最適な教材はありませんので、その失敗から学べるように指導してあげること。
そうすればその失敗は成功体験の礎になってくれるはずです。
ただ、手抜きや不正などの怠惰な仕事には厳しく指導するように。
それを許してしまうとせっかくの成功体験が汚れてしまいます。
純度100パーセントの楽しさを味わってもらうためにも、怠惰な仕事は決して許さないように、徹底した指導を心掛けてください。
仕事のクオリティに関する部分は厳しく
そして仕事とは直接関係のないところは寛容に、しかし仕事のクオリティを決定づける細部には厳しく指導してください。
上下関係とか服装とか髪の色とか言葉遣いとか、直接仕事と関わりがないところは大目に見てあげても結構。
ただし仕事のクオリティは妥協なく厳しく求めるように、納得のいくクオリティになるまで何度でも指導してください。
もちろんこれも成功体験を経て仕事の楽しさを学んでもらうためです。
真似されて困るような仕事はしない
そして最も大切なのは、誰よりも自分自身に厳しくあることです。
指導をしてもらう側にとって、指導者の仕事は基準になります。
指導者が仕事に手を抜けば、それが指導をしてもらう側にとっての仕事の基準になってしまうのです。
人の学習能力は主に「真似(まね)ること」にありますから。
真似(まね)をされて困るような仕事は決してしないように、自分自身を厳しく管理するように心掛けてください。
社会には、優しい指導者でもなく、厳しい指導者でもない、尊敬できる指導者が必要なのですよ。