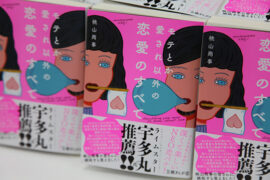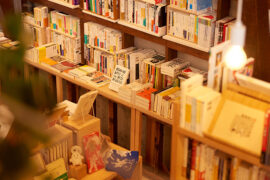2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ事件(9.11)のあと、約7000人もの被害者と遺族に補償金を分配するプロジェクトに任命され、「“命の値段”をどうやって算出するのか?」という難題に向き合った人々の姿を描いた映画『ワース 命の値段』(サラ・コランジェロ監督)の試写会とシンポジウムが中央大学多摩キャンパス(東京都八王子市)で2月に開催されました。
同映画では、日本における東日本大震災被災者に対する補償にも共通する課題を扱っているものであることから、未来を担う若者たちに、震災復興を含め、分断化されつつある日本社会で困難を抱える人たちに何ができるか、考える機会にしてほしいというねらいで行われました。
東日本大震災被災者に対する補償との共通点
最初に、マイケル・キートンさんが演じる実在の主人公であるケネス・ファインバーグ弁護士からの特別メッセージ動画が上映されました。
「9.11補償ファンドのような仕組みは、特別なもので、先例にはならないと言いましたが、今後もそのようなものができない、とは思いません。9.11テロの時に、このようなプログラムを設けることは正しかったのです。しかし、法の下の平等という視点では、公的資金から救済を受ける資格のある被害者と、そうでない被害者が区別されるのは、やはり問題でしょうが、それは私の問題というより、大学の先生や法律家などの専門家に聞いてみることができるでしょう」というファインバーグ弁護士の問いかけを起点にシンポジウムはスタートしました。
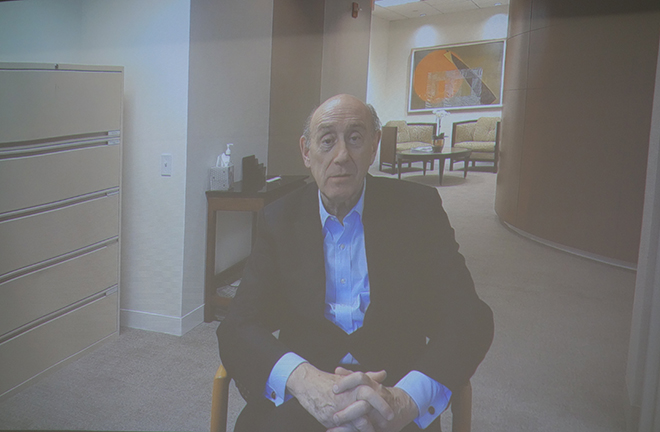
特別メッセージを寄せたケネス・ファインバーグ弁護士
東日本大震災の前から災害の被害者支援に携わってきたという宇都彰浩弁護士は「第一に、9.11の補償基金では、全被害者全員をリスト化し、連絡先も把握できたのだという前提がすごいと思った。おそらく、基金側から案内が送られたのだろう。日本では、基本は申請主義で、申請しないと行政サービスや補償が受けられない。東日本大震災のケースでも同様。新型コロナウイルスの給付金10万円を配る、という議論のときも、どうやって配るのかと問題になっていた。
第二に、訴訟によらない解決、いわゆる仲裁(裁判外紛争解決手続、ADR)の過程が興味深かった。いろんな事情を抱えている方々がいて、皆さんに納得いただける基準を作るのは難しい。映画では、個人面談をして、最終的に97%を任意で請求させたことがすごいと思った」と映画の感想を述べました。
そして「賠償金を支払うためには明確な基準が必要。だが、基準を作るということは、あてはまる人、あてはまらない人を必ず生み出す。とくに、福島の原発事故だと、帰還困難区域、避難準備区域と、いろんな線引きをした。途中から線引きも変わり、その都度、賠償金の支払い額も変わる。それにより、同じ地域でも、お金を貰えるか否か、高いか安いか、という差が生まれ、不満が渦巻き、地域コミュニティを分断していってしまった。
例えば、津波で被害を受けたが原発事故の賠償からは外れてしまった方々が、福島県のいわき市に押し寄せた。すると地域が変容してしまい、お金を貰った人、もらっていない人の分断が生まれたりもしている。なかなか元のような地域コミュニティに戻っていないのが現状。ファインバーグ先生が言っていたように、地域を分断する、社会が混乱する、被害者とそうでない人たちを分断する、ということを起こさないのがとても大事で、それが難しい。この映画を見て改めて思った」と東日本大震災被災者に対する補償にも共通する課題にも触れながら話しました。
薬害エイズ訴訟(血液製剤によって何千人もの血友病患者がHIVになり、裁判が全国で起きた)を和解でまとめた経験を持つ高取芳宏弁護士は「9.11補償のケースと類似するのは、第一に、被害者が多く、グループ訴訟が全国で起きたという、集団的な側面。第二に、被害感情や憎しみが強いという側面。第三に、天災と人災の融合であること。HIVウィルスという天災的なケースでもあり、血友病の患者を救うために点滴をしていたけれども、予見可能性が出た時に半分以上の患者が実は感染していた。裁判で決着をつけると、半分の方が救われない。包括的な救済をどうするか、という難しさが共通していると感じた」と話しました。
吉尾一朗行政書士も「映画を見て思ったのは、信頼関係を築かないと情報が出てこない、理解ができないということ。日本でも、コミュニケーションを普段からとらないといけない、申請主義に頼って仕事をしているからこその難しさがあると感じた」と感想を述べました。

シンポジウムの模様
行政からの情報が届かない人の存在
質疑応答の時間では、学生から高取弁護士に「薬害エイズ訴訟の際、国家側の弁護士として見られ第一印象が悪かったのに、その後どのようにうまく交渉を進めることができたのか?」という質問も。
高取弁護士は「当事者だけで感情のぶつかり合いが起きないように、代理人が入る。経験も必要だが、最終的にコミュニケーションをとる努力によって信頼関係を築ける。実は、第一印象が悪いほど『話を聞いてみるとちゃんと分かっている人だな』と印象が反転することもある。また、薬害エイズ訴訟では和解まで10数年かかったけれど、最後に原告団の代理人がこっそり感謝を伝えに来てくれた。弁護士は当事者の立場に立ちながらも、割り切って、法律上の責務というだけではなく、弁護士間の信頼関係を築くことが大事」と答えました。
また、行政書士の吉尾さんから宇都弁護士に「東日本大震災の時、高齢者、知的障がい者、肢体不自由の方、定住化が進む外国籍の方などは、必要な支援情報がとれない状況があったと思うが、実態はどうだったのか?」という質問が飛ぶと、宇都弁護士は「ご懸念の通り。外国籍の方々は、東日本大震災のとき、難民協会や東北大学の方々が情報を届けようとしたが、なかなか届かない状況があった。日本人でも、在宅被災者がたくさんいて、ボランティアで個別ヒアリングに伺っていた時に、高齢の方で字が読めない、若い頃から仕事に就いていて学校に通っていなかったから、という方もいて、行政からの難しい書類は読めない。日常では地域の方々が声をかけて支え合ってきたが、震災が起こり、散り散りに避難して、社会で孤立してしまった。そういう方こそ手厚く支援しないといけないが、一番助けられない状況にある。それが申請主義の最大の問題。法の下の平等とは? こんなの正義じゃないんじゃないか? と。住民基本台帳に登録している人は申請主義にしてもいいが、申請がなかった人に対しては、自ら出向いていくことが大事。自分でできる人は申請主義でいい。自分で申請できない人がたくさんいるということを知ってほしい」と訴えました。
最後に今回のシンポジウムのモデレーターを務めた中央大学法科大学院教授で弁護士の伊藤壽英さんが「地域コミュニティが分断されたという福島の現象について。ファインバーグ先生は、コミュニティの属するもっと大きなコミュニティ、つまり州や国家まで分断されてしまうというのを気にしていた。日本の状況を見ると、高齢化も含めて、社会の分断化が起こっている。その現状をどうすればいいか?『個人の利益』と『社会』の紐帯を結びつけるのが法律家の仕事だと思う」と締めくくり、シンポジウムを終えました。
映画『ワース 命の値段』は公開中。
■シンポジウム概要
全体司会:佐藤信行(中央大学法科大学院教授)
モデレーター:伊藤壽英(中央大学法科大学院教授、弁護士)
ビデオメッセージ:ケネス・ファインバーグ 弁護士
パネリスト:
宇都彰浩 弁護士(仙台弁護士会・災害復興支援特別委員会委員(元委員長))
高取芳宏 弁護士 (霞ヶ関国際法律事務所、英国仲裁人協会上級仲裁人、日本仲裁人協会常務理事)
吉尾一朗 行政書士(メルクリウス総合行政書士事務所)
阿部信一郎弁護士(霞ヶ関国際法律事務所)
参加者:中央大学学生、教職員、卒業生その他中央大学関係者 20名
主催:日本比較法研究所(中央大学)共同研究グループ
<STORY>
2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ発生後まもなく、政府が被害者と遺族を救済するための補償基金プロジェクトを立ち上げる。特別管理人を任されたのは、弁護士ケン・ファインバーグ。調停のプロを自認するファインバーグは、独自の計算式に則って個々人の補償金額を算出する方針を打ち出すが、さまざまな事情を抱える被害者遺族の喪失感や悲しみに接するうちに、いくつもの矛盾にぶち当たる。約7000人の対象者のうち80%の賛同を得ることを目標とするチームの作業は停滞する一方、プロジェクト反対派の活動は勢いづいていく。期限が刻一刻と迫るなか、苦境に立たされたファインバーグが下した大きな決断とは……。
(C) 2020 WILW Holdings LLC. All Rights Reserved.