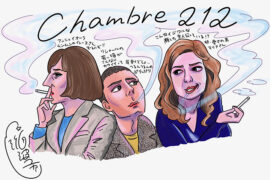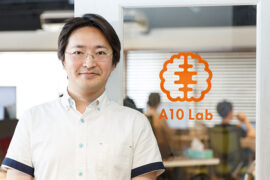魅力的な人に「人徳」があると感じたことはありませんか? この「人徳」の正体とはいったいなんなのでしょうか。
浄土真宗本願寺派 超勝寺の住職、大來尚順さんと一緒に考えていきます。
感じることはできても、掴むのが難しいもの
「人徳」ってどうしたら身に付きますか?
この問いは非常に難しいものです。というのも、私自身「人徳」を身に付けたいと思ったことがないわけではありませんが、実は真剣に考えたことはなかったからです。
「人徳」とは何かと問われれば、漠然としたイメージですが、溜まった水に手を入れてすくいあげてもこぼれ落ちてしまうようなものだと思います。つまり、感じることはできても掴むことができないものではないでしょうか?
それ故、「人徳」そのものが何なのか理解する手がかりがなかなか掴めないのですが、「人徳」と聞いて、私には恩師、元上司、先輩など思い浮かぶ人が数名います。その方々を思い描きながら、そもそも「徳」「人徳」とは何かを考え、「人徳」の身に付け方を模索してみたいと思います。
「徳」について考える
「徳」と一口に言っても、実は儒教をはじめとする中国思想的な観点、仏教的な観点、西洋哲学的な観点によるさまざまな解釈があり、どの立場で語るかで意味が異なります。
ここでは仏教的な観点から「徳」について紐解きますが、仏教においても「性質としての徳」「行としての徳」「報果としての徳」など、難しい解釈と複数の意味があります。しかし、ごく簡単に言えば「善の行いの結果が自分に戻ってくること」になるかと思います。
しかし、ここで問題となるのが「善」の意味です。仏教における「善」は、自分の都合によって判断する道徳的な意味ではありません。いかに「自分をかわいがる心」「自分を中心にして計算する心」への執着を手放すことができるかを問うのが仏教の「善」です。この定義からすると、自己への執着心が少なければ少ないほど「善」は強くなります。
つまり、自己への執着を離れ、ときには自分を犠牲にして他者のために尽くす「忘己利他」(もうこりた)というのが仏教の「徳」になるのではないかと思います。
思い浮かぶ人たちに共通する2つのこと
そして「人徳」とは、この「徳」によってその人にもたらされる品性や気質を意味することになります。
この解釈に私が「人徳」と聞いて思い浮かべる方々を重ね合わせると、ある共通項が二つ見えてきます。それは「安心」です。
一つは、どの方にも「この人なら大丈夫」「この人のためなら」という思いが自然に湧きます。よく思い出してみると、その方々は人が避けたがるようなことをやり続けていた気がします。「日々の積み重ね」により、それが周囲に「安心」を与えるものとなったのだと思います。
そして、もう一つの共通項は、その方たちは「人徳」を「人徳」と思っていないことです。つまり、私からは「人徳」と感じても、本人たちは気が付いていません。つまり、「人徳」を目的としていないのです。
「人徳」というものは、自分では把握することができないものだと思います。仮に自分の「人徳」はこれだと掴めたとします。しかし、その瞬間に「人徳」は「驕(おご)り」となってしまうでしょう。
暮らしの中で人のためになることを探してみよう
つまり、仏教の「忘己利他」という「徳」を実践し続けることがそのまま「人徳」となり、それは周りからは感じることができても、自分では掴むことも触れることもできないということです。
その上で、もし「人徳」のある人になるために今日からできる行動があるとすれば、それは何か一つでいいので、人が避けたがることを見つけ、それを続けることで実績を積み上げていくことだと思います。それが周囲に「安心」を与えるようになります。
継続は力なり。「日々の積み重ね」が知れずとあなただけの「人徳」を生み出していってくれることでしょう。
(大來尚順)