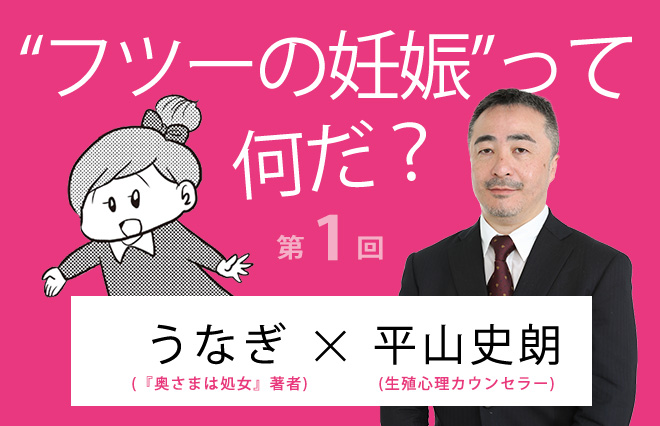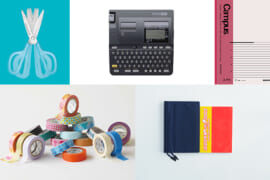「逃げる」というと「負け犬」「ダメな人」といったネガティブなイメージを持つ人は多いのではないでしょうか?
しかし、このたび『逃げ出す勇気〜自分で自分を傷つけてしまう前に〜』(角川新書)を上梓した精神科医で「ゆうメンタルクリニック」のゆうきゆう先生は「本書で言うところの『逃げ出す』は、自分の場所を見つけるための戦略的撤退」と話します。
ゆうき先生に4回にわたって話を聞きます。第3回目のテーマは「サードプレイスを作るのは大事?」です。
【第1回】「逃げる」=「負け」ではない
【第2回】しんどい親子関係からは逃げてもいい?
サードプレイスを作るのがオススメの理由
——最近は「サードプレイス」という言葉もありますが、会社や家庭以外にも自分の居場所を作るというのは大事ですか?
ゆうきゆう先生(以下、ゆうき):そうですね。いろいろな場面があるほうが、気持ちは楽でいられるので、分散していくのは手ですね。
自分の行動にしても、仕事にしても、話せる人にしても、誰か一人しか信頼できる人がいないと考えてしまうと、その人といさかいがあったときにうまくいかなくなっちゃうので、いろいろな場面、いろいろな友だち、いろいろなグループを持っておくほうがリスク分散になるのかなと思います。
——それも「逃げる」につながってきますね。「狭く深く」よりも「広く浅く」のほうがいいということですか?
ゆうき:浅くなきゃいけないということはないですが、浅くてもいろいろな人がいるほうがいいと思います。
相談するなら「境界密度が低い人」を選ぶ
——「いさかいがない人」と言えば、「相談をするなら『境界密度が低い人』を選ぶ」と書かれていましたが……。
ゆうき:「家族」や「職場の同僚」などいろいろなグループを独立した一つのグループとしたときに、グループ間でどれだけ交流があるかを表すのが「境界密度」です。
例えば、家族とサークルがあったとして、家族とサークルの友だちが実は別のグループでもつながっているというのはあまりよろしくない。家族に関する愚痴をサークルの友だちに吐いたら、めぐりめぐって家族に伝わってしまうかもしれない。そういう意味で、関係が薄いほうが、境界密度が低いほうが気持ちが楽でいられるんです。
——確かに、地元の幼なじみには会社のことでも家族のことでも恋愛のことでも恥ずかしいことでも何でも話せます。長年の親友というのもありますが、彼女が私が所属しているグループとは絶対につながってないってわかっているから。
ゆうき:そういうことです。
——バーやスナックというのもサードプレイスになりますか?
ゆうき:匿名性の集まりですね。それも大事だと思います。逆に言えば、そういう場所を持ちたくてネットにハマっちゃう人も多いのかもしれませんね。匿名的なツイッター、匿名的なSNSとか。そっちはそっちでトラブルもあるので、難しいですが。
緊張は必ずしも「悪い」とは限らない
——サードプレイスの見つけ方でオススメの方法はありますか?
ゆうき:いろいろな場所に顔を出す。「昨日はパーティー行った」とか「今日は飲み会に行く」とか、毎日何か小さいものを見つけていくことかな。
——飲み会に行く当日になるとなぜか行くのが嫌になってしまうんですが、無理して行ったほうがいいですか?
ゆうき:人間ってね「楽しみにしているものとか、期待が高いものほど、現場において緊張が強くなる」って言われているんですよ。
例えば、ジェットコースターに乗る前に、ドキドキ感や緊張が強い人ほど、実はジェットコースターに乗ったあとの興奮や楽しさは強かったという調査があって。「ジェットコースターに乗る前に緊張がない人は、ジェットコースターに乗ったあともそんなに楽しくなさそうだった」っていう。
——そうなんですね。
ゆうき:緊張感が強かったり、直前になって怖じ気づいたりするからといって、根本的に嫌だと考える必要はない。
それを乗り越えたら、すごい興奮や楽しさが待っている可能性も高いので、直前になってためらうからといってネガティブに思う必要はないよ、と。それは楽しみの裏返しである可能性があるので。
——緊張も悪いとは限らないんですね。
ゆうき:悪いとは限らないと思います。「緊張したからダメだ」って思っちゃうと、どんどん気持ちがネガティブになっちゃう。
緊張しているんだったら、緊張を否定するのではなくて、「自分はドキドキしているのではなくて、ワクワクしているんだ」といふうに自己表現を変える。すると、緊張をより楽しめてその後のパフォーマンスも高くなるという調査もあるので、言い換えをするのもオススメです。
※第4回は6月25日(月)公開です。
(取材・文:堀池沙知子)