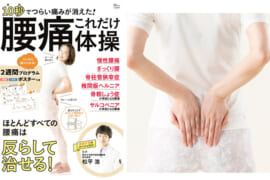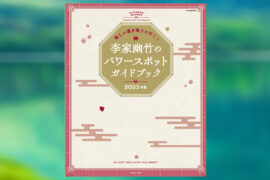6月の菅官房長官の記者会見で次々と質問をして追及し、注目を浴びた東京新聞の望月衣塑子(もちづき・いそこ)記者(42)。ニュースで望月さんが菅官房長官に厳しく追及している姿を見たことがある人も多いのではないでしょうか?
このほど、駆け出し時代からの記者の歩みをたどりながら、仕事への思いや官邸会見出席して以降の顛末についてつづった『新聞記者』(角川新書)を上梓しました。
会見で注目されたのは知っているけれど、望月さんって何者? 「空気を読まない」で、バッシングを受けても自分のスタイルを貫くのはかっこいいと思うけれど、自分にできるかといったら自信がない……など、望月さんを見ていろいろな思いを抱く読者もいるでしょう。
ウートピ読者から見れば“先輩”にあたる望月さんに話を聞きました。
<後編は…>おじさんは「忖度」するものだから…望月衣塑子記者に聞く
他人のフィールドでも自分の仕事をやっただけ
——インタビューを引き受けてくださり、ありがとうございます。望月さんと言えば、「早ければ5分で終わる定例会見で23個の質問をして会見時間が37分間に及んだ」ことで注目されました。
望月衣塑子(以下、望月):本当に思いもがけないことでした。それまで出席している政治部の記者たちは、北朝鮮からミサイルが飛んできたり、日銀の金融緩和など、さまざまなトピックスがあるから一つの問題でそんなに時間がかけられないということなんでしょうね。だからこそ会見も淡々とするし、一問一答のやり取りも意味があるのかな、と思っていました。
記事にするには政府見解のコメントが必要なときもありますから、官邸からコメントをとるのは重要だとは思うんですが、疑惑を追っている側からすると誰も満足できませんよね。疑惑があるなら明らかにしたい、当事者に疑問をぶつけたい、という社会部のマインドを官邸に持ち込んだだけです。
社会部の記者にとってはいかに関係者から真実を聞き出すかが勝負だし、基本、権力側は不都合な事実は隠しますから、言いたくないことを引き出すのが仕事なんですよ。世間では大きな話題になり、もてはやしていただいたりするのですが、それほど特異なことではないです。
——そもそも政治部と社会部の違いもよくわかっていなかったです。望月さんは社会部の記者なんですよね。初歩的な質問なんですが、政治部と社会部のちがいって何ですか?
望月:政治部は主に内閣や国会議員を取材して国の政策や外交について発信します。社会部は事件や疑惑を取材します。だから必然的に政治家や検察などの「権力」と対峙する場面も多いんです。
——なるほど。だから政治部の記者が官房長官の定例会見に行くんですね。社会部の記者が行ってもいいんですか?
望月:それは、うちの会社だからっていうのもありますね。他社の記者に聞くと、「うちだったらありえない」「政治部の縄張りだから」と言います。やはり私は政治部にご迷惑をかけているんだなとは感じますし、会見に出ることを会社が認めてくれていることには感謝しています。
社会部の記者は、朝日新聞以外は、来たくても来れないようですね。森友・加計疑惑を含めて、追及している新聞・テレビ・ネット各社の社会部記者が来ればもっと疑惑の追及は活気付くと思うんですけれどね。
——そうなんですね。他人のフィールドで発言するのはすごく勇気がいることだと思うのですが……
望月:それはあまり気にならなかったというか、当時は、質問したいという気持ちが強かったので、勇気も何もという感じでした。社会部の記者として突っ込んでいく感じとしては、あの質問の重ね方は普通ではないかとも思います。少ししつこいほうかもしれませんが……。
あれでも自分なりには、配慮しているほうなんですよ。誰も突っ込まないから浮いてしまいますが、社会部の記者だったらきっと突っ込むと思います。
——望月さんからしてみたら、自分のやるべきことをやっただけ、仕事をしただけってことなんですね。
入社後は事件記者に
——とはいえ、外から見ていると彗星のごとく望月さんという熱い思いを持った記者が現れたという感じなんですが、これまでどんなふうにキャリアを築かれてきたのか教えてください。
望月:中学のときから記者という仕事にあこがれて、大学生のときには東京の日雇い労働者が集まる山谷というところで取材とはどういうものなのか、と自分なりに取り組んだりしました。福祉政策から取りこぼれるような人を取材し、社会にそのような問題を投げかけるような仕事をしたかったんです。
母が性的被害を受け精神疾患を患った女性たちの身の回りの世話やカウンセラーをしていたこともあり、私は母ほどのメンタルの強さがないので同じ仕事はできれないけれど、こんなことが起きている社会の問題を書いて、世に伝えることならできるかもしれない、やってみたいと思っていました。
詳しくは『新聞記者』に書いたんですが、ストレートで大学に入った同世代より2年遅れで社会人になり、中日新聞社に入社しました。2000年のことでした。
——それから千葉支局に配属になっていわゆる「夜討ち朝駆け」*の日々がスタートするわけですね。
望月:はい。警察回りや支局回りの日々で大変だったけれど、やりがいもありましたし、夢中でした。ずっと事件を追っていきたいなと思いました。
*深夜と早朝に警察幹部の自宅などを訪れ、情報を集めること。
内勤を経験して気づいたこと
——2005年に整理部に異動されたんですね。異動の理由は本に書いてありますが、整理部ってどんなことをする部署なんですか?
望月:現場の記者が書いた記事に見出しをつけたり、紙面のレイアウトをしたりする仕事です。社内でする仕事です。
——完全に内勤なんですね。記者として飛び回っていた人がいきなり内勤になるのは、いかがでしたか?
望月:そうですね、最初はやる気のなさがまわりにもわかったみたいでデスクから「真面目にやれ!」と怒鳴られたこともありました。実際、現場の仕事に戻りたくて、内勤の仕事に悶々としていました。
でも、やっているうちに紙面が事件だけだと読者も疲れてしまうということがわかってきた。ちょっとした囲み記事や人物の記事、ホッとする話題や生活面もあって初めて社会が見えてくるんだなと。問題の捉え方が変わってきたんです。世の中事件だけでできているんじゃないんだ、と当たり前のことにようやく気づきました(笑)。
——その後、2年ほど整理部に勤務して、さいたま支局に赴任。1年半勤務して、その後本社社会部の記者に戻って2009年の夏にご結婚されたんですね。第一子の出産は2011年の東日本大震災の直前だった。
望月:はい。約1年間、育児休暇を取って、子守をしながら世の中が大変なことになってしまっている様子を一人の読者として見ていました。もちろん、もどかしい気持ちはありました。復帰したのは2012年4月だったんですが、経済部に配属され、経済産業省担当になりました。
子育てで仕事ができないことに悶々
——子育てしながら、ですよね。やっぱり仕事のスタイルは変わったんですか?
望月:当時の経産省は原発問題でバタバタしていて。19時から大臣について取材するぶら下がり取材が始まって、21時から有識者の勉強会が始まったりしていました。私は保育園のお迎えがありますから、始めの3分だけ大臣会見をぶら下がって、途中で帰らなくてはなりませんでした。
今、世の中で起こっていることを満足にキャッチアップして、記事で伝えられていない。子どもは急に熱が出て保育園から呼び出されることもしょっちゅうです。「今まではいろいろできたのに」と悶々としていました。
やっぱり、朝と夜も働いて日々のニュースを追っている記者には追いつけない。でもそんなときに当時の経済部の富田光部長が「日々の取材にこだわらずにテーマを絞り込んで掘り下げてみたら?」とアドバイスをしてくれたんです。デイリーのニュースではなく、調査報道を主体に置く、という大きな転換でした。目の前を覆っていた霧が晴れていくような気がしました。
その後、第二子を妊娠して、2014年4月に復帰したんですが、「武器輸出三原則」が撤廃されてっていう時期だったんです。調査報道へのアドバイスをくれた同じ上司が「武器輸出が解禁になって大事な問題だと思うけど、どこもあまり追いかけていないんだ」とヒントをくれて、私自身も関心が向いて、じっくりと追っていこうと決めたんです。
「夜討ち朝駆け」できないなら記者じゃないって思ってた
——望月さんは『武器輸出と日本企業』(角川新書)という本も書かれていますが、それはライフスタイルが変わったことで、仕事のやり方やスタイルも変わった結果だったんですね。
私もそうなんですが、今は自分の時間を自分のことに100%使えている状態だけれど、ライフスタイルが変わるかもしれないし、このままの体力でずっと働けるかどうかはわからない。そうなったときのことを考えると不安という気持ちもあります。
望月:わかります。私もそれまでは「夜討ち朝駆け」ができないなら新聞記者じゃない、と思っていました。「夜討ち朝駆けで特ダネを一面でバーンと!」がやりがいだと思っていたし(笑)、それ以外のやりがいは見つからないのではとさえ思っていましたから。でも、武器輸出の問題に取り組むようになって、そういう、とらわれからやっと逃れられるようになったんです。
変わったことといえば、一つのテーマに絞って特集記事を書くと自分の名前のクレジットも入れられるんです。
——クレジットはすべての記事に入るのではないんですか?
望月:事件記者だとネタ元との関係もあるので、おそらくあの記者が書いたんだろうなというのはわかっても、特ダネに関しては、捜査当局からのものであればあるほど、クレジットは入れられないことが多いです。
——そうなんですね。知らなかったです。
望月:特集記事だと入れられるので、「東京新聞の望月っていう記者は武器輸出を追っているんだな」とまわりにも認知されるようになります。それによってあいさつに出むいた防衛官僚に「あんな記事、書きやがって」といきなり怒られ、説教をされることもありましたが、逆に講演会に呼んでいただいたり、本も出せて、より多くの方々にこの問題を伝えることができるようになりました。人生ってわからないもんだなとつくづく思います。
——その延長線上に「森友・加計問題」問題での追及があるのですね。
※後編は12月11日に掲載します。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)