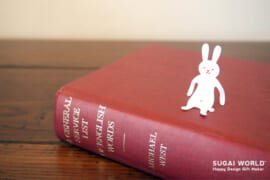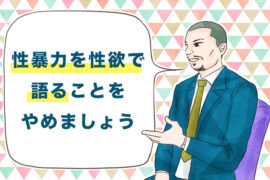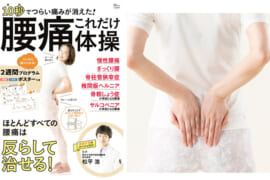仕事で感じた頭打ち感を乗り越えるため、東芝のスタートアップ制度を利用し、ネイル事業を立ち上げた千木良康子(ちぎら・やすこ)さん。
女性の困りごとを解決しようと、「電機メーカーが作るネイルチップ」という異色の組み合わせを新規事業部に提案しますが、「なぜ東芝がネイルなのか」と、社内の壁も厚かったと言います。
第2回は企画を提案することになった経緯や、立ち上げまでの壁について聞いていきます。
第1回:このままでいいの?「会社に行くのが仕事」と感じてしまう貴女へ
スタートアップの仕組みづくりにハマる
——東芝という企業の中でスタートアップというのは、手を上げやすいものですか?
千木良:アイデアを “考える”のが好きな人は多いと感じますね。新規事業開発部では最初の仕事として全社のアイデア募集サイトの立ち上げと運営を担当しました。約4000件集まり社内の関心の高さを感じましたが、よく聞くアイデアが9割9分という現実もありました……。
なかにはもちろん実現できたら面白いものもあるんですけど、「本当にできるの?」とか「じゃあ誰がやるの?」という、やはり実行上の壁が立ちはだかります。
特に初期のやわらかいアイデアはいくらでも方向転換する可能性と必要性を含んでいるもの。アイデアを提案する人が実行までできるような仕組みが必要だと思って、その後のアイデア公募制度のリニューアルではそこを意識して改善していきました。
もともと東芝にはこれとは別に、技術者視点の新規事業育成プログラムはあったんですけど、技術者だけだとやっぱり技術がメインになってしまう。それよりも、いろんな専門性をもった人がチームになって、お客さんに向きあって事業を作れるような制度に変えなければと。
アイデアを最後まで見届けるのは面白い!
——新規事業開発の裏方として仕組みを作っている中で、なぜ千木良さん自身もそれに挑戦してみようと思ったのですか?
千木良:もともと誰かを喜ばせるモノづくりをするために東芝に入ったので、自分でやりたかったのです。ただ、自分を含めた若手が新しいアイデアを提案して実行するための仕組みが無かったので、まずは仕組みを作りました。
仕組みづくりと並行して、自分が培ったデザイン関連の専門性を強みとして活かせる事業アイデアを探していました。そのきっかけとなったが、アパレル関係の新規事業プロジェクトにサービスデザイナーとしてジョインした経験です。
——どんなプロジェクトだったんですか?
千木良:美容室に仮装試着できるディスプレイを置いて、新しい髪型に合う服をすすめるというものです。その服を購入できるショップに誘導するというマーケティングビジネスでした。サービスデザインの観点から、そのデジタルサイネージ(システム)をどこに設置したら、どんな事業になるかということを、ゼロから考えて進行させていきました。
想定を大きく上回る送客率を達成した時、サービスデザインの考え方で人間の行動を変え、新しい世界を作れるのだということがわかって嬉しくて。そこにすごく可能性を感じました。
——仮装試着のプロジェクトを大きくしようとは思わなかった?
千木良:私自身がサービスデザイナーとしてやれることはすべてやり切ったと思いました。あとは、どこまで腹をくくってプラットフォームづくりに投資できるかという話であり、自分が提供できる価値が少ないように思えたのでプロジェクトリーダーに任せることにしました。
しかしその後のプロジェクトはいろいろな事情もあって私のイメージしていた方向性には進まず、自分のした決断を後悔しました。次のプロジェクトには最後まで自分が携わり切ろうと決めたのはこの時です。
3Dプリンターで今の時代にやるべきことは?
——千木良さんの強みとは?
千木良:プロダクトデザイナー時代に慣れ親しんだ3D(3次元)設計です。それと、女性の“言葉にならないような不満”を感じられること。3Dプラス女性の困りごとで、何かイノベーションを起こせないかと。その時に勝負できそうな領域として思い浮かんだのが、3Dプリンターを活用するということでした。
——3Dプリンター!
千木良:当時ビジネスシーンではかなり流行って、もてはやされていたんですけど、市場ではいまいちブレイクしていなかったんですよね。可能性はあるけど、顧客のニーズとマッチしたアプリケーションが少ないからだと思いました。だから、これで何か面白いことができるはずだって。
持論ですが、人って、自由を与えられ過ぎると何もできないんだと思うんですよ。3Dプリンターだって、何でも作れると言われていたから、何も作らないというねじれができたのだと思います。3Dプリンターを活かして、女性の困りごとを解決する。と考えた時に、爪は個人で形が違うし、これでネイルチップを作ったらいいんじゃないかな、と。
——それでネイルチップを作ろうと思ったんですね。
千木良:はい。困りごとという意味でも、お金はあるけれど、時間がないという女性も多いだろうと思っていたので、それを解決できる。チップは小さくて軽いので物流のコストも相当抑えられます。
同時期に参加した、北米のサウスバイサウスウエストというスタートアップの祭典でも、「3Dで臓器を作ります」とか「靴を作ります」「骨を作ります」と、3Dの可能性が議論されていました。
でも、3Dプリント臓器が一般的に利用可能になるまでにはそれなりの研究開発期間が必要になるとか、靴ならばもう実用化されているとか、3Dと一口に言っても、時間軸がある。その中で、ネイルならばすぐに実現可能だし、臓器よりも規制も厳しくない、何より顧客のモチベーションも高いだろうということで、これは今やるのに丁度いいと思ったんです。
あったらいいよね。でも東芝がやるの?
——これだ!って思うものが見つかるとワクワクしますよね。
千木良:はい。とてもワクワクしました。すぐに社内で話してみたのですが、第一声は「あったらすごくいいよね。でも東芝がやるの?」でした(苦笑)。東芝のブランドイメージとネイルのギャップがすごくて、違和感しかなかったみたいです。そこが最初の壁になりました。東芝だと男女比もあるし、まだまだ男性が多いわけですから、私が勢いで話しても「本当にそれは、女性が困っていることなの?」ってピンとこないんですよね。
——なるほど……。会社の意識という課題が出てきたわけですね。
千木良:はい。そこが一番大変でしたね。女性の困りごとという男性にとっての他人事に、いかに興味を持ってもらうか。どうやったらビジネスになるのかという議論に持って行くところが最初の関門でした。
次回は、壁を乗り越えるために、周りの人をどのように味方につけてきたのか、その方法を伺います。
(取材・文:ウートピ編集部・安次富陽子、写真:池田真理)