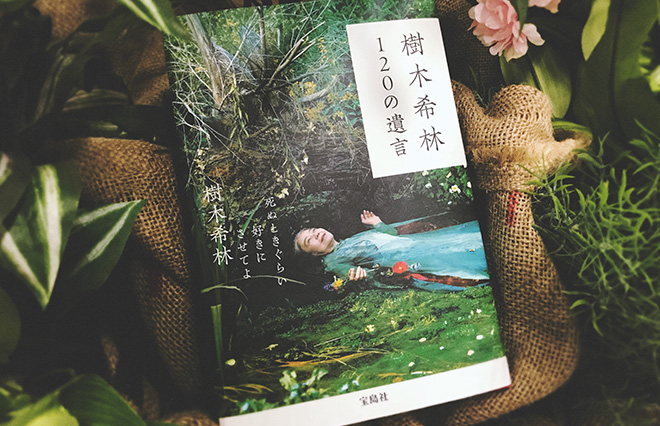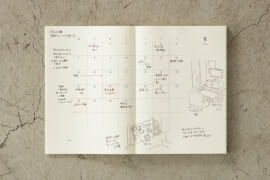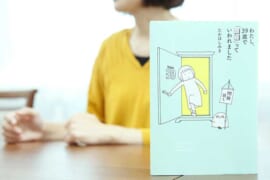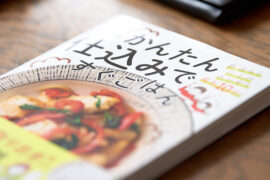今、密かにブームの伝統芸能、それが「落語」です。
落語家の生涯を描いた、雲田はるこさんの漫画『昭和元禄落語心中』(講談社)のヒットや春風亭昇々さん、三遊亭王楽さんら「イケメン落語家」の登場により、落語にハマる女性も急増しているのだそう。
社会人の嗜みとしてもにわかに注目を集めています。
でも、「落語ってなんだか難しそう」「着物を来た人が身振り手振りで話すだけなんでしょ?」と二の足を踏んでしまう人も多いはず。そこで、「笑点」の若手大喜利やラジオで引っ張りだこの女流落語家・春風亭ぴっかり☆さんに、落語初心者におすすめの落語の楽しみ方を伺いました。
【1】まずは有名落語家の落語を観よう
――初心者がまず落語に触れるなら、何を観るのがベストでしょうか?
春風亭ぴっかり☆さん(以下、ぴっかり☆):私のおすすめは、まずテレビに出演しているような有名人の落語会に足を運ぶことです。たとえば、私の師匠である春風亭小朝や「笑点」に出演されているメンバー、タレントとしてもご活躍の笑福亭鶴瓶師匠など、大御所の方々の会はハズレがないんです。そこで「落語」そのものに免疫をつけてください。
【2】お気に入りを見つけて寄席に通おう
――最初は気軽にメジャーどころの噺を聞いてみる、ということですね。
ぴっかり☆:はい。そこで落語の雰囲気になじんだら、次は寄席*に通って掘り下げてみましょう。寄席では次から次にたくさんの落語家が出てきます。華がある人や噛めば噛むほど味が出る人、本当にいろんなタイプの方がいるので、自分好みの落語家や噺(はなし)を見つけてほしいですね。
――今は動画やCDなどで、落語に触れることもできます。寄席に行くことは大事なのでしょうか?
ぴっかり☆:動画やCDから興味を持つのはもちろん悪くないんですけど、最終的には、寄席に行って生の空気感や熱量に触れてください。落語は、自分の肌で落語家の演技を感じとるのも含めて「落語」なんです。
*寄席……落語や漫才などを行う演芸場のこと。東京では、浅草や新宿、上野の寄席が有名。
【3】落語らしい落語なら「滑稽話」
――おすすめの演目はありますか?
ぴっかり☆:古典落語はどれも難しくないので、聴いていただければ入りやすいと思います。なかでも、推すなら「人情噺」*と「滑稽噺」**でしょうか。
特にわかりやすいのは「滑稽噺」。みなさんが「落語」と聞いて想像するような、落語らしい落語です。「まんじゅうこわい」や「寿限無」「目黒のさんま」などが有名ですね。私自身、滑稽噺を演じるのが得意な落語家さんの、軽い語り口や楽しい雰囲気がとても好きなので、ぜひ聴いてみてほしいです。
それでも古典落語に抵抗があるという場合は、自由な発想で創作された「新作落語」***を演じる会もありますから、そういうところに参加してみてもいいかもしれませんね。
*人情噺……町人の世界を舞台に、親子や夫婦の愛情、身分違いの恋などを描いた噺。自堕落で酒好きな亭主のために女房が嘘をつく「芝浜」や、勘当されて火消しになった若旦那が、両親の店の窮地を救う「火事息子」など、ほろりとさせられるものが多い。
とにかく飛び込んでみること!
――落語には、さまざまな種類があるんですね。
ぴっかり☆:そうですね。今はものすごい数の落語会が行われています。人それぞれ好みがありますし、自分の嗜好にあった演目に出会うためにもまずは足を運んでほしいですね。
――とにもかくにも、臆せずに寄席に飛び込んでみることが必要だと。
ぴっかり☆:はい。たとえば何か失敗しても、お客さんの前でかっこつけずにそれを披露すると笑ってもらえる。私の失敗さえ一つもムダになっていないことが嬉しくなるんですよ。そのたび、「落語ってすごいな」と実感します。ぜひ一度、寄席に来てみてください。落語って本当に面白いから!