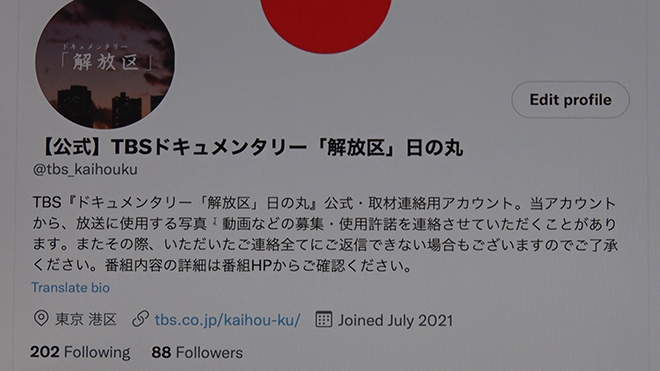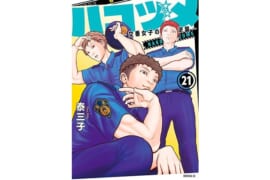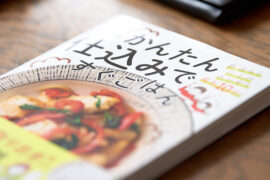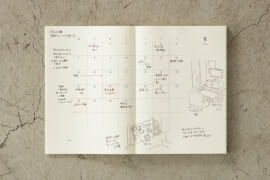「日の丸と言ったらまず何を思い浮かべますか?」
「日の丸の赤は何を意味していると思いますか?」
「あなたに外国人の友達はいますか?」
「もし戦争になったらその人と戦えますか?」
女性のインタビュアーが突然、街頭で道行く人にマイクを向ける『日の丸』。1967年2月の放送当時、物議を醸したTBSのドキュメンタリーです。そんな“問題作”が3月18日から始まる「TBSドキュメンタリー映画祭 2022」で『日の丸~それは今なのかもしれない〜』としてよみがります。
2022年と1967年の2つの時代の「日の丸」インタビューの対比を中心に「日本」の姿を浮かび上がらせていく内容で、テレビ版はTBSのドキュメンタリー枠「解放区」で2月13日に放送されました。
1967年版の『日の丸』から55年たった今、自らマイクを取って街頭に出たのは佐井大紀(さい・だいき)監督(27)。TBSの社員としてドラマ制作部に所属する佐井監督に、なぜ今「日の丸」のドキュメンタリーを作ろうと思ったのか、撮影を通して見えてきたことを聞きました。
55年後の今、『日の丸』を作った理由
——普段はドラマ制作部に所属されているということですが、今回ドキュメンタリーを、しかも「日の丸」をテーマにした作品を作った経緯を教えてください。
佐井大紀監督(以下、佐井):今回、初めてドキュメンタリーに挑戦したのですが、自分がやるとしたらこれだろうなと思って「TBSドキュメンタリー映画祭」の企画募集に応募しました。1967年放送の『日の丸』は寺山修司が構成を担当していたのですが、寺山修司のドキュメンタリーはある種フィクション的というか、劇映画的な側面もあります。自分はドラマ部にいるので、いわゆる一般的に想像されるドキュメンタリーと劇映画の間に球を投げたいと思いました。
——ドラマとの違いはありましたか?
佐井:撮ってみるとあまり大きな違いはなかったです。なにかを物語るという部分では一緒なのかなと。テレビドラマには台本がもともとありますが、リハーサルでの役者の芝居に合わせて、想定していたカット割やセリフを修正することは常です。視聴者の反応によって、脚本の流れが少し変わることもあります。まずは自分でなにかを仕込んでから、撮れたものに応じて方針を変えていくというドキュメンタリーの制作過程は、ドラマ制作と実はそれほど違わなかった、というのが今回やってみてわかったことです。
——2022年に「日の丸」について街頭インタビューをする理由について、「オリンピックや万博など当時の社会状況と似ている」と説明されていましたが、改めてこの作品を撮った理由を教えてください。
佐井:東京五輪と大阪万博に挟まれているという点では、1967年と2022年は似ていると思ったのですが、やっぱり全然違うんですよね。確かに起こっていることは近いけれど、人々が感じていることも違うし、同じオリンピック、万博と言っても状況は全然違う。
世の中の事象や社会といった大きなものというよりも、個人が「日の丸」や「日本」についてどんなふうに認識しているのか、個人がどう思っているのか? という点がこのドキュメンタリーの肝なのだと、撮り終えた時に確信しました。この街頭インタビューはいつの時代に行ったとしても、それを観た人たちは感情を動かされる。つまりこれは、人々の感情を動かすある種の装置として普遍的なものであるのだと気づきました。寺山さんが言うところの「情念の反動化への挑戦」ということでしょうか。
街頭インタビューの難しさ…「答え」より「反応」が面白い
——いきなりマイクを向けて答えてくれる人はどのくらいいるんだろうとハラハラしながら見ました。実際に何人くらいにインタビューしたのでしょうか?
佐井:街で声をかけた人は何百人という単位です。しかし、ほとんどの方に断られています。無視して立ち去ってしまうとか。すべてを撮り終わったあとに「やっぱり使わないでください」とその場で言う方も何人もいました。撮影の手順としては、インタビューをドンで行って、答えてくれた方に、インタビュー後に私の身元を明かして作品の説明をする。そして、その場で承諾書にサインもお願いしています。
——何百人……。心が折れそうになりませんでしたか?
佐井:折れました。僕自身、いきなりドンで行って、どんなリアクションされるか予想もできず……。矢継ぎ早に質問しているこちらも、相手がためらわずに矢継ぎ早に答えてくれたら、それはそれでビックリするんです。だから質問が飛んだり、噛(か)むこともたくさんありました。何回も何十回も何百回も同じ質問をしているのに、初対面の人に堂々と「日の丸は誇りだよ!」「もちろん戦えます」と反射的に答えられたら、こちらもひるんでしまう。そんなインタビューの中から、どれを使用するか選んでいったという形です。
——街頭インタビューで意識したことは?
佐井:いきなりドンで「日の丸」について質問する。そのリアクションがどのようなものか、それこそがこのドキュメンタリーの根幹、見せ場になると思ったんです。答えの内容というよりも、それがどんな反応なのか。
なのでカメラワークも、俯瞰で撮り始めて、インタビューが成立し始めたら顔に寄っていくという方針にしています。でもあまりにもインタビューを断られ続けて、しまいにはカメラマンが「一回TBSだと名乗ってから撮ってもいいんじゃないか」と言い始めたくらいです。
責任を負いたくない? SNSでスルーされたのはなぜ?
——テレビ局が「日の丸」について聞くなんて、まさにSNSで炎上しそうなテーマだと思ったのですが、ほとんど反応がなかったというのが驚きでした。
佐井:『日の丸』企画として番組公式のTwitterを開設し、視聴者から自分で撮影した日の丸の動画や画像を募集しました。その告知としてテレビCMを流し、TBSの公式アカウントでも何回かリツイートしたりもしました。少なからず、強い考え方を持った方からの反応はきてはいたのですが、それもTBSの公式広報アカウントに対してのものが多く、直接番組アカウントにリーチして来た数はごくわずかという印象がありました。
——作品の中で「日の丸の赤は“空洞”である!?」と表現されていましたが、直球の質問を投げかけると沈黙してしまうことについてどんなふうに分析されていますか?
佐井:多くの人が「日の丸とは何か?」とか、自分の主義主張や自分がどの立場に立つかというのは明言したくないのかもしれません。それを提示してしまうと、さまざまな矛盾やいろいろなことに向き合わないといけなくなるから。自分の発言に対して責任が生じてしまう。みんな自ら好んで責任は負いたくない。でも、有名なアーティストが愛国心について歌ったら、「あれは軍歌だ」と強く反応する人は必ず出てくるわけです。
「あなたは日本についてどう思うのか?」と聞かれて口ごもるのは、ある意味、みんな何かに反射させることで自分の意見を提示しているからなのかもしれません。誰かの意思表示に対しては反応したり、返答したりするけれど、自分からはストレートに表現しない。責任が発生しないようにしているのかもしれません。
そういう意味で、この作品を通して聞いているのは、「日の丸」ど真ん中について、「他の誰かがどう思ったか?」ではなく、「あなたはどう思うか?」です。SNSでの反応を受けて、自分自身もそのことに改めて気づかされました。
——Twitterで例えれば、自分からわざわざ「日の丸」についてはつぶやかないけれど、誰かが何かを発言したら返信したりリツイートしたりするという感覚なのでしょうか。それについてはどう思いますか?
佐井:そんな態度をとるのはズルい、とは思わないですね。要は、そもそもそんな簡単に答えられる事柄ではないのかなと。「国を愛するということはどういうことなのか?」「日本はどういう国なのか?」「日本人とはいったい誰のことなのか?」というものに、たった一つの答えなんてない。でも、先ほど言ったような歌が街で流れてきたら、「ちょっと嫌だ」とか「違うんじゃないの?」という意見は、誰しもがいかようにでも表明できます。そういう意味で「叩けば音がする空洞」と表現しました。
自分の名刺を登場させた理由
——佐井さんは作品の中で自身の名刺をわざわざ撮影していますが、ここでは当事者性を意識したのでしょうか?
佐井:森達也さんも言っていますが、「ドキュメンタリーは嘘をつく」ということなんですよね。ドキュメンタリーには絶対に作り手の意思というものが介在していて、それは徹底的に主観的なものだから、最初に自分の名前を出さなければいけないと思いました。
1967年版は作家の名前は前面に出さず、若い女性がインタビュアーとして登場しているのですが、作品が問題視された時にまず彼女が悪者になってしまった。世間からのバッシングは相当なもので、天井桟敷の一員だった彼女は寺山さんの元を去ったと聞いています。当時と同じ轍を踏みたくなかったので、今回は自らインタビュアーとなり自分の名前も前面に出すことにしました。
——質問する側の暴力性というのはこうしたインタビューでも常に意識しています。インタビューされるほうはインタビューする側の質問の範疇(はんちゅう)でしか答えられないわけだから……。
佐井:近代ジャーナリズムというのは、平等な目線から情報を提示するということが原則だと思うのですが、ドキュメンタリーはその真逆なんです。取材対象者と取材する人間の関係性、情念の衝突……おそらくそれがドキュメンタリーの見せ場なんですよね。情報や知識を得ることではなくて、作り手と取材を受けてくれた人との心のぶつかり合いというか……その関係性こそが面白いと思っています。
ドキュメンタリーを作るという行為は、取材対象者を自分のフィールドに巻き込んでいくという暴力的な行為なので、だからこそ、その加害性は強調するべきだと思いました。答えてくれた人たちの意見や答えが仮に視聴者や観客の意見とそぐわなくても、悪いのは僕。加害性が僕にあることを明確に提示すれば、ある種の不満やいら立ちは僕に集中させられると考えました。
——最後にどんな人に見てほしいですか?
佐井:僕は同じ世代の20代の人に見てほしいですね。ドキュメンタリーの主観性を突き詰めていくと、ある意味ドキュメンタリーとは、制作者の私小説的な側面を持つものだと思います。だからこそ、僕という個人が社会と関わっていく中で生まれたこの作品を、同時代に同じ社会で生きる同世代の人に観てもらいたい。共感する面もあれば、嫌悪感をおぼえる部分もあるかもしれない。でも必ず、何かを考えるきっかけにはなるはずです。
「TBSドキュメンタリー映画祭 2022」は3月18日(金)〜24日(木)までヒューマントラストシネマ渋谷にて開催。以降、全国順次開催。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)