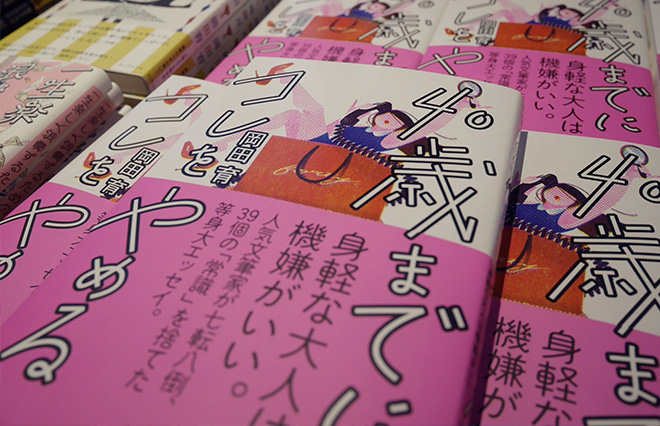慢性的な便秘で悩む読者から、「便秘を改善するには食物繊維をとろうと聞き、海藻や野菜をたくさん食べています。もう1年余り続けていますが、便秘はよくなりません。なぜでしょうか。病院で胃腸の検査をしても異常はないとのことでした」(44歳・女性・会社員)という質問が届いています。
食物繊維のとりかたについてはあれこれと言われていますが、いったいどうすればいいのでしょうか。そこで医学的な観点での回答について、京都大学大学院医学研究科・特定助教で消化器病専門医の菊池志乃医師に尋ねました。
食物繊維は腸内細菌のエサになる
——まず、食物繊維が便秘の改善に働くと言われる理由は何ですか。
菊池医師:食物繊維とは、「食べものに含まれる、ヒトの消化酵素では消化、分解されない成分」です。小腸では消化・吸収されずに、大腸まで達して排便を促すように作用します。そうした整腸作用をはじめ、血糖値の調整、コレステロール濃度の調整など体にとって有用に働き、「第6の栄養素」といわれています。
また、食物繊維は水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」に大別され、それぞれに便秘の改善に働く特性と、豊富に含む食材が異なります。まず、次のことを整理しておきましょう。
・水溶性食物繊維……文字通り、水に溶けやすくて、腸管内で粘性を持ったゲルの状態となって便の移動を促す。海藻類、コンニャク、ゴボウ、アボカド、ジャガイモ、大麦、リンゴ、ドライフルーツなど。
・不溶性食物繊維……水に溶けにくく、水分を吸収して膨らみ、便のカサを増やして腸の蠕動(ぜんどう)運動を刺激し、排泄を促す。レタス、キャベツ、ブロッコリー、サツマイモ、ホウレンソウ、タケノコ、キウイ、キノコ類、大豆など。
ただし、ひとつの食材には水溶性か不溶性かのどちらかだけではなく、両方が含まれています。例えばジャガイモ 100gあたりの含有量は水溶性が約5.4g、不溶性が約4.4gです。水溶性も不溶性も、腸内細菌のエサになり、腸内環境を整える働きがあることが明らかになっています。
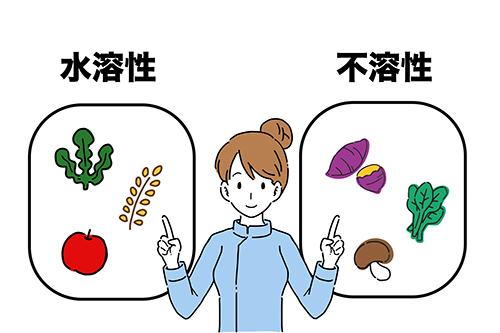
1日あたり、3~4gプラスして摂取しよう
——どちらをどうとればいいかの目安はありますか。
菊池医師:水溶性と不溶性をとる割合の理想は、「水溶性1:不溶性2」といわれます。しかしながら、毎日の食事にこの理想通りに摂取するのは難しいですね。そこで食材を選ぶコツとしては、不溶性のほうが多くの種類の食材に含まれているので、水溶性を多く含む食材を意識することがひとつの方法でしょう。
ただし、後で腸の病気の際に説明しますが、便秘の種類や原因によっては不溶性をとりすぎると逆効果の場合があるので、注意が必要です。
——冒頭の読者の場合、海藻類や野菜をたくさん食べているとのことで、水溶性をとっていると考えられます。なぜ便秘が改善しないのでしょうか。
菊池医師:そもそも慢性便秘症の「診療ガイドライン」(医学会などで医療者向きに作成された、診療の根拠や手順をまとめた指針)では、便秘の定義として、排便回数が減少したというだけでなく、便の硬さやいきみ、残便感などの不快感も含めて便を十分量かつ快適に排出できない状態としています。
ですから、例えばダイエットや、腹痛が嫌で食べる量を減らしているために排便の回数が減っている場合は、便秘と言い切れない可能性があります。また、便秘の原因によっては食物繊維が有用ではないこともあります。読者の方は検査で異常がないということなので、食物繊維以外の食事も適度にとっているという前提で話を進めます。
食物繊維が腸にとって有用であるのは、「軽症の便秘で、適切な量を毎日とっている場合」です。「日本人の食事摂取基準」(2020年版 厚生労働省)では、食物繊維の摂取目標量は、18〜64歳の男性で1日あたり21g以上、18〜64歳の女性で1日あたり18g以上、65歳以上は17g以上とされています。
例えば、リンゴ中サイズ1個やキャベツ100gに含まれる食物繊維の量は約1.8~2.0g、ゴボウ100gなら約5.7gです。自分では「たくさん食べている」と思っていても、本当に便秘の改善に適切な量を食べているかどうかが懸念されます。
また、朝に食物繊維をたくさんとっているとしても、夜は食物繊維がほとんど含まれない肉ばかりを食べているなど、栄養のバランスが偏った食事の場合も、便秘の改善は望めないでしょう。
——では、どのぐらいを、どうとればいいのでしょうか。
菊池医師:こうした基準値などから考えて、食物繊維をとる量の目標は「1日あたり、これまでより3~4gをプラスする」ことが推しょうされています。
さらに、もし適量を摂取しているとしても、腸の状態には生活習慣が大きく関わります。運動をしない、睡眠不足、ストレスフルなどではないでしょうか。食事の内容だけではなく、これらも同時に見直してみてください。
食物繊維のとりすぎで便秘が悪化するケースも
——食物繊維をとりすぎてはいけないということはあるのですか。
菊池医師:あります。便秘は医学的に多くの種類に分類されています。そのうち、大腸の機能が低下している「大腸通過遅延型」や「機能性便排出障害型」では、便が大腸にとどまる時間が長くなっています。原因には薬の副作用、直腸の筋肉や神経などの異常、ほかの病気などがありますが、これらの場合は食物繊維をいくらとってもあまり改善は望めません。
また、過敏性腸症候群のように知覚過敏があると、不溶性食物繊維のとりすぎで蠕動運動が促されて、お腹の張りや痛み、残便感を引き起こす可能性もあります。
さらに、大腸がん、クローン病、術後狭窄(きょうさく)など器質性の病気が原因の場合、腸管が狭くなっていることがあるので、不溶性食物繊維をとりすぎると腸閉塞など重篤な状態をまねく危険性もあります。
——便秘に関して、医療機関を受診したほうがいい場合を教えてください。
菊池医師:排便の状態が変わってきたとき、とくに血液が混じる、体重減少がある、便が細くなってきた場合などは早めに消化器内科を受診してください。また、読者のお悩みのように、検査で異常がなく、食物繊維を十分にとって、睡眠などの生活習慣を整えたのに便秘が続く、お腹が痛い、便秘と下痢をくり返すなどの症状があって日常生活に支障をきたすときは、先ほど挙げたように過敏性腸症候群など腸管の機能異常やほかの病気の可能性もあるので、内服薬の相談も含めて再度の受診をしましょう。
聞き手によるまとめ
食物繊維の水溶性と不溶性の特性と食材を知っておき、水溶性をとることを意識して、1日あたりはこれまでより3~4g多くとる、また便秘がひどい場合や腸の病気ではとりすぎに注意し、食事だけではなく運動や睡眠、ストレスなど生活習慣も見直そうということです。
(構成・文 藤井 空/ユンブル)