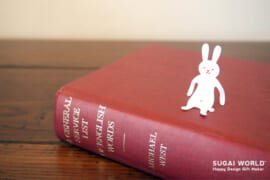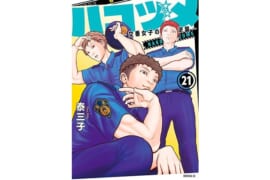健康に美しく生きるために、最先端の研究を学ぶYoutube番組「生命科学アカデミー」を配信する協和は、同番組に同志社大学生命医科学部の米井嘉一教授を招き、「良いAGEsと悪いAGEs!」ほか全5回を配信。米井先生に、老化の原因となる、体のサビ「酸化」と体の黄ばみ「糖化」が起こるメカニズムと対策法についてたっぷりとお話しいただきました。
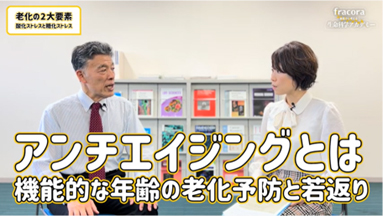
米井先生(左)と、聞き手で生命科学アカデミー学長のHIROCOさん(右)
※本記事はYouTubeチャンネル「生命科学アカデミー」で配信された内容を、ウートピ編集部で再編集したものです。
体のサビ=酸化、黄ばみ=糖化
——人類史上最大の敵と言われている「体のサビと黄ばみ」について教えてください。
米井嘉一先生(以下、米井):まず、サビについてですが、すべての生き物が何億年前から、人類だと何十万年前から、サビ=酸化ストレスと闘ってきたんですね。
——自分の体がですか?
米井:はい。紫外線による酸化や有害物質による酸化と日々の生活の中で闘ってきたことで、体の中にも酸化に対抗する仕組みができています。特に人類はほかの動物と比べると、抗酸化システムが発達しています。
酸化はフリーラジカル(活性酸素)が原因になることが多いのですが、フリーラジカルを消去する酵素もできているし、その活性も強い。さらにはビタミンやカテキンなどの抗酸化物質を食べ物からどんどんとっている。体内でも作るし、食品からも摂取する。対抗の仕方がわかっているんです。
一方、黄ばみ=糖化ストレスは、戦後の混乱期まではほとんどなかったものです。そのころと今と何が違うかというと、やっぱり身体活動量が違いますよね。便利になったぶん、体を動かしていません。それらを詳しく解説した本を読むと、20%、少なく見積もっても10%は低下していると考えられます。
身体活動量は減ったものの、胃袋の大きさは変わっていません。ただ、糖化の原因となる炭水化物の食べ方は変わりました。早食いだったり、忙しいから朝食は食べなかったり。ほかにも、睡眠不足やストレスなど、いろんな原因で食後高血糖(血糖スパイク)を起こしやすくなりました。つまり、糖化による体の変化が起きやすい状態になっています。
脂肪は自分の仲間を増やしたがる
——糖質のほかにも、脂肪の酸化も原因になるそうですが……。
米井:脂肪といっても、食品中の脂肪と体脂肪がありますけど、体脂肪の話をしますね。体脂肪というのは、実はもともと人間の味方です。
皮下脂肪は寒さから体を守りますし、エネルギーを蓄えてくれる。
そして、脂肪からは、がん細胞をやっつける物質などいろいろな物質が出ます。
また、脂肪自体が酸化して、大事なタンパク質や遺伝子を酸化から守ってくれる、抗酸化作用ももっています。それから、出血したときには血液をとめてくれます。
また、脂肪はレプチンというホルモンを出すのですが、これは女性の卵巣や子宮を成熟させる作用があります。だから、特に成長期の女性は、体脂肪を減らしすぎるダイエットをしてはダメです。体脂肪率18%は切っちゃダメ、脂肪は必要です。
だからといって、体脂肪率が30%を超えると肥満です。30%を超えると弊害が出てきます。
——30%を超えるとどのような弊害が?
米井:分泌するいろいろな成分のバランスが狂ってきます。血栓を起こしやすい成分が分泌されたり、インスリンが効きにくくなって血糖値が上がりやすくなったり。
もっと怖いのは、脂肪細胞というのは、自分の仲間を増やしたがるんです。つまり、もっと脂肪をとりなさい、運動はするな、そういう命令を出すんですね。
——運動しなかったのは自分のせいじゃなくて、脂肪細胞のせいだったんですね。
米井:そうなんですよ。脂肪が脂肪を欲する。たぶん、脳にも作用するんです。アルコール依存症やニコチン依存症と同じところに作用する、動物性脂肪依存症というのがあります。
——先生の研究だと、体脂肪率が30%超えるとその可能性が増えてきてしまうと。だからといって18%は切っちゃいけない。あまり神経質にはならずに、美味しいものを美味しく、ちょうどいいバランスでとって、何事もほどほどに。次回は糖化ストレスを減らす食事法についてお聞きします。
(第3回へ続く)
■動画で見る方はこちら