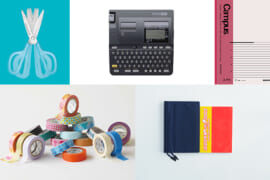過敏性腸症候群(IBS)の便秘型で悩む読者の声が複数届いています。そこで、『慢性便秘症 診療ガイドライン2017』作成委員会委員長であり、消化器内科専門医・指導医、『胃は歳をとらない』(集英社)という著書が話題の三輪洋人(みわ・ひろと)医師に連載にてお話しを聞いています。
前回・第1回では、過敏性腸症候群は便の種類によって「便秘型」、「下痢型」、便秘と下痢の「混合型」、「分類不能型」に分けられること、中でも「便秘型」の症状や特徴について 詳しく聞きました。今回はその原因について尋ねます。
過敏性腸症候群「便秘型」の原因はストレス
過敏性腸症候群といえば下痢の症状だとばかり思っていましたが、そうではなく、20~40歳の女性には便秘型が多く、それも下痢型のようにおなかの痛みを伴うケースも多いとのことでした。では、便秘型の原因とは何なのでしょうか。三輪医師は次のように話します。
「主な原因はストレスだと考えられています。便を排出するとき、腸は収縮して、腸が刺激を感じとる知覚機能が働きます。こうした動きは、脳と腸の情報交換によってコントロールされています。これを『脳腸相関』といいます。
しかしストレスがあると、ストレスに関与する『副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRHと呼ばれる)』が脳にたくさん放出され、これによって腸の収縮運動が過剰になったり、けいれん状態になったりします。また、複雑なネットワークをつくる神経が知覚過敏となって、痛みを感じることもあります。
つまり、ストレスが腸の運動異常や知覚過敏に影響して、便秘や痛みをまねくということです」
緊張や不安、さらに感染症も原因に
思い当たる人も多いと思います。三輪医師は
「前回に話したように、会議や面談、受験などで緊張が強いときや、電車や車での移動で長時間トイレにいけないときに、『おなかが痛くなったらどうしよう』と不安になっておなかが痛む、張る、便秘や下痢をすることがあります。これは自律神経のバランスが乱れて消化吸収が悪くなり、腸の運動や神経に影響するからです。過敏性腸症候群の原因が特徴、症状につながります」と話し、原因について次の説明を加えます。
「ほかに、風邪やインフルエンザ、新型コロナ、ノロウイルス、食あたり、食中毒などで細菌やウイルスによる『感染性腸炎』にかかったあとも、過敏性腸症候群になりやすいことがわかっています。
感染症によって腸に炎症が残っていると、腸の運動や知覚に変化が起こることが原因と考えられます」
女性ホルモンの影響で便秘になりやすい
では、過敏性腸症候群の便秘型には女性が多いとのことでしたが、それはなぜでしょうか。三輪医師はこう説明を続けます。
「女性ホルモンの影響が考えられます。月経後約2週間の排卵期から月経前には、女性ホルモンの1つの黄体ホルモン(プロゲステロン)が多く分泌されます。
プロゲステロンは腸管から水分を吸収して便を硬くし、また大腸のぜん動運動を抑えます。そのため、月経後2週間~次の月経直前の時期には便秘になりやすいのです」
その時期は、肌荒れ、イライラや憂うつ感などが現れることも知られています。
「この時期にストレスが重なると、睡眠不足や食欲不振などで自律神経のバランスが乱れ、よりストレスが強くなって、先の述べた脳腸相関が悪循環に働きます。
過敏性腸症候群の場合は、『病院で検査をしても器質的な病気はみつからないのに、このおなかの痛みはなんだろう?』と原因がわからないこと自体がストレスとなり、さらに便秘や腹痛をまねくこともあります」(三輪医師)
原因がわからないまま便秘が続く、腹痛があるのはつらいと思います。
「まずは原因を理解することが重要です。自己判断で市販の薬を飲んでも、選び間違っていることもよくあります。一度は消化器内科や内科を受診して原因を探りましょう」と三輪医師。
聞き手によるまとめ
便秘型の原因としてストレスが挙げられ、それによって腸が過敏に運動することや、知覚過敏となって痛みを伴う便秘をまねくということです。市販薬で効果が見られない場合は、自分の身に起きている便秘と腹痛の原因を知るために医療機関を受診しましょう。次回・第3回は、病院での治療法について尋ねます。
(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)