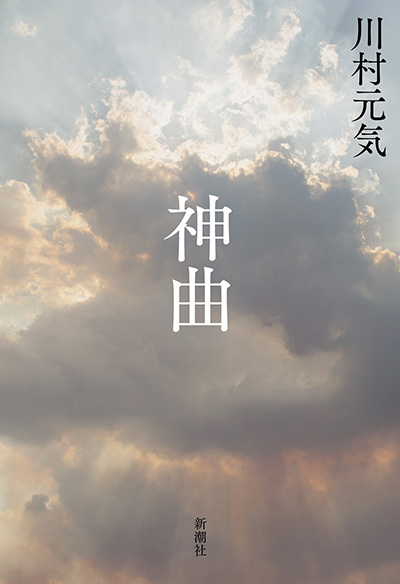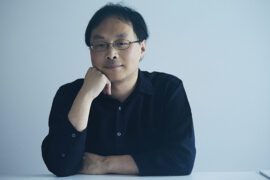小説家、脚本家、映画プロデューサーなどさまざまな顔をもつ川村元気(かわむら・げんき)さんの2年半ぶりの長編小説『神曲』(新潮社)が11月18日に発売されました。
通り魔に息子を殺され、ある「神」を信じることになった一家の、秘密と崩壊、再生を描いた物語。信心と不信、そして「目に見えないけれども、そこにあるもの」を描いています。
執筆期間はちょうど新型コロナウイルス感染症まん延の時期と重なったという川村さんに、なぜ今「信仰」をテーマにした小説を書いたのか、お話を伺いました。前後編。
「不信」が溢れている世界で描きたかったもの
——川村さんと言えば、全世界累計200万部を突破したベストセラー『世界から猫が消えたなら』を2012年に刊行して以来、『億男』『四月になれば彼女は』『百花』など話題作を次々に発表されています。今回の『神曲』は2年半ぶりの長編小説ですが、「宗教」や「信仰」をテーマに執筆された経緯をお聞かせください。
川村元気さん(以下、川村):僕は映画の仕事もあるので、小説は2、3年に1作しか書けません。それだけに、毎回「今、自分自身が不安なことを解決するために」小説を書くんです。常に「世間は今どんな気分なんだろう?」ということを考えているのですが、自分にとって切実なことは同時代を生きる皆にとっても同じであろうと仮説を立てて書いていく。今は世界に「信じられるものがとても少ない」気がして、でも「不信にまみれて生きる」のは嫌で、そこを書きたいと思いました。
——どういう意味でしょうか?
川村:今はインターネットで検索すれば何でも分かったような気になれます。僕も日々ネットに頼って生きているのですが、一方で世間を見渡すと「有名な神社に行ってきた」とか「あの占い師は当たる」とか目に見えない存在への依存度が、以前にも増して上がっている気がして……そのアンバランスさに興味を持ちました。
もともと「神様」や「宗教」のようなものをテーマにしたいという気持ちはあったのですが、それを直接的に書いても自分が読みたい物語にならない。どちらかと言うと、それを信じ切ってしまう人間とか、どうしても信じることができない人間のことを書きたかったんです。
——川村さん自身は神や宗教についてどんなふうに思っているのでしょうか?
川村:基本的に僕はうたぐり深い人間で……。占いや宗教などに対してはどこか斜めに見てしまうところがあって、何かを信じ切れることに憧れがあります。でも、今の自分のような人が実はマジョリティではないか、つまりそれが世間なんじゃないかと思ってもいるんです。
それでまずは「強く信じる気持ち」を知りたくて、宗教やスピリチュアルに関する取材を始め、100人以上の方に取材をしたのですが、結局僕が書きたいものは「信じられない人の物語」なんだと気付いたんです。神や信仰について調べれば調べるほど「何も信じられない」という気持ちが、世間や日常にまん延していると感じました。
——具体的にどんな場面で感じますか?
川村:顕著なのがインターネットの中ですよね。ネットやSNSが不信感の集積場になっている。コロナ後においても、自分の家族ですら分からない存在になりつつある。子供が何を考えているか分からないとか、夫婦がお互い信じられないとか。そして「疑う」ことがベースのスタンスになっていて、それがある種の知恵というか理性であり正義になっている感じもあります。
でも、いろんなことを疑って信じないでいようとする人もあまり幸せそうにも見えない。信じることの危うさもあるわけですが、一方で信じないで理性的に生きている人たちもあまり幸せそうに見えないのはなぜだろう? と。要するに、幸福論が僕の一貫したテーマなんです。それを「生き死に」で書いたのがデビュー作の『世界から猫が消えたなら』だし、恋愛で書いたのが『四月になれば彼女は』です。人は何をもって幸せと感じるか? をずっと書いてきたので、そういう意味で今回も信じること、もしくは不信と「幸せ」の関係性にすごく興味がありました。
あとはここ数年、ずっとテーマにしたいと思っていたのが、「目に見えないけれど、そこにあるもの」だったんです。今回の小説にもお守りをゴミ箱に捨てられないというエピソードが登場しますが、お守りってゴミ箱に捨てられないですよね?
——捨てられないです。
川村:初詣も行かないと、ちょっと気持ち悪いですよね。普段、信仰に熱心というわけでなくても、それは思いますよね。ほかにも「あいつは本当に雨男だ」「私は晴れ女だ」とか言うじゃないですか。何を根拠に? という話なんですけれど。
——日常に転がっていますよね。
川村:いっぱいあるんですよ。そういうことを人が信じてしまうし、信じたいと思う。その正体を書いてみたかったっていうのはありますね。
コロナ禍、東京五輪…最悪の終わり方をするかもと思いながら書き進めた
——小説は第1章が、息子を殺され信仰の道に突き進んでしまう妻を止めようとする「三知男」、第2章が信仰の世界に漬かることになる三知男の妻の「響子」、そして第3章が二人の娘で信心と不信のあいだで揺れる「花音」の視点から構成されています。個人的な話で恐縮ですが、私は特に花音に感情移入しながら読み進めました。
川村:まさに僕が書きたかったのは、花音という人なんです。どっぷり信仰に漬かっている母親とどこか信じられない父親、その信心と不信の間で揺らいでいるのが花音であり世間。どんな結論になるか分からないで書いていった部分はあるので、花音という娘をどう書くかは自分の中で大きなことでした。
——川村さん自身もどんな結論になるか分からなかったのですね。
川村:小説の面白いところは書き手が結論を決めずに書けることなんです。映画の場合は結論ありきでそこに向かって全体をどう構成して脚本を作るかなのですが、小説の場合は著者が結論を分かって書いているものほどつまらないものはないと思っています。書き手も真理を知りたくて揺さぶられ続けるというか、これはどんな結論になるんだろう? と分からないで書いていることが物語をけん引する力になる。同時に、答えなんかないのかもしれないけれど、自分の中でどう落とし所をつけるか分からないで書いているからこそ面白いとも言えます。そして、著者が予想できていないことは読者も絶対予想できないだろうと前向きな気持ちでやっているのもあるのですが(笑)。
書いている2年の間に、世の中はコロナになったり、オリンピックがあったりなかったり、結構すごい2年間で、同時に急速に憎悪や不信が渦巻いていった2年間でした。小説を書き始めた当初はもっと最悪の終わり方になるかもなと思いながら書いていましたし、先日インタビュアーの方に言われたのが「すごく最悪な落ちになるかもしれないと思いながら読んだ」と。
——ちょっと分かる気がします。
川村:僕もそう感じていたのですが、映画の撮影をしてるときにたまに起こることなのですが、雨が降ってきちゃって「もう今日は撮れないね」というときにでももう少し待ってみようかと待っていたら急に晴れたりすることが自然現象として起こるんです。みんな天気予報を見て、晴れとか曇りとか雨というのを見てるけれど、実際に撮影現場で10時間とか20時間も天気と向き合ってると、そこにはものすごく複雑なレイヤーがあるんです。今回、表紙は川内倫子さんの写真を使わせていただいたのですが、本当にこの写真のように雷雨の中から急に晴れ間が見えたんです。そんな感じでした。
——晴れ間が見えた瞬間があった?
川村:僕にとってはこの小説の結末は晴れ間だったんだなって。投げっぱなしにして「あとは考えてください」「信じることは悲痛ですよね」というふうにはどうしても終わらせられなかったし、最後は花音たち少年少女が主人公になっていくので、悲痛なまま終わらせるべきではないと思ったんです。信じることを呪いたくなかったし、信じないスタンスを肯定もできなかった。おそらくそれは、まだコロナ禍の中にいる自分自身が信じたいことだったのかなとは感じました。
“不在”によって描いたコロナ禍
——コロナを思わせる描写もありますが、コロナ禍が作品に与えた影響は大きかったですか?
川村:もう迷惑でしたね(笑)。書いてるときにコロナが来て。今、作家の間でコロナを書くか書かないか問題が大きくて。コロナそのものを書くのはつまらないよねというのは共通のスタンスだと思うのですが、だからと言ってコロナがなかったかのように書くのも違うんじゃないかって。
——嘘っぽいっていうことですか?
川村:世界がね、パラレルワールドになっちゃうじゃないですか。
——確かに違う世界を見てる感じになっちゃいますね。
川村:僕の一貫したスタンスは、書きたいことを空洞にして書くこと。不在によってそれを書くということなのですが、それは『世界から猫が消えたなら』から一貫している。「ない」を一所懸命に書くと、「ある」が見えてくる。
『神曲』でも、神を信じられない人を描いているうちに、「信じるということ」が見えてくる。本作は、コロナも空洞になっています。書いている途中にコロナウイルスが来て、そのとき僕が決めたのは、第1章はコロナが来た瞬間で終わらせる。第2章は、コロナが落ち着いた4年後を描きました。そうすると、その間に何があったかは一切書かれていないけれど、その間にどんなふうに人々の気持ちが変わって、何に依存するようになったのかが書けると思いました。近年、新興宗教は組織されにくくなっていますが、だからといって何かを信仰する気持ちはなくならない。だから、いろんなものに形を変えてそこに「ある」んです。
あまり具体例としては出せないですが、いろいろなタイプの信仰を『神曲』では書きました。最初は「宗教」や「神」というと狭いテーマかなと思ったのですが、取材をしていくたびに家族や親戚、友人も含めて、そういう「怪しげな信仰」にかすらない人は、いないと気づきました。みなの共通した不安であり、欲望なのだと。
——周りでも親や家族が何かの宗教を信仰しているという人はいますし、ライトなもので言うと朝は占いをチェックするし、月曜にはしいたけ占いを見るし……。
川村:しいたけ占いって本当に当たってますよね。当たってるっていうか、当たってるって思いたいのかもしれないけれど。
「まだ言葉になっていないもの」を言葉にしたい
——花音が外の世界に目を向けるきっかけを作った隼太郎について伺いたいです。隼太郎は花音の母親の響子に言わせれば「悪魔にとりつかれ」た、質問をしても質問でしか答えない「人を食ったもの言い」をする人物です。善悪のジャッジをすることに慎重になっている人物なのかなと思ったのですが、隼太郎に込めたものは?
川村:まさにそれです。みんな白黒つけたがるし、勝ち負けを決めるのが好きだけど、そういうことをやってるから戦争か炎上しかなくて、ずいぶん幸福とかけ離れてるなって。僕は灰色が好きだし、天気雨のような空が好きなんです。黒とか白とかはっきりするのは面白くないというか、人間自体そういう複雑な信仰をもつものだと思っているんです。
自分の正義だけを主張しきれる人は怖い、という気持ちがありました。ほとんどの人がそれをできないし、好ましいと思っていないんじゃないかなと。
やっぱり、僕はどうしても世間の中に眠る、みんなが切実に思っていたり感じたりしているんだけど、まだ言葉になっていない“気分”を、物語にしたいという欲望がすごくあるんです。それって黒とか白とかはっきりしたメッセージではなくてすごく曖昧なものなのですが、結構、核心をついた不満や欲望、恐怖で、そんなことを多くの人が抱えているんじゃないかと信じて書いています。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)
※後編は11月20日公開です。