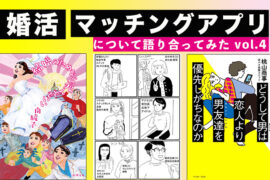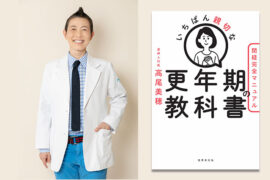傷付いた心を救済する場面が見たがられている?
スー:男性のホモソーシャル、つまり同性同士の友好関係については、それ自体が問題というよりも、それを維持していくために女性を自分たちと同じ心を持つ人間として扱わなかったり、同性愛者に対する嫌悪をあらわにしたり、上下関係による順位づけ、つまり家父長制的なものをベースにすることでないがしろにされる人が出てくる点が問題だと思うのですが、その点に関してご自身の体験談というか、記憶はありますか?
松居:同性同士の友好関係と、異性や同性愛者への考え方は別物じゃないですかね。そういうふうに偏見を持ってしまう人は、同性同士の友好関係を維持するためにではなく、ただ単純に、別のところに問題があるというか。例えば自分のプライドだったり、自分の培ってきた感性を肯定するために、自分のものさしでは測れないものを否定している気がします。
自分の父がいわゆる亭主関白な九州男児で、母がテレビに出たり、書きたいものを書いたりするものに対して露骨に嫌悪感を示したのは、自分の過ごしてきた環境にないものを受け入れることができなかったからのような気がしますね。
スー:松居さんの作品では男の子たちの楽しい時間が描かれることが多い印象で、彼らは権力を持たない側の人たちですよね。ただ、その人たちが女性とどう関わるかとなると、また別のレイヤーが生まれてくると思うんです。わかりやすい搾取がないにしても、女性を人間として見られるのか、みたいな問いが来るわけじゃないですか。どうですか?
松居:そこで知ってます感を出すのも変なんですよね。知ろうとしても、実感を持って知ることはできないから。じゃあ、どんな痛みを受けたかって、それを知ってるふうに装うことも不誠実な気がしていて。
でも映画や演劇は、一人で作っているわけではないので、責任転嫁ではなく、一緒に作っている人たちに言葉を聞ける。そこで自分の知らない景色も教えてもらって、それこそ一緒に作ってその景色を描いていくしかないかなと思います。
スー:『くれなずめ』(全国公開中)で前田敦子さんが演じるミキエって、怖くてトゲトゲしくて。でも、それは「彼女の真の姿」ではなく、彼らから見た彼女なんですよね。
松居:そう。あれは、彼らの思い出の中での彼女です。
スー:彼らがいないところの彼女は描かれてないですもんね。根底に愛情があるので、見る人はそこを読みとってほしいな。
松居:一つスーさんに聞きたいのが、例えば「ブスだ」という台詞(せりふ)があったとして、それが容姿云々の意味ではなく、関係性からくる愛情ゆえの裏返しの言葉として言っていても、言葉の表面だけで作中の精神性を否定されるっていうのは、かなり表現にとって残酷なものなのですが、どう思いますか? 文脈を読み取ってもらうためにどう情報を補完すればいいんだろう、でもその補助線を引けば引くほど登場人物の生きる言葉ではなくなってしまう難しさがあって。
スー:作中でも日常的な会話でも、文脈や関係性を無視した言葉の切り取りは非常に危ういと思います。ただ、いまのムード、あえて「ムード」という言葉を使いますが、は「ブスだ」と言われた側の傷付いた心を救済する場面、もしくは言った側がなんらかのきっかけで態度を変える場面なんかが求められているようにも感じる。
松居:例えば、愛していることを伝えるときに、「愛してるよ」とスマホを触りながら言うのと、「大嫌いだよ」と抱きしめて言うならば、後者のほうが自分には意味が伝わるというか。むしろそうやって言葉や情報を無価値にしていくことが視覚的世界で表現する意味の一つとは思っていて。
スー:わかるわかる。言葉と裏腹な登場人物の心情が伝わってきますよね。「愛してる」と「大嫌い」は言葉を発する側の相手に対する感情だから別に問題ないんじゃないかな。ブス、デブ、チビ、ハゲなんかは他者による容姿のジャッジととられる可能性はあるけど。
たとえば女の子がスマホで自分の自撮りを見ながら「私、ブスだよねえ」と独り言のようにつぶやいて、それを耳にした横に座ってる彼氏が写真も見ずに「うん、ブスだね」と答える。彼女が「もー!」とか言ってバシン! と彼の肩を叩く。そういう流れなら文脈的に、彼は彼女のことをブスだとは思っていないと伝わるとは思いつつ、そのあと別の場面で、彼が彼女に「きみはめちゃくちゃかわいいよ」と伝える場面が出てくると、いまのムードとしては見てる側に救済を与えるのではないかなとも思う。良い悪いではなく、そういう場面が見たがられているというか。
松居:なるほど。ちょっと譬(たと)えがズレてしまいました。しかし、救済というのは、確かにそうですね。
誤解されないようにされないようにし尽くした果てに、描きたいものすら潜らせてしまうとつまらないものになる恐れがあるので、そこを気にするよりは、何か言葉が上がってきた時にそれをちゃんと受け止めたいですね。
スー:ただ、正しさのチェックボックスを全部埋めたら必然的につまらなくなるって話でもないのが難しいところで。チェックボックスを全部満たした上で面白いものを作る人がまだ少ないというだけの話だから。と同時に、正論で割り切れないところを描くのも、松居さんの仕事だし、私の仕事だし。
今って、互いの信頼関係がある上でないと伝わらない言葉が結構はっきり存在しています。私はよく「ストリートの話」という言い方をするんですけど、つまり正論としての正義だとか正しさというのはもちろんありますけど、明日も道徳的には厳しい環境で食べていかないといけない人たちもいるわけですよね。道徳としての正義と、街場の話、ストリートの話って食い合わせが良いとは限らない。私は街場の話をしていたいし、ストリートの話をしていたいわけです。だってそうしないと、自分の首も締まるから。
松居:実感としては、言語化合戦ですかね。言葉にすればするほど遠くなっていくから、みんなが感覚として理解していけたらいいのになと思いますけど。
スー:バックグラウンドがそれぞれ違うからなかなか難しいですよね。どのものさしを持ってきても、たたこうと思えばたたけてしまいますし。表現者は胆力を試される。本もそうですね。誤読する人ほど言語化するし。
松居:しかもそういう人のほうが、たくさんの言葉を持っている。
スー:伝わってないことは、作り手としての表現力の拙さですけど。でも、今喋っていてわかりました。私は理想の状態を思い浮かべながら、そこと現実、つまりストリートとの間を埋めていく表現をしていけばいいのかなと。
松居:昨日スーさんがLINEで『くれなずめ』を見た感想を送ってくれた時、「一言では言えないけど面白い」ってあって、あれはすごくうれしかったです。
スー:フフフ。松居さん、ナイス反骨心って思いました。このご時世、一言で言えた方がバズるし売れるけど、日常って大きな事件で動くものじゃないし、同じことの繰り返しのレイヤーがミルフィーユみたいに少しずつ重なって、地層みたいに表情を変えていくから。ひと言では言えないものが広まったら、また景色も変わるでしょうね。
松居:ここがこうでこうで面白かったと言われるより、「何かわからないけど面白かった」と言われるほうが気持ち的にはうれしかったりします。言語化されたくないと思いつつ、言語化しないと届かない、という狭間(はざま)にいます。
スー:的確に言語化できるものも、あるにはあるんですよ。言語化自体が悪いとは思わない。でも、シンプルに言語化される着地から逆算してフォーマットに沿ったもの作りをしたらつまんなくなるんでしょうね。体験する側のデヴァイスを作り手が想定して、SNSでバズることから逆算して作る行為には限界がある。商売として、着地には目配せはしますけど。
自分たちの時代の価値観にどう落とし前をつけるか
スー:想像力をどこまで働かせられるか。二十歳くらいの子たちって、全然違いますもんね。ジェンダーがどうってことを話していること自体のベースが違う。
松居:そうなんですよ。そっち、結構気になります。
スー:もちろんレイヤーもグラデーションもあるけど。二十歳くらいの娘さんを持つ方がおっしゃっていたのは、自分が好きなのは女性なのか男性なのかまだはっきりしていなくて、どっちもあると思うくらいの揺らぎをおおらかに受け止めているって。と同時に、キャバクラで稼いでみたいと素直に親に言える子もいる。目に見える範囲としての「ここからここまでOK。それ以外は社会的に罰せられます」が、我々の世代と比べてかなり少なくなっているように思います。男の子のマニキュアやメイクも、特別なことではなくなっていくでしょうし。
松居:感覚で理解できるまで、わかったふりするしかないんですかね?
スー:えー。でもわかんないことを作品にはできないでしょう。したくないでしょう。
松居:そうですね。わかったふりしちゃうと4、5年でやめちゃいそう。自分もしんどいし、周りもしんどい。あとは、作り方を変えるというのはあるかな。監督は、脚本家、プロデューサーと組むことができるので、純粋自分オリジナルは舞台でやりつつ、映像はハイブリッドでいくとか。
スー:ハイブリッドがいいと思う。新しい時代になれば、私たちは、過去の人たちがそうだったように、必然的に取り残されていきます。そこで自分たちの時代の価値観にどう落とし前をつけるか、が問われてくるのかと。我々は決して罪のない世代ではなくて。非常に暴力的かつ支配的な笑いだったり面白さというものに、小さな疑問を抱きながらも体に染みついてて、多少なりともそれを下にやってきた過去がある。恩恵も受けてきた。時代が変わりつつある今、それとどう向き合うか。振り返れば産廃がしっかり残っているし、全然平気で続けてる上の世代もいるし、下の人たちはそういうことを本当に毛嫌いしてる。