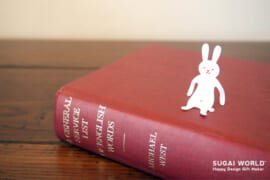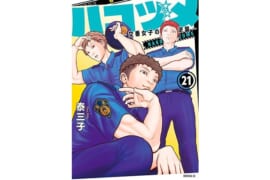仕事に家庭にと悩みが増えるこのごろ、布団に入ってもなかなか寝つけないことはありませんか。ストレスや不安感で眠れないことが続くときの改善策のひとつとして、漢方薬があるということを耳にしました。
漢方専門医で臨床内科専門医、消化器内視鏡専門医でもある吉田裕彦医師に聞くと、「漢方では、体の不調と精神の状態は深く関係しているととらえます。ストレスや生活習慣を改善したうえで漢方薬を適切に選ぶと、良い眠りを取り戻すことが期待できるでしょう」と話します。
そこで、漢方薬をどう選べばよいかについて詳しく聞いてみました。
ストレスや不安で脳が興奮すると眠りの質が悪くなる
——厚生労働省発表の平成27年「国民健康・栄養調査」によると、「20歳代~30歳代の約3割の女性が、睡眠の質に何らかの不満をもっている」という報告があります。睡眠の質が悪いとは、具体的にどういったことなのでしょうか。
吉田医師 不眠の状態はさまざまで、医学的には、「寝つきが悪い入眠障害」、「途中で何度も目が覚めて寝つけなくなる中途覚醒」、「早く目が覚めてそれからは眠れない早朝覚醒」、「少しの物音でも目が覚めるなど熟睡ができない熟眠障害」に分けて考えています。複数の症状がある人もいます。
——なぜそういった症状が出るのでしょうか。引き金となる要因はありますか。
吉田医師 自律神経の働きが強く影響します。自律神経は昼は積極的に活動して夜は休息するように働きますが、昼夜逆転などで生活時間が不規則になる、また、栄養のバランスが整った食事がとれておらず時間も不規則だ、運動が十分ではない、お酒をたくさん飲むなど、日常の過ごし方、食生活のありようが乱れがちになると睡眠の質は低下します。
さらに、悩みがある、ストレスや不安感が強いとき、あるいは寝る直前までパソコンやスマートフォンを操作しているなどだと、布団に入っても脳の興奮状態が続いて自律神経が休息モードに切り替わりにくいため、質のよい睡眠を妨げることになります。
——楽しいイベントの前にはワクワクして眠れないこともあります。睡眠にはいろいろな精神の状態が関わっているということでしょうか。
吉田医師 東洋医学では、日中は「陽」、夜半は「陰」の状態にあるのが自然であり、この調和がとれているときはスムーズに眠りにつけると考えます。このバランスが崩れると、心身が休まらない、不眠の症状が現れることがあります。不眠は、生活全体のバランス、また、体と精神の調和の乱れを知らせるサインの一つと考えて注意をしましょう。
疲れの度合い、冷えやのぼせなどの体調を加味して選ぶ
——漢方薬を選ぶとき、具体的にどのように考えればよいのでしょうか。
吉田医師 自分の体質や体格と精神の状態を考え合わせましょう。
ストレスや不安が強くて眠れないときはまず、自分の精神の状態を見つめてください。「イライラして気になることが頭から離れない」、「ささいなことなのにクヨクヨと心配になる」、「ちょっとした怒りがぶり返して落ち着かない」、「疲れてクタクタなのに目がさえる」などのどれに近いかを探ります。複数の場合もあるでしょう。
また、睡眠には一定の体力が必要ですので、疲れが激しい場合もよい眠りが得られにくくなります。自分の日ごろの体力の程度と不調の具合、例えば、疲労度や疲れに伴う症状のめまいやふらつき、冷えやのぼせがあるかなどを考慮しましょう。実際には、次のような漢方薬があります。
加味帰脾湯(かみきひとう)
・体格や体質:体力は中等度以下、食欲がない、虚弱体質、血色が悪い
・症状:疲労感が強い、貧血、イライラする、不安が強くて眠れないなど
桂枝加竜骨牡蠣湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
・体格や体質:体力は中等度以下、やせ気味で顔色がよくない
・症状:疲れやすくてクタクタ、ささいなことがクヨクヨと気になる、興奮して眠れないなど
柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
・体格や体質:体格がよく、体力は中等度以上
・症状:ささいなことでイライラする、便秘がある、動悸(どうき)がある、不安感や緊張感が強くて眠れないなど
抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
・体格や体質:体力は中等度、やや胃腸が弱い
・症状:怒りっぽい、神経が高ぶる、神経質、イライラが強くて眠れないなど
黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
・体格や体質:体力は中等度以上、のぼせやすい、顔色に赤みがある
・症状:ささいなことでイライラする、落ち着かないなどで眠れない、胃炎がある、めまい、動悸(どうき)、湿疹、皮ふ炎、皮ふのかゆみ更年期障害など
加味逍遙散(かみしょうようさん)
・体格や体質:体力は中等度以下、虚弱体質、のぼせやすい、冷え性、
・症状:疲れやすく、イライラして眠れない、便秘がある、月経困難、更年期障害など
——自分の症状が複数の薬の特徴にあてはまるなどで、迷ったときはどうすればいいでしょうか。
吉田医師 目安となるポイントを挙げましたが、パッケージに記述されている特徴を読んでもよく理解できないこともあるでしょう。そんなときは必ず、薬局に常駐する薬剤師に相談してください。また、自分の体質がわからない、精神の状態も複雑で選べない、それに市販の薬を2週間ほど服用しても睡眠の質が改善されないときは、内科か心療内科、精神科を受診しましょう。何らかの病気が隠れている場合もあります。
——不眠を改善するために、漢方薬という選択肢があるということがわかりました。ありがとうございました。
眠れないときには、部屋の状態や寝具などの環境にばかり目が向きがちでしたが、毎日の過ごし方や精神、体の状態と睡眠の質が深く関わっていることを改めて知りました。ストレスやイライラ、不安感はどうしようもないなどと諦めずに、生活習慣を見直しながら、ときに漢方薬の力を借りてよい眠りを手に入れたいものです。
(取材・文 ふくいみちこ×ユンブル)